【徹底ガイド】南半球の極軸合わせ・西オーストラリア遠征記【第2回】
こんにちは!天リフ編集部です。西オーストラリア遠征記第2回目は「南半球の極軸合わせ」です。初の南半球で極軸がちゃんと合わせられるのか?ドキドキヒヤヒヤでしたが、結果としてはなんとか無事クリアすることができました!(*)
(*)実は運良くあっさり合わせられてドヤ顔だったんですが^^v
でも、南半球での極軸合わせは確かに一筋縄ではいかないものだと実感しました。事前にきちんと下調べしておかないと絶対に無理!!これだけは断言できます。北半球の極軸合わせが恵まれすぎているのです。その調子で南半球に行くと間違いなくハマります。「2回くらい遠征すればすぐに合わせられるようになる」というのはけだし名言。難しさのレベルを認識して準備さえすれば、初めてでも大丈夫です。
当方のたった1回の経験からではありますが、読者のみなさまが南半球で戸惑うことがないように、体験したノウハウをまとめてみました!これだけ読めば南半球の極軸合わせは大丈夫!
はちぶんぎの台形を探せ!
はちぶんぎの台形と「σ(シグマ)のヒゲ」

これがはちぶんぎの台形です。南半球に行く前に、この星並びを毎日眺めて頭にたたきこみましょう。
ここで問題は、「台形」という星並びがあまりにありふれたものであること。実際に星空を流して見ると、台形っぽい並びがいたるところにあります。
そこで、台形の短い方の端の「はちぶんぎ座σ(シグマ)星」の横にちょんとある、小さな星(HIP112355)を目印にしましょう。この星並びを「台形のヒゲ」または「σのヒゲ」と名付けることにします。このヒゲ、大事です。このパターンが頭に入っていると、一発で台形が認識できるようになります。
ちなみに、台形で一番重要なのはこのσ(シグマ)星です。いってみれば南極星。どんな極軸望遠鏡のパターンであってもσ星は必ず使用します。台形のσ、ヒゲのσ、シグマとヒゲをお忘れなく。

では、小テストです^^上の画像からはちぶんぎの台形を探してみましょう^^4月中旬の薄明終了直後の状態です。

はい、答はこちら。まあ最初は無理ですね^^ でもこの図から台形を見つけられるようになるまで練習しましょう^^
はちぶんぎの台形の見つけ方・小マゼランからたどる方法
北極星は2等星。よほどの光害地でなければ、普通に見つかります。ところが、はちぶんぎの台形を構成する星は5等星以下。光害地や薄明下では肉眼では見えません。これが南半球での極軸合わせを難しくしている最大の原因なのです。

俗に「みなみじゅうじの縦棒を伸ばせば天の南極」「アケルナル(α Eri)と南十字を結んだ線の真ん中あたりが天の南極」と言われています。このことは極軸合わせの必須知識。しっかり記憶に刻んでおく必要があります。
しかしこの見つけ方は、実戦的極軸合わせにとっては荒っぽすぎるため、はちぶんぎの台形を見つけるのはまず無理。肉眼で5等星4個の星並びである台形の視認は困難です。極軸望遠鏡では視野1個ほどずれている上に天の南極からは30°以上離れています。台形を捕まえるのには、みなみじゅうじ座とアケルナルをを頼りにするのは難しいのです。

一番見つけやすい探し方は、小マゼラン星雲からスターホッピングすること。見やすい目印が3つあり、極軸望遠鏡程度の視野なら比較的簡単にたどることができます。しかも、ベストシーズンである4月ごろなら、薄明終了時点で小マゼランはほぼ天の南極と同じくらいの地平高度なので、赤道儀(三脚)を水平にずらして簡単に捕まえられるのです。(筆者はそのパターンで楽しました)^^

拡大図。みずへび座β星は2.8等。明るいです。はちぶんぎ座γ(ガンマ)1〜γ3は5等星で暗いですが、特徴的な3つの星ならびですぐわかります。ここから視野もう一つ分ではちぶんぎの台形です。
◯は極軸望遠鏡の視野です。
小マゼランから
①➡みずへび座β星
②➡はちぶんぎ座β星三星
③➡はちぶんぎ座ν星
は等間隔で一直線隣り合う2つは極望の視野に程よく入るので、①②③とまっすぐホッピングすると簡単ですね。
ニュージーランド在住の人に教えていただきました😄 pic.twitter.com/sUykVOt285
— suika (@Suika95961015) April 25, 2019
この方法はニュージーランド在住の方もオススメだそうです^^@Suika95961015さん、情報ありがとうございます!
はちぶんぎの台形の見つけ方・みなみのさんかく座α星からたどる方法
ところが・・マゼラン雲が天の南極を下方通過するような状態や月明・薄雲で見つけにくい場合は、この方法をとることが難しくなります。
上の画像は半月前の月に照らされた状態。小マゼラン雲はかなり低くなり、肉眼では見つけるのが難しいコンディションでした。しかも小さな雲が流れて「にせマゼラン」あちこちに^^;;

そんなときのBプランは、みなみのさんかく座α星からのスターホッピングが推奨。南のさんかく座α星は1.9等星と明るく、ふうちょう座の三角形も3.8等〜4.7等のわかりやすい星並び。この2つの手がかりは視野の倍くらい離れてはいるのですが、ほぼ等間隔でもありセカンドベストといえるでしょう。小マゼランとほぼ天の南極をはさんで反対側にあるのもBプランに最適。
はちぶんぎの台形を見つけるには、小マゼラン経由、みなみのさんかく座α星経由の2つの方法を覚えておけばまず大丈夫ではないかと思います。
季節による台形の向きの違い
はちぶんぎの台形を見つけることを難しくしている理由は、暗い以外にもう一つあります。北極星による極軸合わせは基本的に星1個。星並びも季節による向きの違いは意識しなくて済んでいたのです。
ところが、はちぶんぎの台形は違います。4つの星でパターン認識をしなくてはならないので、季節による台形の向きを把握していないと台形が見つけられません。

季節別の台形の見え方。どれが台形で、どの方向にアケルナルとみなみじゅうじがあるのか、わかりますか?

答はこちら。知らなきゃまずわからないですよね。でも簡単な覚え方があります。台形の平行な部分を真っ直ぐ伸ばすと「シグマのヒゲのある方がみなみじゅうじ(*)」を向き、反対側が小マゼランとアケルナルを向きます。おお、シグマのヒゲ、使えるじゃありませんか!
(*)ただし、極軸望遠鏡の視野を見ながら実際の空を肉眼で見た場合は逆になることに注意が必要です(後述)。
実戦的には、ステラナビゲータやスカイガイド(Sky Guide)のような星図ソフト・アプリを使って、自分が極軸を合わせるであろう時刻の台形付近の画像キャプチャしたものを事前に準備しておくことをオススメします。
製品別・極望パターン徹底ガイド
「はちぶんぎの台形」を見つけることができれば最大の難関はクリアです。でも、もうひとつ重要な注意事項があります。それは、自分が使用する極軸望遠鏡のパターンをよく理解しておくこと。
お使いの極軸望遠鏡、南半球でどう使うかご存じですか?普通考えもしませんよね。筆者も現実に行くと決まるまではそうでした。でも、実はけっこうパターンにクセがあるんです。多くの極軸望遠鏡では、視野中心に天の南極を導入するとはちぶんぎの台形が一部しか視野に入りません。このため、台形のどの星を使うかは各社でバラバラ。台形以外の星を使うものもあります。この使い方を抑えておかないと、「台形は見つかったけど、そこからどうすればいいかわからない」ことになってしまいます。
そうならないために、代表的な機種のパターンを徹底解説していきましょう。
ビクセン・PF-L(*)
(*)最新モデルPF-LIIより一つ古いですが、視野が少し狭い(倍率が高い)以外は同じです。
今回筆者が使用した極軸望遠鏡です。暗視野照明搭載というのが南半球では非常に強力。はちぶんぎの台形を構成する星はどれも5等級以下。北極星なら明視野照明で明るく照らしても問題ありませんが、台形の場合はそうはいきません。この製品ならかなり暗い星でもパターンを見ながら確認できます。後述の旧モデルとの差は歴然。南半球なら絶対こっちが便利です。
ただし、パターンに台形が描かれておらず、小さな字でσ,χ,τとしか書かれていないので、ν星がどのへんにあるべきかは理解しておく必要があります。
歳差補正の目盛が細かくて見にくいのですが、これはアプリ「PF-L Assist」を使えば大幅に合わせやすくなります。大事なことなのでこの先何度も言いますが、極軸合わせにアプリは強い味方。上の画像のように、基準となる星がパターンのどの位置にあるべきかをビジュアルに示してくれます。
ビクセンPF-LとアプリPF-L Assistの組み合わせはベストマッチ。恐らくこれが一番南天で極軸合わせがしやすい組み合わせでしょう。
ビクセン・PF1.0
PF-Lになる前の旧モデル。北半球では視野の回転角は目盛で合わせるのですが、南半球ではそれは使えず(目盛の打ち方を逆にしなければならないので)、はちぶんぎの台形で合わせます(*)。
(*)台形の一番端の星は収差で見えないと思った方がいいでしょう。
残念なのはアケルナルと南十字の方向を示す線がパターンに入っていないところ。台形を平行に伸ばした方向がアケルナルとみなみじゅうじなのですが、「ヒゲのσ(σ)星」がどれかも書かれていません。①台形のうち天の南極に一番近いのがσ星②台形のヒゲのあるほうがみなみじゅうじ③極望は180°倒立の3つをたよりに、アケルナルがσ星の方向だ、と考えて下さい。

PF1.0の極望パターンは残念ながら歳差には対応していません。なのでアプリPolar Scope Align を使用するのが便利。現在時刻の歳差を考慮した基準星の位置を、画面に表示してくれます。後述しますが、極軸アプリはどんどん活用すべきです。出発前にインストールして、自分のパターンを設定しておきましょう。
Sky-Watcher系

北半球ではアプリを使えばとても合わせやすい時角円型のパターンですが、南半球ではいくつか注意があります。極望パターンにある4つの○は「はちぶんぎの台形」ではありません。準備しないで現場でこの事実に気がつくと死にます^^;;
しかもτ星は書いてあるのに、肝心のσ星もχ星も書いてないし。画面上の×の位置が「ヒゲのσ(シグマ)」、そのすぐ左がシグマのヒゲです。極望パターンは歳差補正には対応していません。Polar Scope Align は必須です。
もうひとつ注意点。北半球では十字を水平にしてパターンのしかるべき位置に北極星を入れればいいのですが、南半球ではパターンが正しい位置になるまで赤緯軸を回す必要があります。状態によっては上の図のようにバランスウェイトが逆さまを向くかもしれません(*)。
(*)ガム星雲が南中する頃がこの形になります。
これ、現場で気がつくと意表を突かれることでしょう。まあやるだけなんですけど。機材構成によってはいったん鏡筒を外してやった方がいいかもしれませんね。
タカハシなどその他の時角円方式パターン

時角円パターンの製品は上の画像のタカハシ(1985-2015)など多数ありますが、基本的には「ヒゲのσ(シグマ)」1星で合わせます。アプリ必須、Polar Scope Align 最強です。アプリが対応したパターンであればまず安心でしょう。基本的に画面上の×点にはちぶんぎσ星を導入すればOKです。
スカイメモRS
スカイメモRSの極望パターン。北半球では評価が高いですが、南半球はちょっとクセがあります。まず、どれがヒゲのσ(シグマ)なのかどこにも書いていません。視野が広いので台形は全部見えるはずなんですが、台形の形も書かれておらず、その代わりはちぶんぎ「10G」「7G」という見知らぬ星のパターンが刻まれています(*)。
(*)はちぶんぎ10Gも7Gも、手持ちの星図・星図アプリのどれにも書かれていない上、星並びからも特定することができませんでした。はっきりいってスルーすべきです。
ただし、みなみじゅうじとアケルナル(α Eri)の方向は書かれています。これを頼りに角度を合わせて、σとχをパターンに入れれば十分でしょう。

Polar Scope Align は「Skymemo RS(S)」にしっかり対応しています。この画面の×の位置にσ星を入れればOK。
実践的ノウハウ集
南半球の極軸合わせで注意すべき点をまとめてみました。
極望は倒立像
ふつうの極望は当然ながら倒立像です。星図アプリや双眼鏡で見える台形とは、上下逆であることに注意しましょう。肉眼では「台形のヒゲのあるほうがみなみじゅうじ」ですが、極望を覗いた状態では反対になります。
暗視野照明と明視野照明
明るい北極星なら、特に視野照明装置なしでもヘッドランプで横から照らしてもなんとかパターン上に配置できますが、5等星以下のはちぶんぎの台形ではそれでは困難です。暗視野照明タイプの極軸望遠鏡が理想ですが、少なくとも簡単にON/OFFないしは光量調整ができる明視野照明を準備しておくべきでしょう。
アプリを活用する
極軸合わせにはアプリ最強です。特に歳差対応していないパターンや時角円方式のパターンの場合には必須です。アプリなら基準星である「ヒゲのσ(シグマ)星」が、パターン上のどの位置にあるべきかをビジュアルに表示してくれます。
ただし、本記事でご紹介したPolar Scope Align はiOS版しかないようです。Androidでどんなアプリがあるのかについては現時点で未調査です。よいアプリをご存じの方は是非コメント下さい。情報が入り次第、追記していきます。
また、無料版のPS Alignは「現在の位置」を手動で変えることができないため、日本から南半球仕様の状態を確認することができません。240円のPro版なら設定できるのですが、たぶんですが無料版でも実際に南半球にいけば大丈夫ではないかと思います(不覚にも現地で試すのを忘れました。。こちらも情報をお持ちの方はお知らせいただけると幸いです)。
基準星を全部無理にパターンに合わせる必要はない
北半球でもいえることですが、極軸望遠鏡のパターンに複数の星が描かれている場合に、律儀に全ての星を同じレベルの正確さで追い込む必要はありません。パターンの回転角さえ正しければ、極軸合わせは1星で十分です。一番大事なのは天の南極に一番近い「ヒゲのσ(シグマ)星」です。残りの星は、回転角合わせの目安程度と考えてよいと思います。
南天では赤道儀は逆回転
極軸合わせとは直接関係ないのですが、当たり前のようで気がつきにくいのが逆回転の設定。南半球では星は逆回りです。赤道儀の設定を変更しないと、2倍恒星時で流れます(経験者多数^^;)
南北設定の変更方法はマニュアルで事前に確認しておきましょう。製品によってはGPSと連動して自動で切り替わるものもあるようです。
それと帰国後に北半球仕様に戻すことも忘れずに^^
Polemaster
こちらは使ったことがないのでコメントできないのですが、たとえPolemasterを使う場合でも「はちぶんぎの台形」は認識できる必要があるので、事前の予習は必須だと思われます。
Pole Masterの南半球での運用事例の情報は少ないのですが、少し古いですが以下の記事に画面キャプチャがあります(*)。
K-ASTEC BLOG – デジタル式の極軸望遠鏡 「PoleMaster」 その-7
http://k-astec.cocolog-nifty.com/main/2016/01/polemaster-7-3f.html
(*)今回の遠征では現地にPoleMasterもあったしK-ASTECさんもいらしたのにその情報をちゃんと取材してこなかったのは大失敗。申し訳ありません。
追記:SharpCap
CMOSカメラ用キャプチャソフトSharpCapの「Polar Alignment」機能(*)です。
(*)ツアーに同行したHさんより情報を頂きました。過去の遠征・日本での使用を含め1年間使われているそうですがもうこれだけでOK、との使用感だそうです。SharpCapは無料ですがPolar Alignmentは年間10ユーロのライセンスキーが必要です。
ガイドカメラとしてCMOSカメラを使用している構成の場合、追加ハードなしで極軸合わせが可能になります。大きな流れは以下の通りです。
- ガイドカメラを天の極付近に向ける
- 極軸を回転させながら撮像(この画像から回転の中心をSharpCapが割り出す)
- 回転の中心がだいたい視野内になるようにカメラの赤緯を調整
- 画像を撮像。この画像から、ShapCapがPlateSolve(星ならびから赤緯赤経を自動判別)し天の極を割り出してくれる
- 画面の指示通りに極軸を上下・水平に動かして極軸合わせ
SharpCapのPlateSolve機能を利用し天の極の恒星の配置を自動認識して極軸合わせを行います(*)。
(*)通常はPlateSolveにはネットワーク接続は必要ですが、天の両極はオフラインでも解決可能とのことです(あまり極から外れると解析できないことになります)
ShapCapは英語表示のみであることもあり、使いこなすにはしっかり事前の練習が必要と思われますが、北半球・南半球に関係なくやることは一緒なので、遠征前に日本で操作方法をマスターすることできるでしょう。
ちなみにPoleMasterの場合は焦点距離25mmのレンズを使用しカメラの視野角は11°×8°です。ガイド鏡のカメラを使用する場合はこれよりも長めになり視野が狭くなることが予想されます(筆者が使用しているGT-40+ASI120MMの構成の場合は1.4°)。このような場合の操作感については、情報が得られた時点で追記予定です(*)。
(*)5/3追記:100mmレンズ+QHY5L2の場合「ちょっと視野が狭いがデータマッチングできる領域にさしかかるとキャッチできる」とのこと。
あると便利な双眼鏡
「台形探し」にあると便利な双眼鏡。台形確認用だけなら低倍率で小口径の双眼鏡で十分ですが、海外の暗い空で双眼鏡は非常に素晴らしい観望アイテムなので、小型の42mm か32mmのダハ式を手に入れることをオススメします。天リフ押しのSVBONYなら42mmでも4000円ほどです。
小マゼランが見えないとき
繰り返しになりますが、小マゼランが見えていないと極軸合わせの難易度が上がります。見えないときは仕方ありません。南のさんかく座αで合わせましょう。
極軸微動は必要か
筆者は今回軽量化のため持っていきませんでしたが、もちろん極軸微動はあった方がいいです。今回の極軸合わせの所用時間は20分程でしたが、その大半は台形が見つかった後の調整でした。微動があれば10分は節約できたでしょう。
極軸微動が台形探しのホッピング用として使えるかどうかはよくわかりません。比較的近い小マゼランからでも極軸微動でホッピングするのは移動量が多くてしんどいかもしれません。
三脚ホッピング
筆者は今回の遠征では「極望を覗いた状態で三脚の南側2本を手で軽く持ち上げて台形を探す」という方法が有効でした。でも、小マゼランが天の南極より上だとこの方法は使いにくいし、重い架台では無理っぽいです。状況によっては便利な方法、くらいのノウハウでしょう。
追記:覗き穴方式の極軸合わせ
ビクセンのポラリエやユニテックのSWATなど、ポータブル赤道儀では簡易的な極軸合わせ方式として「覗き穴」があります。北半球の場合「北極星を覗き穴の中心に入れる」だけでも、最大1度程度までの誤差で極軸が合わせられることになります。
あまり焦点距離の長くないレンズで、短時間の露出時間の場合には実はこれでほとんどの場合こと足ります。また、1/2恒星時追尾で30秒〜60秒露出するような場合なら「だいたい北に向ける」だけでも十分実用になります。
しかし、南半球の場合ではかなり不利です。はちぶんぎの台形を覗き穴の真ん中に入れることは普通は無理でしょう。覗き穴と南天の星野のイメージから「だいたいこのへんだろう」という方向に向けるしかありません。

実際に覗き穴合わせでポラリエを使用して撮影してみました。1コマ3分露出ですが、等倍にするとわずかに流れています。これ以上露出時間を伸ばすことは無理でしょう。
比較明合成してみました。15分で25pxくらい流れています。この撮影時の極軸合わせの精度がどのくらいだったのかは定かではありませんし、流れの原因が極軸のズレなのかもわかりません。
ただ、現場では撮影画像を拡大表示すれば、流れているかどうかはある程度判別できます。この撮影の際も、カメラのモニタで10倍拡大表示して「ほんの少し流れてるみたいだけどまあいいか^^;;」と判断して3分露出で撮りました。結果をきちんと確認して、露出時間を適切に設定すれば、荒っぽい極軸合わせでもなんとかなるものですね。

追記:天の南極ダイレクト導入法
K-ASTEC BLOG・南天専用の赤道儀を作る
http://k-astec.cocolog-nifty.com/main/2019/05/post-3e9d33.html
今回の遠征にも同行されたK-ASTEC様のブログから。天の南極に直接極軸望遠鏡の中心を向ける方法の紹介です。

天の南極は6.8等・7.8等の2個の星からなる三角形(天の南極三角形 )の頂点にあり、「σのヒゲ」から比較的わかりやすいホッピングでたどり着けるそうです。この方法は暗い星を使用するため上級者向けですが、極望に十字線があればどんなパターンでも対応できるのがメリット。南天ツアーをガイドする側の立場の人は、覚えておくと役に立ちそうです。

ただし、歳差による極の移動には注意。リンク先の画像には2000年〜2030年までの動きが示されています。2000年には正三角形だった「南極三角形」は、2019年では上の図のようなややひしゃげた二等辺三角形に。2030年頃には、天の南極はこの2つの星とほぼ一直線になります。そのころになればさらに合わせやすくなりそうですね^^
実録・極軸合わせ動画
今回オーストラリアで極軸を初めて合わせた際の記録動画を撮っています。ご笑覧下さい。風きり音がうるさくてすみません・・
今回持っていったSWAT-310赤道儀とビクセン極軸望遠鏡PF-L(左)。暗視野照明には助けられました。軽量化を優先し、極軸微動装置は大胆にも持っていきませんでした。極軸の上下微動は右の自作三脚アジャスタを使用しました。可動域が狭いのが難点。水平方向はK-ASTECのカーボン三脚PTP-C22の「すり割り方式」の固定部を緩め、手動で回転させて合わせます。北半球では筆者は、この方式でこれまで普通に使っていました(*)。
(*)結局、純正の上下水平微動を買い足しています。やっぱりこっちの方が圧倒的に便利です。
まとめ
いかがでしたか?
とにかく、南半球の極軸合わせは「はちぶんぎの台形」が見つけられるかどうかが第一関門。これがクリアできないとまずお話になりません。第二関門は自分の極望パターンをしっかり理解しておくこと。この2つをきちんと予習しておけば、南半球恐るるに足らず、です!
それでは皆様のご武運をお祈りしております。快適な南半球ライフをお過ごしください!
https://reflexions.jp/tenref/orig/2019/05/01/8519/https://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-1024x538.jpghttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-150x150.jpg天文紀行こんにちは!天リフ編集部です。西オーストラリア遠征記第2回目は「南半球の極軸合わせ」です。初の南半球で極軸がちゃんと合わせられるのか?ドキドキヒヤヒヤでしたが、結果としてはなんとか無事クリアすることができました!(*)
(*)実は運良くあっさり合わせられてドヤ顔だったんですが^^v
でも、南半球での極軸合わせは確かに一筋縄ではいかないものだと実感しました。事前にきちんと下調べしておかないと絶対に無理!!これだけは断言できます。北半球の極軸合わせが恵まれすぎているのです。その調子で南半球に行くと間違いなくハマります。「2回くらい遠征すればすぐに合わせられるようになる」というのはけだし名言。難しさのレベルを認識して準備さえすれば、初めてでも大丈夫です。
当方のたった1回の経験からではありますが、読者のみなさまが南半球で戸惑うことがないように、体験したノウハウをまとめてみました!これだけ読めば南半球の極軸合わせは大丈夫!
はちぶんぎの台形を探せ!
はちぶんぎの台形と「σ(シグマ)のヒゲ」
これがはちぶんぎの台形です。南半球に行く前に、この星並びを毎日眺めて頭にたたきこみましょう。
ここで問題は、「台形」という星並びがあまりにありふれたものであること。実際に星空を流して見ると、台形っぽい並びがいたるところにあります。
そこで、台形の短い方の端の「はちぶんぎ座σ(シグマ)星」の横にちょんとある、小さな星(HIP112355)を目印にしましょう。この星並びを「台形のヒゲ」または「σのヒゲ」と名付けることにします。このヒゲ、大事です。このパターンが頭に入っていると、一発で台形が認識できるようになります。
ちなみに、台形で一番重要なのはこのσ(シグマ)星です。いってみれば南極星。どんな極軸望遠鏡のパターンであってもσ星は必ず使用します。台形のσ、ヒゲのσ、シグマとヒゲをお忘れなく。
では、小テストです^^上の画像からはちぶんぎの台形を探してみましょう^^4月中旬の薄明終了直後の状態です。
はい、答はこちら。まあ最初は無理ですね^^ でもこの図から台形を見つけられるようになるまで練習しましょう^^
はちぶんぎの台形の見つけ方・小マゼランからたどる方法
北極星は2等星。よほどの光害地でなければ、普通に見つかります。ところが、はちぶんぎの台形を構成する星は5等星以下。光害地や薄明下では肉眼では見えません。これが南半球での極軸合わせを難しくしている最大の原因なのです。
俗に「みなみじゅうじの縦棒を伸ばせば天の南極」「アケルナル(α Eri)と南十字を結んだ線の真ん中あたりが天の南極」と言われています。このことは極軸合わせの必須知識。しっかり記憶に刻んでおく必要があります。
しかしこの見つけ方は、実戦的極軸合わせにとっては荒っぽすぎるため、はちぶんぎの台形を見つけるのはまず無理。肉眼で5等星4個の星並びである台形の視認は困難です。極軸望遠鏡では視野1個ほどずれている上に天の南極からは30°以上離れています。台形を捕まえるのには、みなみじゅうじ座とアケルナルをを頼りにするのは難しいのです。
一番見つけやすい探し方は、小マゼラン星雲からスターホッピングすること。見やすい目印が3つあり、極軸望遠鏡程度の視野なら比較的簡単にたどることができます。しかも、ベストシーズンである4月ごろなら、薄明終了時点で小マゼランはほぼ天の南極と同じくらいの地平高度なので、赤道儀(三脚)を水平にずらして簡単に捕まえられるのです。(筆者はそのパターンで楽しました)^^
拡大図。みずへび座β星は2.8等。明るいです。はちぶんぎ座γ(ガンマ)1〜γ3は5等星で暗いですが、特徴的な3つの星ならびですぐわかります。ここから視野もう一つ分ではちぶんぎの台形です。
◯は極軸望遠鏡の視野です。小マゼランから①➡みずへび座β星②➡はちぶんぎ座β星三星③➡はちぶんぎ座ν星は等間隔で一直線隣り合う2つは極望の視野に程よく入るので、①②③とまっすぐホッピングすると簡単ですね。ニュージーランド在住の人に教えていただきました😄 pic.twitter.com/sUykVOt285— suika (@Suika95961015) April 25, 2019
この方法はニュージーランド在住の方もオススメだそうです^^@Suika95961015さん、情報ありがとうございます!
はちぶんぎの台形の見つけ方・みなみのさんかく座α星からたどる方法
ところが・・マゼラン雲が天の南極を下方通過するような状態や月明・薄雲で見つけにくい場合は、この方法をとることが難しくなります。
上の画像は半月前の月に照らされた状態。小マゼラン雲はかなり低くなり、肉眼では見つけるのが難しいコンディションでした。しかも小さな雲が流れて「にせマゼラン」あちこちに^^;;
そんなときのBプランは、みなみのさんかく座α星からのスターホッピングが推奨。南のさんかく座α星は1.9等星と明るく、ふうちょう座の三角形も3.8等〜4.7等のわかりやすい星並び。この2つの手がかりは視野の倍くらい離れてはいるのですが、ほぼ等間隔でもありセカンドベストといえるでしょう。小マゼランとほぼ天の南極をはさんで反対側にあるのもBプランに最適。
はちぶんぎの台形を見つけるには、小マゼラン経由、みなみのさんかく座α星経由の2つの方法を覚えておけばまず大丈夫ではないかと思います。
季節による台形の向きの違い
はちぶんぎの台形を見つけることを難しくしている理由は、暗い以外にもう一つあります。北極星による極軸合わせは基本的に星1個。星並びも季節による向きの違いは意識しなくて済んでいたのです。
ところが、はちぶんぎの台形は違います。4つの星でパターン認識をしなくてはならないので、季節による台形の向きを把握していないと台形が見つけられません。
季節別の台形の見え方。どれが台形で、どの方向にアケルナルとみなみじゅうじがあるのか、わかりますか?
答はこちら。知らなきゃまずわからないですよね。でも簡単な覚え方があります。台形の平行な部分を真っ直ぐ伸ばすと「シグマのヒゲのある方がみなみじゅうじ(*)」を向き、反対側が小マゼランとアケルナルを向きます。おお、シグマのヒゲ、使えるじゃありませんか!
(*)ただし、極軸望遠鏡の視野を見ながら実際の空を肉眼で見た場合は逆になることに注意が必要です(後述)。
実戦的には、ステラナビゲータやスカイガイド(Sky Guide)のような星図ソフト・アプリを使って、自分が極軸を合わせるであろう時刻の台形付近の画像キャプチャしたものを事前に準備しておくことをオススメします。
製品別・極望パターン徹底ガイド
「はちぶんぎの台形」を見つけることができれば最大の難関はクリアです。でも、もうひとつ重要な注意事項があります。それは、自分が使用する極軸望遠鏡のパターンをよく理解しておくこと。
お使いの極軸望遠鏡、南半球でどう使うかご存じですか?普通考えもしませんよね。筆者も現実に行くと決まるまではそうでした。でも、実はけっこうパターンにクセがあるんです。多くの極軸望遠鏡では、視野中心に天の南極を導入するとはちぶんぎの台形が一部しか視野に入りません。このため、台形のどの星を使うかは各社でバラバラ。台形以外の星を使うものもあります。この使い方を抑えておかないと、「台形は見つかったけど、そこからどうすればいいかわからない」ことになってしまいます。
そうならないために、代表的な機種のパターンを徹底解説していきましょう。
ビクセン・PF-L(*)
(*)最新モデルPF-LIIより一つ古いですが、視野が少し狭い(倍率が高い)以外は同じです。
今回筆者が使用した極軸望遠鏡です。暗視野照明搭載というのが南半球では非常に強力。はちぶんぎの台形を構成する星はどれも5等級以下。北極星なら明視野照明で明るく照らしても問題ありませんが、台形の場合はそうはいきません。この製品ならかなり暗い星でもパターンを見ながら確認できます。後述の旧モデルとの差は歴然。南半球なら絶対こっちが便利です。
ただし、パターンに台形が描かれておらず、小さな字でσ,χ,τとしか書かれていないので、ν星がどのへんにあるべきかは理解しておく必要があります。
歳差補正の目盛が細かくて見にくいのですが、これはアプリ「PF-L Assist」を使えば大幅に合わせやすくなります。大事なことなのでこの先何度も言いますが、極軸合わせにアプリは強い味方。上の画像のように、基準となる星がパターンのどの位置にあるべきかをビジュアルに示してくれます。
ビクセンPF-LとアプリPF-L Assistの組み合わせはベストマッチ。恐らくこれが一番南天で極軸合わせがしやすい組み合わせでしょう。
ビクセン・PF1.0
PF-Lになる前の旧モデル。北半球では視野の回転角は目盛で合わせるのですが、南半球ではそれは使えず(目盛の打ち方を逆にしなければならないので)、はちぶんぎの台形で合わせます(*)。
(*)台形の一番端の星は収差で見えないと思った方がいいでしょう。
残念なのはアケルナルと南十字の方向を示す線がパターンに入っていないところ。台形を平行に伸ばした方向がアケルナルとみなみじゅうじなのですが、「ヒゲのσ(σ)星」がどれかも書かれていません。①台形のうち天の南極に一番近いのがσ星②台形のヒゲのあるほうがみなみじゅうじ③極望は180°倒立の3つをたよりに、アケルナルがσ星の方向だ、と考えて下さい。
PF1.0の極望パターンは残念ながら歳差には対応していません。なのでアプリPolar Scope Align を使用するのが便利。現在時刻の歳差を考慮した基準星の位置を、画面に表示してくれます。後述しますが、極軸アプリはどんどん活用すべきです。出発前にインストールして、自分のパターンを設定しておきましょう。
Sky-Watcher系
北半球ではアプリを使えばとても合わせやすい時角円型のパターンですが、南半球ではいくつか注意があります。極望パターンにある4つの○は「はちぶんぎの台形」ではありません。準備しないで現場でこの事実に気がつくと死にます^^;;
しかもτ星は書いてあるのに、肝心のσ星もχ星も書いてないし。画面上の×の位置が「ヒゲのσ(シグマ)」、そのすぐ左がシグマのヒゲです。極望パターンは歳差補正には対応していません。Polar Scope Align は必須です。
もうひとつ注意点。北半球では十字を水平にしてパターンのしかるべき位置に北極星を入れればいいのですが、南半球ではパターンが正しい位置になるまで赤緯軸を回す必要があります。状態によっては上の図のようにバランスウェイトが逆さまを向くかもしれません(*)。
(*)ガム星雲が南中する頃がこの形になります。
これ、現場で気がつくと意表を突かれることでしょう。まあやるだけなんですけど。機材構成によってはいったん鏡筒を外してやった方がいいかもしれませんね。
タカハシなどその他の時角円方式パターン
時角円パターンの製品は上の画像のタカハシ(1985-2015)など多数ありますが、基本的には「ヒゲのσ(シグマ)」1星で合わせます。アプリ必須、Polar Scope Align 最強です。アプリが対応したパターンであればまず安心でしょう。基本的に画面上の×点にはちぶんぎσ星を導入すればOKです。
スカイメモRS
スカイメモRSの極望パターン。北半球では評価が高いですが、南半球はちょっとクセがあります。まず、どれがヒゲのσ(シグマ)なのかどこにも書いていません。視野が広いので台形は全部見えるはずなんですが、台形の形も書かれておらず、その代わりはちぶんぎ「10G」「7G」という見知らぬ星のパターンが刻まれています(*)。
(*)はちぶんぎ10Gも7Gも、手持ちの星図・星図アプリのどれにも書かれていない上、星並びからも特定することができませんでした。はっきりいってスルーすべきです。
ただし、みなみじゅうじとアケルナル(α Eri)の方向は書かれています。これを頼りに角度を合わせて、σとχをパターンに入れれば十分でしょう。
Polar Scope Align は「Skymemo RS(S)」にしっかり対応しています。この画面の×の位置にσ星を入れればOK。
実践的ノウハウ集
南半球の極軸合わせで注意すべき点をまとめてみました。
極望は倒立像
ふつうの極望は当然ながら倒立像です。星図アプリや双眼鏡で見える台形とは、上下逆であることに注意しましょう。肉眼では「台形のヒゲのあるほうがみなみじゅうじ」ですが、極望を覗いた状態では反対になります。
暗視野照明と明視野照明
明るい北極星なら、特に視野照明装置なしでもヘッドランプで横から照らしてもなんとかパターン上に配置できますが、5等星以下のはちぶんぎの台形ではそれでは困難です。暗視野照明タイプの極軸望遠鏡が理想ですが、少なくとも簡単にON/OFFないしは光量調整ができる明視野照明を準備しておくべきでしょう。
アプリを活用する
極軸合わせにはアプリ最強です。特に歳差対応していないパターンや時角円方式のパターンの場合には必須です。アプリなら基準星である「ヒゲのσ(シグマ)星」が、パターン上のどの位置にあるべきかをビジュアルに表示してくれます。
ただし、本記事でご紹介したPolar Scope Align はiOS版しかないようです。Androidでどんなアプリがあるのかについては現時点で未調査です。よいアプリをご存じの方は是非コメント下さい。情報が入り次第、追記していきます。
また、無料版のPS Alignは「現在の位置」を手動で変えることができないため、日本から南半球仕様の状態を確認することができません。240円のPro版なら設定できるのですが、たぶんですが無料版でも実際に南半球にいけば大丈夫ではないかと思います(不覚にも現地で試すのを忘れました。。こちらも情報をお持ちの方はお知らせいただけると幸いです)。
基準星を全部無理にパターンに合わせる必要はない
北半球でもいえることですが、極軸望遠鏡のパターンに複数の星が描かれている場合に、律儀に全ての星を同じレベルの正確さで追い込む必要はありません。パターンの回転角さえ正しければ、極軸合わせは1星で十分です。一番大事なのは天の南極に一番近い「ヒゲのσ(シグマ)星」です。残りの星は、回転角合わせの目安程度と考えてよいと思います。
南天では赤道儀は逆回転
極軸合わせとは直接関係ないのですが、当たり前のようで気がつきにくいのが逆回転の設定。南半球では星は逆回りです。赤道儀の設定を変更しないと、2倍恒星時で流れます(経験者多数^^;)
南北設定の変更方法はマニュアルで事前に確認しておきましょう。製品によってはGPSと連動して自動で切り替わるものもあるようです。
それと帰国後に北半球仕様に戻すことも忘れずに^^
Polemaster
こちらは使ったことがないのでコメントできないのですが、たとえPolemasterを使う場合でも「はちぶんぎの台形」は認識できる必要があるので、事前の予習は必須だと思われます。
Pole Masterの南半球での運用事例の情報は少ないのですが、少し古いですが以下の記事に画面キャプチャがあります(*)。
K-ASTEC BLOG - デジタル式の極軸望遠鏡 「PoleMaster」 その-7
http://k-astec.cocolog-nifty.com/main/2016/01/polemaster-7-3f.html
(*)今回の遠征では現地にPoleMasterもあったしK-ASTECさんもいらしたのにその情報をちゃんと取材してこなかったのは大失敗。申し訳ありません。
追記:SharpCap
CMOSカメラ用キャプチャソフトSharpCapの「Polar Alignment」機能(*)です。
(*)ツアーに同行したHさんより情報を頂きました。過去の遠征・日本での使用を含め1年間使われているそうですがもうこれだけでOK、との使用感だそうです。SharpCapは無料ですがPolar Alignmentは年間10ユーロのライセンスキーが必要です。
ガイドカメラとしてCMOSカメラを使用している構成の場合、追加ハードなしで極軸合わせが可能になります。大きな流れは以下の通りです。
ガイドカメラを天の極付近に向ける
極軸を回転させながら撮像(この画像から回転の中心をSharpCapが割り出す)
回転の中心がだいたい視野内になるようにカメラの赤緯を調整
画像を撮像。この画像から、ShapCapがPlateSolve(星ならびから赤緯赤経を自動判別)し天の極を割り出してくれる
画面の指示通りに極軸を上下・水平に動かして極軸合わせ
SharpCapのPlateSolve機能を利用し天の極の恒星の配置を自動認識して極軸合わせを行います(*)。
(*)通常はPlateSolveにはネットワーク接続は必要ですが、天の両極はオフラインでも解決可能とのことです(あまり極から外れると解析できないことになります)
ShapCapは英語表示のみであることもあり、使いこなすにはしっかり事前の練習が必要と思われますが、北半球・南半球に関係なくやることは一緒なので、遠征前に日本で操作方法をマスターすることできるでしょう。
ちなみにPoleMasterの場合は焦点距離25mmのレンズを使用しカメラの視野角は11°×8°です。ガイド鏡のカメラを使用する場合はこれよりも長めになり視野が狭くなることが予想されます(筆者が使用しているGT-40+ASI120MMの構成の場合は1.4°)。このような場合の操作感については、情報が得られた時点で追記予定です(*)。
(*)5/3追記:100mmレンズ+QHY5L2の場合「ちょっと視野が狭いがデータマッチングできる領域にさしかかるとキャッチできる」とのこと。
あると便利な双眼鏡
「台形探し」にあると便利な双眼鏡。台形確認用だけなら低倍率で小口径の双眼鏡で十分ですが、海外の暗い空で双眼鏡は非常に素晴らしい観望アイテムなので、小型の42mm か32mmのダハ式を手に入れることをオススメします。天リフ押しのSVBONYなら42mmでも4000円ほどです。
小マゼランが見えないとき
繰り返しになりますが、小マゼランが見えていないと極軸合わせの難易度が上がります。見えないときは仕方ありません。南のさんかく座αで合わせましょう。
極軸微動は必要か
筆者は今回軽量化のため持っていきませんでしたが、もちろん極軸微動はあった方がいいです。今回の極軸合わせの所用時間は20分程でしたが、その大半は台形が見つかった後の調整でした。微動があれば10分は節約できたでしょう。
極軸微動が台形探しのホッピング用として使えるかどうかはよくわかりません。比較的近い小マゼランからでも極軸微動でホッピングするのは移動量が多くてしんどいかもしれません。
三脚ホッピング
筆者は今回の遠征では「極望を覗いた状態で三脚の南側2本を手で軽く持ち上げて台形を探す」という方法が有効でした。でも、小マゼランが天の南極より上だとこの方法は使いにくいし、重い架台では無理っぽいです。状況によっては便利な方法、くらいのノウハウでしょう。
追記:覗き穴方式の極軸合わせ
ビクセンのポラリエやユニテックのSWATなど、ポータブル赤道儀では簡易的な極軸合わせ方式として「覗き穴」があります。北半球の場合「北極星を覗き穴の中心に入れる」だけでも、最大1度程度までの誤差で極軸が合わせられることになります。
あまり焦点距離の長くないレンズで、短時間の露出時間の場合には実はこれでほとんどの場合こと足ります。また、1/2恒星時追尾で30秒〜60秒露出するような場合なら「だいたい北に向ける」だけでも十分実用になります。
しかし、南半球の場合ではかなり不利です。はちぶんぎの台形を覗き穴の真ん中に入れることは普通は無理でしょう。覗き穴と南天の星野のイメージから「だいたいこのへんだろう」という方向に向けるしかありません。
実際に覗き穴合わせでポラリエを使用して撮影してみました。1コマ3分露出ですが、等倍にするとわずかに流れています。これ以上露出時間を伸ばすことは無理でしょう。
比較明合成してみました。15分で25pxくらい流れています。この撮影時の極軸合わせの精度がどのくらいだったのかは定かではありませんし、流れの原因が極軸のズレなのかもわかりません。
ただ、現場では撮影画像を拡大表示すれば、流れているかどうかはある程度判別できます。この撮影の際も、カメラのモニタで10倍拡大表示して「ほんの少し流れてるみたいだけどまあいいか^^;;」と判断して3分露出で撮りました。結果をきちんと確認して、露出時間を適切に設定すれば、荒っぽい極軸合わせでもなんとかなるものですね。
追記:天の南極ダイレクト導入法
K-ASTEC BLOG・南天専用の赤道儀を作る
http://k-astec.cocolog-nifty.com/main/2019/05/post-3e9d33.html
今回の遠征にも同行されたK-ASTEC様のブログから。天の南極に直接極軸望遠鏡の中心を向ける方法の紹介です。
天の南極は6.8等・7.8等の2個の星からなる三角形(天の南極三角形 )の頂点にあり、「σのヒゲ」から比較的わかりやすいホッピングでたどり着けるそうです。この方法は暗い星を使用するため上級者向けですが、極望に十字線があればどんなパターンでも対応できるのがメリット。南天ツアーをガイドする側の立場の人は、覚えておくと役に立ちそうです。
ただし、歳差による極の移動には注意。リンク先の画像には2000年〜2030年までの動きが示されています。2000年には正三角形だった「南極三角形」は、2019年では上の図のようなややひしゃげた二等辺三角形に。2030年頃には、天の南極はこの2つの星とほぼ一直線になります。そのころになればさらに合わせやすくなりそうですね^^
実録・極軸合わせ動画
今回オーストラリアで極軸を初めて合わせた際の記録動画を撮っています。ご笑覧下さい。風きり音がうるさくてすみません・・
今回持っていったSWAT-310赤道儀とビクセン極軸望遠鏡PF-L(左)。暗視野照明には助けられました。軽量化を優先し、極軸微動装置は大胆にも持っていきませんでした。極軸の上下微動は右の自作三脚アジャスタを使用しました。可動域が狭いのが難点。水平方向はK-ASTECのカーボン三脚PTP-C22の「すり割り方式」の固定部を緩め、手動で回転させて合わせます。北半球では筆者は、この方式でこれまで普通に使っていました(*)。
(*)結局、純正の上下水平微動を買い足しています。やっぱりこっちの方が圧倒的に便利です。
まとめ
いかがでしたか?
とにかく、南半球の極軸合わせは「はちぶんぎの台形」が見つけられるかどうかが第一関門。これがクリアできないとまずお話になりません。第二関門は自分の極望パターンをしっかり理解しておくこと。この2つをきちんと予習しておけば、南半球恐るるに足らず、です!
それでは皆様のご武運をお祈りしております。快適な南半球ライフをお過ごしください!編集部山口
千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフOriginal
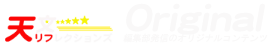






これだけ 詳しく解説しあっても成功するとはかぎりません。
やったことのある人にやってもらうのが確実ですけど1台成功すれば
あとは何台あろうととてもはやくスムーズに導入できますね。
自分はスカイメモRSタイプです。4台。なれれば15分くらいで完了してます。
ただ 何回遠征しても 最初の1台で「はちぶんぎの台形」に自身がもてません。
現に 今回も初日 何回あわせても台形にたどりつけず あきらめて 撮影!しました。
出発点の「みずへび座β」を間違っていたのですから当然です。
「ひげ」なるほど これは重要ポイントですね。倒立像だとなおさらです。
西オーストラリアはやはり暗いです。台形4星がよくみえます。
日本ですと北極星以外の2星はよく見えません。(南紀でも)
いつも天リフを読ませていただいております。
自分もみずがめ座流星群を追って、初めて西オーストラリアのパース方面に、というか皆既日食以外では初めて南半球に観測に行って、帰ってきたところです。
今回の「南半球極軸合わせ」の記事は大変役に立ちました。記事をよく読んでおいて正解でした。
実際には、南十字星やケンタウルスのαの位置から、記事の雰囲気から、南極はこのあたりかと双眼鏡で見たら、いきなり、はちぶんぎ座の台形を見つけてしまいました。改めて、ふうちょう座β、γ、δあたりからたぐり直したりして、再確認という逆の手順でした。双眼鏡が4×18という新しい低倍率のポロプリズム型であったことも大きかったかもしれません。
機材はビクセンのポラリエですが、極望は最新の暗視野タイプのを改めて購入しました。5×20なので従来より低倍率広視界だそうで、ホッピングも容易でした。双眼鏡とほぼ同様の視野で、台形がそのまま見て入れられる仕様ですが、自分は南極に近い方の三つの星で入れてしまいました。
ホッピングは、ポラリエ用の極軸微動の雲台のままでホッピングができました。対象となる星が暗いので、極望から目を離さずに調整できるので助かりました。
おかげさまで、無事に流星をとらえることができました。ついでですが、南十字星付近は7×50の双眼鏡で見る対象としては、最高という感じで、かみさんは双眼鏡でじっくり見ていました。なんか雲が多い空だなぁと思ったら、星雲だったという状況で・・・
今回の記事は、初めて南半球で極軸を合わせる自分には大変参考になり感謝しております。ありがとうございました。