【ほぼ完結!】SVBONY MK105MMレビュー/天リフ読者レビュー企画
8/15追記)
予想を超える悪天候もあり、約2ヶ月延びてしましましたが、全レビューア様のリレーが終了しました!皆様から、各人各様の使い方とレビュー記事をいただき、読者の皆様にとって大いに参考になることかと思います!
レビューアーの皆様、SVBONY様、ありがとうございました!
始まりました!第二回「天リフ読者レビュー企画」。天リフ読者の方々で天文機材を順にレビューしていこうというリレーレビュー企画です。今回はSVBONY社の「SVBONY MK105MMマクストフカセグレン式鏡筒 」と「SVBONY SV135ズームアイピース7-21mm」「SV207スーパープロッスル接眼レンズ15mm」の3点セットです。
本記事では、5月下旬まで計6名の方にリレーされていくプロセスと同時並行で、それぞれのレビューア様が発信された情報を随時更新していきます。ぜひお見守りください!!
2/1追記)
SVBONY&天リフ読者レビュー企画 MK105MM
レビュー期間中購入すれば、3000円クーポンを配布!
*決済時に直接値引き!https://t.co/vbDGQbrf6T#SVBONY #天リフ読者レビュー企画 #MK105MM pic.twitter.com/x6dUKnqUKY— SVBONY Japan (@svbony) January 31, 2023
レビュー期間中に MK105MMを購入すると3000円クーポンがもらえるそうです!
目次
レビューアー様ご紹介
8/15新規レビュー更新!
「yagi」さん(7月上旬〜7月下旬)
SVBONY MK105MMレビュー(その5)〜手持ち撮影やってみた〜
https://note.com/astro3dp/n/n0fd0211df405
#天リフ 企画の #SVBONY MK105MM レビューその5:手持ち撮影やってみた をnoteに書きました。https://t.co/c30DtV2cBk
— yagi (@yagikjp) August 12, 2023
SVBONY MK105MMマクストフカセグレン式鏡筒は
・三脚使わず手持ちで一眼レフ直焦点撮影できます。
・ピントノブが軽くカメラをホールドしたままピント調節できます。
まだまだ続くyagiさんのレビュー。なんとMK105MMにカメラを装着し「手持ち」で撮るというチャレンジ。
鏡筒重量2.2kgはカメラ用の超望遠レンズより少し軽め。ピントノブを軽く回せるので撮影中にピント調節がやりやすかったとのこと。3Dプリンタ出力した対象導入用の照門のSTLファイルもいつものようにダウンロード可能です。
SVBONY MK105MMレビュー(その4)〜暖色系〜
https://note.com/astro3dp/n/nd19dde48acec
#天リフ 企画の #SVBONY MK105MM レビューその4:暖色系 をnoteに書きました。4000文字弱の大スペクタクル超大作です!?https://t.co/CVAB9NN4zf
— yagi (@yagikjp) August 6, 2023
第4弾も濃い^^ MK105で撮影した「高下(たかおり)地区のダイヤモンド富士」の動画、小型マクカセ・シュミカセの実写比較、周辺減光比較、色味比較など充実のレビュー。
「今日の結論:星よりゆるキャン!ん?あれ?」
さらに(こちらが本題?)の「ゆるキャン△」聖地巡りもたっぷり。
SVBONY MK105MMレビュー(その3)〜バッフル長め〜
https://note.com/astro3dp/n/n68f26b9e247f
#天リフ 企画の #SVBONY MK105MM レビューその3:バッフル長め をnoteに書きました。https://t.co/tbo1CUGM8O
— yagi (@yagikjp) August 5, 2023
レビュー記事第3弾です。「バッフル長め」は焦点をボケるまで内側に繰り込んだ際の事象で、合焦時に影響があるかどうかは不明です(*)。「副鏡バッフル」はあるに越したことはありませんが、これもどの程度の悪影響があるのかないのか不明。「3mまでピントが合う」のは野鳥観察などでメリットになりそうですね!
SVBONY MK105MMレビュー(その2)〜実はFL1500〜
https://note.com/astro3dp/n/n24e234f58dff
大きさ比較です。左から
MAKSY60 D60 FL750
NexStar4SE D102 FL1325
MC102 D102 FL1300#SVBONY MK105MM D105 FL1365
MAK127 D127 FL1500今回レビューのMK105MMはFLの割に鏡筒が長めですね。
MC102のみ鏡筒がスチール(薄板?)で、MAKSY60はプラ、ほかはアルミ?っぽいです(磁石つかない)。 pic.twitter.com/J3FUFRg9oO— yagi (@yagikjp) July 7, 2023
yagiさんは小型のマクストフカセグレンやシュミットカセグレンを4本もお持ちです。上のツイートはそれらの大きさ比較。「FLの割に鏡筒が長め」との印象から、なんと焦点距離の実測までやっていただき「実測では焦点距離1500mm」だったとのこと。この件については、SVBONY様に確認中です。
SVBONY MK105MMレビュー(その1)〜レビューまとめ〜
https://note.com/astro3dp/n/na6645829f860
私は天文歴2年半なので、今回のレビューと言うか感想と言うかは話半分でお読みください。さっそく最初に「私なりの結論」書いちゃいます。
「天文歴2年半」と謙遜されていますが、yagiさんの鋭い着眼点と機材の底力に迫る突破力は、上記記事とyagiさんの一連のツイートから伺えます。総じて幾つかの「注意点」はあるものの、105MMは小型でよく見える鏡筒との評価をいただきました。
note yagi
https://note.com/astro3dp
MAK127、MC102、MAKSY60との使い勝手の比較や、ズームアイピースの使い心地を確認したいと思います。
トリを締めるのは、yagiさん。シュミカセ・マクストフを複数お持ちで、それらとの見比べが楽しみ。小型鏡筒ほど、アイピース交換の手間のないズームアイピースのメリットが生きますが、そのあたりの使用感のレポートにも期待です。
「boso-ware」さん(4月中旬〜4月下旬)
SVBONY MK105MMレビュー企画: 撮影してみる。
https://boso-ware.seesaa.net/article/499131875.html
https://boso-ware.seesaa.net/article/499131875.html
boso-wareさんのレビュー記事がアップされています。西豪遠征で更新が遅くなり申し訳ありませんm(_ _)m
眼視・撮影・電視の3方面でご活用いただいたようです。
こちらの画像はライブスタック・10秒約600枚です。F13の鏡筒の10秒露光でも、ライブスタックすればここまで写るのですね!
製品に対する要望も4点ほどいただいています。
一つめはアリガタの位置。上の画像は標準仕様ですが、接眼部にカメラや重いパーツを付けるとリアヘビーになるため、アリガタがもう少し接眼部側にあるとバランスが取りやすくなります。
アリガタは2個の六角ネジで固定されているだけなので、取り外して逆に付けてみました。これで少しですが接眼部側に移動することができました。
他の3つについてもSVBONY様にフィードバックし、検討をお願いする予定です!boso-ware様、ありがとうございました!
SVBONY MK105MMレビュー企画: 超々望遠レンズとして
https://boso-ware.seesaa.net/article/498977935.html
https://boso-ware.seesaa.net/article/498977935.html
こちらのレビューにも注目。補正レンズを使用しない純?マクストフ光学系ですが、接眼部からの光路長を延長筒で調整する自由度があります。それによって周辺減光が改善できるという結果が。「フルサイズ対応の超々望遠レンズとして、実用に値する」とのことです。
SVBONY MK105MM・アイピースレビュー企画: PL15mmとズーム
https://boso-ware.seesaa.net/article/499116329.html
https://boso-ware.seesaa.net/article/499116329.html
2本の接眼レンズについてもレビューいただいています。こちらも高評価です。鏡筒のレビューにも書かれていましたが、ズームアイピースは小型の固定力の弱い架台では「接眼レンズの交換で視野がズレることが少なくなり使いやすい」というのは実用的な視点ですね。
junk box
https://boso-ware.seesaa.net/
超望遠レンズとして地上風景を撮ってみる。春の銀河を眼視・電視くらべ。以前JSO Space10(*)を使ったことがあります。
(*)「JSO Space10」は、日本特殊光機社が販売していた口径100mmのシュミットカセグレン望遠鏡です。
boso-wareさんは以前よりTwitterでフォローさせていただいていて、よくお名前を拝見しています。「超望遠レンズとして地上風景を撮ってみる」のは面白そうですね(*)!
(*)MK105MMの接眼部はT2のカメラマウントを装着できるのですが、回転機構を持たないので、それをどうクリアするのかが気になるところ。1.25インチスリーブ差し込みなら問題ないのですが。
「SuperGlow」さん(3月上旬〜3月中旬)
SV BONY MK105 企画レビュー
https://ameblo.jp/smith-catapy/entry-12794055045.html
当方の更新が遅くなってしまいましたが、レビュー記事がアップされました!光学性能について「5インチのマクカセにも劣らない」「性能は水準以上」との評価をいただいています。ファインダー脚の取付部が2箇所あることについてもご評価いただきました(*)。
(*)経緯台搭載時に縦横いずれにも対応可能になります。
詳細はこちらのレビュー記事をごらんください!
SV BONY MK105 企画レビュー
https://ameblo.jp/smith-catapy/entry-12794055045.html
月や惑星をメインに二重星をAz Gtiで駆動します。高橋FS-102 、Mak127 10インチドブソニアン、セレストロン140ss、 ミード10インチリッチークレチアン所有しています。機動性や光学系のレポートができると思います。
SuperGlowさんは当方は存じ上げなかった方ですが、ご所有の機材から推測するにかなりのご経験をお持ちのガチな方かと推察します。「二重星」のレビューはあまり見かけないので、こちらも楽しみですね!
「ヤマネコ」さん(3月下旬〜4月上旬)

SVBONYさんのマクストフカセグレン『MK105MM』のモニターで10日間ほど、試用させていただきました以下、感想です。
軽量、コンパクト、鏡筒も短いので、小さな架台に搭載できるので、お子さんにも充分使いこなせますね。閉鎖光学系なので、ニュートン反射より温度順応の時間がかかるようです。色がつかないのて、短焦点アクロよりずっとシャープです。長焦点ですが、オリオン星雲などはしっかり見えます。昨夜は、月が大きいので、QBPフィルターをつけましたが、十分な見え味でした。しかし、低倍率が得づらいので、ぜひ接眼部を2インチにしていただきたいと思います。自分の2インチの接眼部で使用しました。月面、惑星はいいですね。とてもシャープです。デジ一でも、CMOSカメラの電視観望、どちらでもいいです。適した架台は、az-gti なんでしょうが、長焦点なので、視野が狭く、対象が逃げてしまうとなかなか厳しいと思います。自分はGP赤道儀を改造して片持ちフォーク赤道儀を使いましたが、それ以上の大きい赤道儀の方がイイかもしれません。最も適していると感じたのは、双眼装置で見る月面です。片目だと長時間見ていると疲れますが、双眼装置で見ると、まったく疲れません。バーダーの傾斜型双眼装置を使いましたが、色収差も感じず、素晴らしい見え味でした。付属していただいまズームアイピースも長焦点側はまずまず、ハッキリ見えます。それ以上に15mmのアイピースはかなりのものと感じました。このシリーズのアイピースはお値段以上なので、いくつか欲しいと思いました。いずれにしても、この大きさで、この価格、おそるべしです。特に、入門用としてはこれ以上の鏡筒はないかもしれません。今回はモニター試用させていただき、本当にありがとうございました。
昨夜も北海道の夜は氷点下になりました。今度はもう少し暖かいシーズンにまたモニターをさせていただきたいと思います。この度はどうもありがとうございました
Facebook 山中高弘
https://www.facebook.com/takahiro.yamanaka.104
市民観望会でスマホ月面撮影をレクチャーする予定です。今は重たい鏡筒しかないので、軽い鏡筒を探していました。
ヤマネコさんはFaceBookではお名前をちょくちょく拝見しておりました。北海道にお住まいとのことで、3月下旬なら市民観望会も雪融けの状態でしょうか?多くの方に「スマホ月面撮影」を楽しんでもらえるといいですね!
番外・天リフ編集長
不肖・天リフ編集長も、少しですが撮影に使用してみました!
2月16日のリザルト。M42を拡大撮影。BlurXterminatorで仕上げると別物になってびびっています^^
SVBONY MK105MM(焦点距離1365mmF13) ASI294MC非冷却 10秒200枚 AP赤道儀CoolStep改造 熊本県産山村 pic.twitter.com/0Wia8tmolq— 天リフ編集部 (@tenmonReflexion) February 19, 2023
MK105MMをビクセンのAP赤道儀に搭載してオリオン大星雲を撮影。焦点距離1365mm、4/3センサーのASI294MCです。
F値の大きな光学系なので、補正レンズを使用しなくてもそこそこ普通に使えます。オートガイドをしているとはいえ小型赤道儀なので露光時間も10秒程度に抑えました。最周辺を等倍拡大すると明らかに点像ではなくなっていますし、パーフェクトな光学系ではもちろんありません。

しかし、BXTをかけてみると、なかなかのディテール描写。F13の鏡筒の10秒100枚でもここまで撮れます!

こちらは同じ日のZTP彗星。彗星のイオンテールはとても淡いので暗い光学系では難しい対象になりますが、核やコマはじゅうぶんな輝度があり、長焦点でもなかなか迫力ある画像になりました。
セットアップ画像を撮りもらしたのは大失敗ですが、MK105MMはとてもコンパクトなので小型の赤道儀でもあまり無理なく搭載することができます。ガチガチの写真用途に「最適」であるとは言いませんが「眼視もやるけど写真も楽しみたい!」というニーズには、対象と撮り方を間違えなければいい感じで遊べる鏡筒だと感じました!
「雑兵A(天)」さん(2月上旬〜2月下旬)
レビュー第一弾「序章」更新!
へぼてんブログ
https://heboten.hatenablog.com
前回に続き、今回もご参戦いただいた「雑兵A(天)」さん。初めての方が望遠鏡を手にしたときの目線で、ご自身の経験をブログで公開されています。
『天体望遠鏡徹底ガイドブック』を真似たレビュー記事を書いてみたいです。
他の方のような経験や知識がない分、読んで下さった方が楽しめるレビューを目指したいです。
本来は前回のSV550でも途中まで書いていたのですが、今回はきちんと公開できましたら!
今回のレビューも期待ですね!
「山下芳晴」さん(1月中旬〜2月上旬)
Facebook 山下芳晴
https://www.facebook.com/yoshiharu.yamashita
早速レビューいただいています!
その3.(1/30更新) New!
Tマウント経由で天体改造デジカメD600を装着しM42オリオン大星雲を撮影されました!F13という「暗い」F値が功を奏しているのか、コマコレクタのような補正レンズ使用しなくても周辺の星像の歪みが少なかったとのこと。
ただし、接眼部が1.25インチ仕様のため、APS-Cセンサーの場合 フルサイズセンサーの場合(*)周辺がケラれるようです。これは仕方ありませんね。フォーサーズAPS-Cやそれより小さなセンサーで使うのが良いのかもしれません。
(*)2/1訂正)初出時にD600のセンサーサイズを勘違いしていました。お詫びし訂正させていただきます。
山下さん、レビューありがとうございました!!
その2.
惑星カメラQHY5Ⅲ462cで撮影。MK105の接眼部は先端がT2ネジになっていて、FマウントTリングを介して画像のような構成に。気流が安定していなかったものの、木星・火星の作例をアップいただきました!「(赤道儀は別として)トータル数万の構成でここまで観察出来ればコストパフォーマンスは高いと思いました。」とのことです!
その1.
眼視観望でオリオン大星雲M42を観察されたとのこと。斜鏡スパイダーのあるニュートン反射と比較して星の光芒が少ないこと、SV135ズームアイピースのズームリングが非常になめらかに回る、スーパースロッセルSV207の「ヌケ」が良いことなどがプラスポイント!
イントロ
開封と製品構成のご紹介。マクストフカセグレンをご使用になるのは初めてとのこと。「ワクワクが止まりません![]() 」とのことで、この後のインプレッションが楽しみですね!
」とのことで、この後のインプレッションが楽しみですね!
山下さんはディープスカイから月惑星まで、オールラウンドに天文を楽しまれている方。どちらかというと?ガチな方ですが、幅広いご経験からMK105MMをレビューいただけるものと期待!
火星など惑星の観察とアイピース型のCCDカメラを使って本格的なDSO撮影にもチャレンジしてみたいです。
「LensLingTV」の「ぼすけ」さん(5月上旬〜中旬)
LensKing’s TV / Bosque Rico
https://www.youtube.com/@BosqueRico
残念ながらぼすけさんに実機を貸出させていただいた期間は、悪天続きでまったく実戦投入できない状態で終わってしまいました。ぼすけさんのレビューを楽しみにされていた方々、ごめんなさい!またの機会をお楽しみに・・・!
天文界有数のYouTuberぼすけさん。前回に続き、今回もご参戦いただきました!数々の機材を実際に使用しレビュー動画をアップされているご経験から、MK105MMに対しても的確なレビューをいただけるに違いありません。
MK105MMとは?
SVBONY MK105MMマクストフカセグレン式鏡筒
https://www.svbony.jp/mk105-maksutov-cassegrain-ota
これまで様々な低価格帯の天体望遠鏡や天体用CMOSカメラSV305などを、業界随一ともいえる低価格で販売してきたSVBONY社ですが、このMK105MM鏡筒は同社初の「マクストフカセグレン式」になります。
マクストフカセグレン式望遠鏡は、最前群のメニスカスレンズが特長。曲率は深いものの主鏡も含め球面のみで構成されるため大量生産に向きます。鏡筒が閉鎖されているため筒内気流の影響がより少ない、副鏡を支持するスパイダーが存在しないため回折による像の悪化が少ないなどの特徴があります。
本製品はメニスカスレンズにメッキによって副鏡を形成するタイプ(*)で径は目測で30mm(主鏡径の28.6%)。一般に副鏡径が小さいことは、特に眼視性能において効果があると考えられています。
(*)一般的には、別に製作された副鏡を使用する「ルマック式」という製品も存在します。
今回のレビュー企画の概要
【大募集】天リフ読者レビュー企画・SVBONY「MK105MM」天体望遠鏡、SV135ズームアイピース、SV207スーパープロッスル接眼レンズ
ざっくり今回のレビュー企画の流れは以下のようなものです。
- メーカー様は、レビュー対象製品を一定期間天リフに貸与する
- 天リフが対象製品に対するレビューアーを募る
- 天リフからレビューアーに一定期間製品を貸与
- レビューアーはレビュー結果を自分のブログ・SNS等にアップ、ないしはレビュー結果を天リフにレポート
- 天リフはレビューアーのリザルトを適宜記事化する
メーカー様のメリットは「評価してほしい製品を貸し出す」だけで、様々な視点のレビュー記事がネットに放流されること。レビューアー様のメリットは、興味のある製品を実際に試すことができること。天リフのメリットは、読者に広く製品紹介を発信できることです。まさに「win-win-win」のスキーム!
まとめ
いかがでしたか?
低価格・小口径のマクストフカセグレンの評価やいかに?さまざまな天文ファンの方々のレポートをぜひ参考に、貴方の機材選びと使いこなしにお役立てください!前回好評を博したリレーレビューですが、今回も楽しみですね!絶対に見逃さないよ!
- 本記事はSVBONY社より機材貸与と協賛を受け、天文リフレクションズ編集部が独自の判断で作成したものです。文責は全て天文リフレクションズ編集部にあります。
- 記事に関するご質問・お問い合わせなどは天文リフレクションズ編集部宛にお願いいたします。
- 製品の購入およびお問い合わせはメーカー様・販売店様にお願いいたします。
- 本記事によって読者様に発生した事象については、その一切について編集部では責任を取りかねますことをご了承下さい。
- 記事中の製品仕様および価格は執筆時(2022年1月)のものです。
- 記事中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

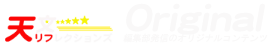
コメントを残す