
みなさんこんにちは!
フィルターワークの徹底解説連載。第一回では、「何のためにフィルターを使うのか」というフィルターワークの基本戦略を、第二回のセンサーとカメラの感度特性では、フィルターとペアになるカメラのセンサーと、カメラに組み込まれたフィルターの波長特性を解説してきました。
「よりよい像を結ぶ」という光学的な目的に照らすと、フィルターはある意味「邪魔者」です。大なり小なり「結像性能を悪化させる」要素を持つことを理解し、その副作用を減らすように使うのが肝要です。さらに、既存の光学系のどの位置にフィルターを置く(装着する)のかは、現実的な運用の問題であると同時に、結像性能をできるだけ悪化させないように配慮しなければなりません。
第三回の今回では、そんなフィルターの副作用と置き場所について解説します!
5つの大きなフィルターの副作用
フィルターがはっきりと「悪さをする」ケースは、大きく5つあります。特に、最近の天体写真の主流である干渉フィルター(*)では、色ガラスフィルターでは起きなかった問題が存在します。天体写真のフィルターワークでは、そんな干渉フィルターの特性をよく理解しておくことが必要です。
(*)光の「干渉」の性質を利用したフィルターで、ガラスの表面にごく薄い(光の波長のオーダー)誘電体の膜を、何層(多いものでは100層以上)にも蒸着したもの。色素による吸収によって透過波長を制御する「色ガラスフィルター」とは原理が異なり、原理的には自在な透過波長のコントロールが可能です。一方で製造コストははるかに高価になります。
焦点位置の移動とそれに伴う収差の増大
 平行平面ガラスによる焦点移動の模式図。点線はフィルターがない場合の焦点位置。
平行平面ガラスによる焦点移動の模式図。点線はフィルターがない場合の焦点位置。
詳しい理屈は省略しますが、フィルターを光学系の中に入れると、光路長がより長くなり、ピント位置が近距離側に移動します。概算的には(*)、フィルターの厚みの1/3分だけずれると覚えておけばよいでしょう。
(*) 正確には、屈折率をn、厚みをdとしたとき、d×(n-1)/n。厚み2mm、屈折率1.5の場合0.67mm。
ピントがずれることによる問題は2つあります。一つはフィルターの厚みが異なる場合はフィルター交換によってピント合わせをやり直す必要があることです。しかしこれは、まあ合わせ直せば済むことではあります。
 フィルターによるピント位置のずれ。いずれも無限遠に合焦している状態です。広角レンズの場合、わずか0.68mmのピント位置の移動であっても、数メートルの近距離を撮影するのと同じ状態になります。
フィルターによるピント位置のずれ。いずれも無限遠に合焦している状態です。広角レンズの場合、わずか0.68mmのピント位置の移動であっても、数メートルの近距離を撮影するのと同じ状態になります。
もう一つの問題は、光学系によっては焦点位置がずれることで、設計時に想定された光学性能が出なくなる場合があることです。屈折パワーのない(凸でも凹でもない)平面の薄いフィルターによる収差は本来は微々たるもの(*)なのですが、特定の条件下では悪影響が顕在化することがあります。
(*)対物レンズの前面に置く場合、フィルターの面精度や脈理などの影響を受けることはあります。
 フィルターの有無による星像の変化。フィルター厚約1.2mmのボディ内装着型です。左の35mmレンズでは像の悪化はほとんどありませんが、右の30mmレンズでは像が若干肥大しています。
フィルターの有無による星像の変化。フィルター厚約1.2mmのボディ内装着型です。左の35mmレンズでは像の悪化はほとんどありませんが、右の30mmレンズでは像が若干肥大しています。
具体的に一番問題になるのは、近距離補正機能を持つ(超)広角レンズで、リア側(レンズ後端とセンサーの間)にフィルターを挿入した場合です。上の画像はその例ですが、レンズによっては周辺像が悪化することがわかります(*)。
(*)一般に広角レンズでは、近接撮影時に像面湾曲が発生し周辺像が悪化するのを抑制するため、レンズの繰り出し量に応じて像面湾曲を補正する(逆に発生させる)「近距離補正」機能を持たせることが多いのですが、フィルターによってピント位置がずれると無限遠であるはずの被写体でも近距離補正が効いてしまうことになり、像を悪化させてしまいます。筆者の経験では、超広角レンズほど影響が顕著なようです。
この問題を解決するにはスペーサ(シムリング)をかませるなどしてレンズとマウントの間の距離を調整し(*)、対象となる天体が本来の無限遠の位置で合焦するようにすればよいのですが、物理的になかなか難しい対応です。現実的には、フィルターを薄くすることで極力影響を少なくするしかないでしょう。最近のボディ内装着フィルターは薄いものでは0.5mm程度にまで薄型化された製品も存在するようです。
(*)社外品のマウントアダプタを使用する際にも同じような問題が存在するようです。最近の超広角レンズの性能向上はめざましいものですが、その分公差にも非常に敏感です。広角レンズの個体差の問題はそのへんにも原因があるのではないかと筆者は推測しています。
 IDASのEOS R用のドロップインフィルターマウントアダプタ。専用の厚み2mm(光路長0.68mm)のフィルターに最適化されています。出典:http://icas.to/space/Digital-camera/DRS-SP-a.htm
IDASのEOS R用のドロップインフィルターマウントアダプタ。専用の厚み2mm(光路長0.68mm)のフィルターに最適化されています。出典:http://icas.to/space/Digital-camera/DRS-SP-a.htm
一方で、最近はミラーレス一眼用にフィルターボックスを持つマウントアダプタが登場しています。フィルター厚とそれによる焦点移動がきちんと考慮されているのであれば、根本的な解決となるはずです。
広角レンズ以外でも、レデューサ・フラットナーなどの補正レンズとセンサーの間にフィルターを置くと、バックフォーカスが設計値とずれることになります。2mm厚フィルターの場合の「約0.68mm」のずれがどの程度影響するかですが、光学系によっては(*)結像性能に差が出てしまうかもしれません。
(*)筆者の経験ではF7の屈折鏡筒に可変フラットナーを使用した場合、バックフォーカスが1mm違うと、等倍画像では四隅の像に悪化とはいかないまでも「変化」がありました。広角レンズほどではないものの、一定の影響があるようです。F値の明るい鏡筒ではさらに顕著になるかもしれません。
フィルターによる反射とゴースト・迷光
 狭帯域の干渉フィルター(左:Baader OIII 8.5nm)の表面はまるで鏡のようです。ほとんどの可視光を透過する広帯域のUV-IRカットフィルター(右:Baader製 )も、斜めから見ると赤色を反射しています。中は色ガラスフィルター(中:ケンコーStarryNight)。
狭帯域の干渉フィルター(左:Baader OIII 8.5nm)の表面はまるで鏡のようです。ほとんどの可視光を透過する広帯域のUV-IRカットフィルター(右:Baader製 )も、斜めから見ると赤色を反射しています。中は色ガラスフィルター(中:ケンコーStarryNight)。
ガラスに色素を混ぜ込んだ色ガラスフィルターの場合、透過しない光はフィルター材が吸収します。吸収された光はそれ以上「悪さ」をすることはありません(*)。これは実は光学系としては非常にハッピーなことです。
(*)厳密には吸収された光はエネルギーとなって温度が上昇します。太陽観察ではフィルターが加熱され割れたり燃えたりする問題があります。
一方で、最近の天体撮影での主流である「干渉フィルター」の場合、カットされた光は基本的に全て反射されます。上の画像はいろいろな天体用フィルターですが、カットする光が多いほど、鏡のように輝いて見えることがわかるでしょう。

では、それの何が問題なのでしょうか?上図左は仮想的なフィルターの波長特性図です。このフィルターを光学系とセンサーの間に入れたと考えてみましょう。
①の波長656nmの光は、フィルターを透過して全てセンサーに到達します。②の波長680nmの光は、フィルターで全反射されて光学系に入射し、レンズの表面などで反射して一部の光が再び光学系に戻ってきますが、その光はフィルターで再び全反射され、センサーには到達しません。
問題は③の波長650nmの光です。この波長では50%の光が透過し、残り50%の光が反射されます。この反射光が再び光学系で反射されて戻ってきた際には、その光のうちの50%は透過されてセンサーに届いてしまうことになります。
 輝星によるゴーストの例。左:アンタレス。カメラマウント前に弱い星雲強調フィルターを使用。中:くらげ星雲右。Hαナローバンドフィルターをマウントアダプタ内に。右)デネブ。三重のゴースト円が出ています。クリップタイプのワンショットナローバンドフィルターを使用。
輝星によるゴーストの例。左:アンタレス。カメラマウント前に弱い星雲強調フィルターを使用。中:くらげ星雲右。Hαナローバンドフィルターをマウントアダプタ内に。右)デネブ。三重のゴースト円が出ています。クリップタイプのワンショットナローバンドフィルターを使用。
その結果、多くの方がすでに経験されていることとは思いますが、上の例のように輝星のまわりに円形のゴーストが出ることがあります。これは2面あるフィルターの反射面で光が反射し、センサーに戻ってきてしまうために起こります。フィルターによってはどちらの面を対物側に向けるかによって出方が変わる(*)こともあるようです。
(*)ゴーストが最小になる前後の向きを示すマークがガラスに描かれている製品もあります。一方で2面とも特性が同じで前後の区別がないフィルターもあります。
ゴースト円の大きさは、センサーとフィルターの距離が離れるほど大きくなります。ゴースト円を大きくする(センサーから遠ざける)ことで単位面積当たりの光は弱くし、ゴーストを薄くするという戦略と、ゴースト円を小さくして輝星の滲みより小さくすることで目立たなくする戦略の2つが考えられますが、どちらがいいのかはケースバイケースになると思います(*)。
(*)中途半端がいちばんイケナイ気がします。
この手のゴーストは円形のマスクで比較的簡単に画像処理で軽減できるのですが、数が多くなるとあまりやりたくない処理ではあります^^;;

星景写真で干渉フィルターを使用する場合、ゴーストはもう少しややこしい症状として表れます。写野内に極端に明るい光源がある場合、上の画像の中の例のように、大小様々なゴーストが現れてしまうことがあります(*)。
(*)その点、色ガラス系のフィルターはカットする光を吸収してくれるので、ゴーストの点では有利です。しかし色ガラス系で天体写真に有効なフィルターは、選択肢がきわめて限られるのが現状です。
レンズの前面にフィルターを装着すれば、干渉フィルターのゴースト問題は回避できますが、逆に次項の斜入射光による特性変化の問題が起きてしまいます。
ゴースト問題は単純ではなく、決定版といえる対策も少ないのですが、まずは入射光がフィルターで一部反射・一部透過されることで問題が起きうる、ということを押さえておきたいと思います。
斜入射光による特性変化
 IDAS LPS-D1フィルターの斜入射角度別の波長特性。「光線入射角17゜(画角34゜)以内のレンズでご利用ください」との注記があります。出典:光映舎 LPS-D1 http://www.koheisha.jp/idas/IDAS%20LPS-D1.html
IDAS LPS-D1フィルターの斜入射角度別の波長特性。「光線入射角17゜(画角34゜)以内のレンズでご利用ください」との注記があります。出典:光映舎 LPS-D1 http://www.koheisha.jp/idas/IDAS%20LPS-D1.html
干渉フィルターでは、斜めに入射した光に対しては特性が変化してしまいます。上のグラフはIDAS社の「LPS-D1」の波長特性ですが、入射角が10°傾いただけでも波長特性は7nmほどずれてしまいます。帯域の広い光害カットフィルターなら許容範囲はまだ広いのですが、狭帯域のナローバンドフィルターではこの問題が顕著になってきます。
この問題を回避するには、フィルターに対する入射角ができるだけ垂直になるようにすることです。具体的には、レンズ前面に装着する場合は焦点距離を長くすること。この場合、上記のLPS-D1フィルターでは「画角34°」の目安に従うと焦点距離約70mm以上でなければならないことになります(*)。
(*)この制限により、星景写真や広角の星野写真では、干渉フィルターのレンズ前面装着は不適だと考えるべきでしょう。
ボディ側に装着するときはF値を明るくしすぎないことです。デジタルカメラ用のレンズは一般に光がセンサー面にできるだけ垂直に入射するように設計されていますが、F値が明るくなると斜めに入射する光の成分が多くなり、影響がより大きくなります。特に半値幅3nmといった超狭帯域のフィルターでは、F5が限界であるという情報(*)も耳にします。RASAやεなどの明るい光学系を使用する場合、極端な狭帯域フィルターは避けた方が良いかもしれません(*2)。
(*)F5の光学系の場合、写野中心の対象からの最大入射角はtan-1(1/10)=約6度。斜め6度に入射した光は0度に入射した光と比較して1-cos(6°)=0.5(%)膜厚が厚くなるのと同等。656nmの0.5%は約3.2nm。
(*2)筆者は105mmF2.0や300mmF2.8のようなレンズで半値幅7nmのHα撮影をしていますが、これまで特に困ったことは感じていませんでした。厳密に比較すると実は光量を損しているのかもしれません。
 出典;http://icas.to/space/optical-filter/NBxPM.htm
出典;http://icas.to/space/optical-filter/NBxPM.htm
この問題を波長特性の工夫で低減しようという製品を紹介しておきましょう。上のグラフはIDASのNB(ネビュラ・ブースター)シリーズの波長特性ですが、透過すべき輝線の波長に対して、フィルターの波長特性が長波長側に振られています。これにより、より斜めに入射した光でも、透過率の高い範囲に収めようというものです(*)。
(*)Baader社のF2対応を謳うナローバンドフィルターも同じ考え方で、透過率が最高になる中心波長をずらした製品です。Fの暗い光学系では逆に不利になることに注意が必要です、
フィルターによるケラレ
フィルターのサイズ・形状・置き場所によっては、光束が遮られケラレが発生することがあります。
 クレセント星雲。フルサイズのデジタルカメラに36mm径のフィルターを使用。小サイズのセンサーやトリミングを前提にするなら、より安価な小径フィルターを使用するのも大アリでしょう。
クレセント星雲。フルサイズのデジタルカメラに36mm径のフィルターを使用。小サイズのセンサーやトリミングを前提にするなら、より安価な小径フィルターを使用するのも大アリでしょう。
まずはわかりやすい例。フィルターが小さすぎる場合です。上の画像はフルサイズのデジタルカメラですが、イメージサークル(44mm径)より小さい36mm径のフィルターを使用しました。ごらんの通り、周辺が完全にケラレています。センサーの近くにフィルターを置く場合、ケラレなく使用するためにはイメージサークルよりも大きなフィルター径が必要です。
 クリップ型フィルターによるケラレの例。長焦点の対物光学系で顕著に現れます。下辺のミラーボックスケラレと同程度の減光が出ています。一方で、広角系のカメラレンズではほとんど目立たなくなります。
クリップ型フィルターによるケラレの例。長焦点の対物光学系で顕著に現れます。下辺のミラーボックスケラレと同程度の減光が出ています。一方で、広角系のカメラレンズではほとんど目立たなくなります。
次の例。上左の画像は、カメラボディに装着するクリップ型のフィルター(上画像右)によるフラット画像。フィルター枠によるケラレが出ています。
クリップタイプのフィルターは、干渉フィルターをカメラレンズで使用する数少ない選択肢なのですが、天体望遠鏡など長焦点の対物光学系で使用すると、ケラレがそれなりに出てしまいます。焦点距離のあまり長くない(*)カメラレンズ向けと考えるべきでしょう。
(*)入射瞳径が小さい光学系ほど、影響が小さくなるようです。

レンズ前面に装着するフィルターでは、広角レンズの場合フィルター枠でケラレることもあります。上の例は24mmの広角レンズにフィルターを2枚重ねして装着したものですが、最周辺がわずかにケラレていることがわかります。
ケラレの発生の原因と影響は、比較的シンプルに予想と対策が可能です。トレードオフの部分もありますし、機材を有効活用する意味では、時にはケラレ上等で撮ることもあるでしょう。
蒸着膜のムラと個体差
 干渉フィルターの特性ムラの例(左)。中心部は均一ですが、周辺部では若干色が違っています。イメージサークルによっては影響があるかもしれません。
干渉フィルターの特性ムラの例(左)。中心部は均一ですが、周辺部では若干色が違っています。イメージサークルによっては影響があるかもしれません。
干渉フィルターの蒸着膜は、光の波長のオーダーの薄さで数十、多いものでは100層以上にも重ねられています。製造する際にその厚さに誤差やムラが発生すると波長特性が設計値からずれてしまい、部分的な「色むら」となって現れたり、本来透過させるべき輝線の透過率が低下してしまうことがあります。
 製品によっては個体毎の実測特性グラフが添付されているものもあります。
製品によっては個体毎の実測特性グラフが添付されているものもあります。
蒸着技術は近年めざましく進歩していますが、逆にいえばビジネス的には過渡期でもあり、品質の低いフィルターが市場に混入している可能性はないとはいえない状況かもしれません。じゅうぶんな製造技術を持っている場合でも、透過帯域の狭い「攻めた特性」の製品ほど品質の歩留まりが悪化することになり、それは販売コストに跳ね返ってきます。場合によっては「当たり外れ」の差が大きくなるとも限りません。
とはいえ、今も世界各国で多くの企業が、よりよい製品を目指して努力しています。フィルターの性能と品質は今後ますます上がっていくことでしょう。
フィルターをどこに置くか

フィルターを使うためには、光学系の中のどこかの場所に、安定して装着しなければなりません。しかし、意外と制約条件が多く、悩みの種でもあります。本項では、さまざまなフィルターの装着方法について概説します。
レンズ前面
 みんな大好き「RedCat51」。活用している人はあまり見かけないのですが、レンズ前面には55mmのフィルターネジが切られています。ステップダウンリングを使用すれば若干光量損失はあるものの52mm径の天体用フィルターが使用できるはず。
みんな大好き「RedCat51」。活用している人はあまり見かけないのですが、レンズ前面には55mmのフィルターネジが切られています。ステップダウンリングを使用すれば若干光量損失はあるものの52mm径の天体用フィルターが使用できるはず。
最も自然な装着場所がレンズ前面。写真レンズ用のフィルターの装着場所として古くから使用されてきました。カメラレンズを使用する場合はノーマルな手段ではほぼ唯一の方法でもあります。しかし、前述の入射角の制限や、大径の干渉フィルターは高価で製品バリエーションが少ないこともあり、あまりガチ撮影では利用されていないようです。
しかし、前面装着はゴーストや焦点移動の問題が最も少なくなります。最近増えてきた小口径のアストログラフでは、活用の余地があるかもしれません。人と違ったことをやってみたい人にはチャンスかも?
2022/3/10追記)
対物前面装着の場合、かなりまずいゴーストが発生する事例を確認しました。イメージセンサーで反射さらた光がフィルター面で反射し再度センサー側に入射し、再結像するものと考えられます。
 焦点距離180mm 48mm径のデュアルナローバンドフィルターを対物前面に装着。3つ星・M42などのゴーストが倒立像で映り込んでいます。
焦点距離180mm 48mm径のデュアルナローバンドフィルターを対物前面に装着。3つ星・M42などのゴーストが倒立像で映り込んでいます。
光学系内部
 キヤノンのEF300mmF2.8のドロップインスクリューフィルターホルダー。52mm径のフィルターが装着できます。フィルターの枠の厚みの制限に注意。
キヤノンのEF300mmF2.8のドロップインスクリューフィルターホルダー。52mm径のフィルターが装着できます。フィルターの枠の厚みの制限に注意。
一部の大口径カメラレンズでは、レンズ前面にフィルターを置くと巨大なフィルターが必要になるため、レンズの内部にフィルターを挿入(ドロップイン)できる仕組みになっています。
例えばキヤノンの「白レンズ」と呼ばれる300mmF2.8などのモデルでは、上の画像のように52mm径のフィルターを装着して入れ込めるようになっています。一部のレンズ限定になりますが、この機構があればかなり自由な(*)フィルターワークが可能になります。
(*)とはいえ、天体用フィルターは48mm径しか存在しない製品も多く、その対策は悩ましいところです。筆者は若干無理目の工作をして回避しています。
 レデューサ【7872】を装着したフィルターボックス。出典:https://www.tomytec.co.jp/borg/products/partsDetail/summary/239
レデューサ【7872】を装着したフィルターボックス。出典:https://www.tomytec.co.jp/borg/products/partsDetail/summary/239
同じような機構をより汎用的に実現したのが、BORGの「フィルターBOXn【7519】」です。M57のオス・メスの延長チューブがフィルターボックスになった形で、径48mm/52mmの双方に対応しているので数多くのフィルターが使用可能。フィルターワークという観点でも、BORGは柔軟なシステムが組める製品だといえるでしょう。
 タカハシの「ワイドマウント(左)」とカメラアダプターCA35(右)に48mmフィルターをねじ込んだところ。
タカハシの「ワイドマウント(左)」とカメラアダプターCA35(右)に48mmフィルターをねじ込んだところ。
カメラアダプタや接続スリーブ、フラットナー・レデューサなどの補正レンズには、フィルター装着用のネジが切ってあるものがあります。特に2インチスリーブにはほとんど全ての製品に48mmネジ(*)が、1.25インチスリーブには31.7mmネジが切られているので、大いに利用価値があります。
(*)48mmネジ≒2インチなのですが、微妙にネジピッチの異なるのか完全にねじ込めない組み合わせがあるようです。合わなくても1回転くらいで固定することができますが、無理にねじ込まないよう要注意です。
このタイプの装着方法の欠点は専用のフィルターボックスよりも交換が面倒なこと。組み付けをばらさないと交換ができない(*)ので、SAO合成のような用途では面倒な上に構図もずれやすいのが悩みの種。
(*)現場で交換するのもかなり気を遣います。筆者は過去2回脱着時に落としました^^;;;冬場は息や指の湿気で曇ってしまうのも悲しいところ。
カメラレンズ後面
 キヤノンの魚眼ズームEF8-15mmF4Lのレンズ後部に設けられたフィルターホルダー。薄いシート上のフィルターを切り取って差し込むようになっています。
キヤノンの魚眼ズームEF8-15mmF4Lのレンズ後部に設けられたフィルターホルダー。薄いシート上のフィルターを切り取って差し込むようになっています。
いわゆる「出目金レンズ」と呼ばれるような前玉が大きく飛び出したレンズや、魚眼レンズのような画角の広いレンズの場合、レンズ全面にフィルターを装着するにはレンズよりも大きなフィルターが必要になり現実的ではありません。このため上の画像のように、レンズの後面にシート型の薄いフィルターを差し込めるようになっている製品があります。
しかし、ディープスカイ撮影では今のところあまり有効な使い道がありません。厚いガラスフィルターは差し込めない上に、前述の光路長変化による星像悪化のリスクがあります。極薄のフィルターは仮に入手できたとしても挿入時に割れてしまうかもしれません。
一方で、リア装着は星景写真でソフトフィルターを使用する良い方法です。前面装着で起きる、周辺の輝星が楕円になる現象を回避できるからです。
カメラボディ内
 左:APS-CフォーマットのEOSシリーズに装着するフィルター。センサー径の小さいAPS-Cでは、ケラレの問題も少なく、製品によってはミラーアップも不要。右:フルサイズのEOSシリーズに装着するフィルター。ミラーアップした状態で装着し、ライブビューで使用する前提ですが、6DMarkIIなど一部の機種ではこの状態ではカメラが異常と検知しシャッターが切れないなど、適合機種に要注意。
左:APS-CフォーマットのEOSシリーズに装着するフィルター。センサー径の小さいAPS-Cでは、ケラレの問題も少なく、製品によってはミラーアップも不要。右:フルサイズのEOSシリーズに装着するフィルター。ミラーアップした状態で装着し、ライブビューで使用する前提ですが、6DMarkIIなど一部の機種ではこの状態ではカメラが異常と検知しシャッターが切れないなど、適合機種に要注意。
一般に「クリップタイプ」と呼ばれる、カメラボディ内に装着する特殊な枠を持ったフィルターが販売されています。レンズを選ばないメリットがある反面、脱着に神経を使うこと、前述のフィルター枠によるケラレや光路長変化による星像悪化の可能性などの欠点があります。
とはいえ一眼レフ機では、広角を含むカメラレンズで干渉フィルターを使うには、事実上この方法しかありません(*)。欠点をうまくカバー、ないしは受け入れて使うのが肝要です。
(*)ミラーレスカメラの場合は、前述のマウントアダプタに装着する方法があります。
センサー直前
センサーの直前は、実はフィルターにとっては特等席です。この場所がゴーストや収差などの光学的な副作用が一番少ない場所だからです。ゆえに、この場所にはすでにデジタルカメラが必要とする「UV-IRカットフィルター」などが鎮座していて、ユーザーの手で簡単に付け外しできる場所ではありません。現実的には利用できない(*)装着場所といえます。
(*)この場所に踏み込んでフィルターを交換するのが「天体改造」です。
そのほかの副作用
最後に、そのほかのフィルターによる副作用をまとめておきます。これらはいずれも特殊なケース・極端な使用方法でしか問題にならないレベルのものです。
光量の損失
フィルターの硝材が一定量光を吸収します。しかし、硝材の吸収による光量損失はほんのわずか(*)で、薄いフィルターにおいては誤差の範囲にもならないレベルです。
(*)最も広く使われている光学硝子材「BK7」の場合、可視光域では厚さ100mmでもわずか約1.6%です。一方で380nmよりも短波長では硝子材による吸収が顕著になってきます。
むしろ問題になるのは表面反射による損失ですが、これは昨今の高性能なマルチコートであれば2面で0.4〜1.0%程度です。これもほとんど気にしなくていいレベルです。
光学系の想定波長域からの逸脱
デジタルカメラは基本的に可視光線(400nm〜650nm)を想定して設計されているため、改造やフィルターを使用することでこれを大きく逸脱する場合は、問題が出てくることもあります。
 左は最近の高性能で定評のある広角レンズですが、赤外域ではゴーストが強く出ます。右のカメラレンズは某社のオールドレンズ。肉眼では黒塗装に見えますが赤外では明るい灰色。最近のレンズではこのような問題はないようで、筆者の手持ちの製品では問題があったのはこれだけでした。
左は最近の高性能で定評のある広角レンズですが、赤外域ではゴーストが強く出ます。右のカメラレンズは某社のオールドレンズ。肉眼では黒塗装に見えますが赤外では明るい灰色。最近のレンズではこのような問題はないようで、筆者の手持ちの製品では問題があったのはこれだけでした。
上左の画像は近赤外による撮影ですが、ひどいゴーストが出ています。レンズのコーティングは可視光域で反射が最小になるように設計されているため、より波長の長い近赤外域ではレンズのコーティングの効果が薄れ、反射が大きくなってしまうためです。
上右は近赤外で撮影したカメラレンズと天体望遠鏡用のカメラアダプタですが、左のカメラレンズでは黒いはずの塗装が明るい灰色に。近赤外域では反射率の高い塗料が使用されていたようです。
一方で近紫外域では、BK7を始めとする多くの光学ガラスは紫外線を通しにくい(*)ため、本格的な紫外撮影はいろいろと制約が大きく撮るだけでも大変なようです。天体写真では金星の模様の撮影で使用されているのを見るくらいで、ディープスカイでの作例はまだほとんどないようです。
(*)合成石英と蛍石は比較的紫外線の透過率が高くなっていますが、一般に紫外撮影は紫外域の透過率の低い屈折系の光学系は大いに不利になります。
フィルターによる収差
薄い平行なガラスによる光学的な影響は軽微なものですが、それでも斜入射光に対しては色収差をはじめとする諸収差による結像性能の悪化が起こりえます。
これらの収差は、フィルターが薄いほど・屈折率が低いほど・分散が小さいほど、影響が少なくなります。光路長の問題と同様、合成石英などの硝子材を使用することは有効でしょう(*)。
(*)この件が理由かどうかは不明ですが、サイトロンジャパンのQBPフィルターはセカンドバージョンからは白板ガラスに替わって合成石英が使用されています。
フィルターの精度・品質の問題
フィルターの表面の研磨精度が低かったり、脈理(ガラス中の屈折率のムラ)がある場合、像の悪化の原因となります。しかし、現実的には写真撮影では、天体望遠鏡の対物レンズのような高い精度と品質は必要ありません(*)。
(*)フィルターで一番よく使用されているのはBK7のような光学ガラスですらく、より低価格な白板ガラス(屈折率nd=1.52、アッベ数νd=58.3:特性はBK7と類似)です。より高級な材質としては屈折率・分散ともにより低い合成石英(屈折率nd=1.46、アッベ数νd=67.9)も使用されます。
近年の光学製品の製造技術レベルからみると、よほどの粗悪品でない限り、影響は軽微(*)であると推測します。
(*)一方で、回折限界レベルの解像度が要求される対象で、レンズの前面など結像面から遠い場所にフィルターを置く場合は、対物光学系と同程度の高い精度が要求されるでしょう。
フィルターを重ねることによる問題
フィルターを重ねると、ごくわずかな問題も積算されていくことになります。極端な話、フィルターを5枚、10枚と重ねると悪化は顕著になるはずです。しかし、そんな使い方をすることは普通はないでしょう。
まとめ
 160万都市・福岡市の自宅ベランダから、みずがめ座のらせん星雲NGC7293。総露出時間105分。狭帯域のワンショットナローバンドフィルターの登場で、かつては「淡い」とされていた対象が、光害地でも手軽に撮れるようになりました。これぞフィルターワークの勝利!
160万都市・福岡市の自宅ベランダから、みずがめ座のらせん星雲NGC7293。総露出時間105分。狭帯域のワンショットナローバンドフィルターの登場で、かつては「淡い」とされていた対象が、光害地でも手軽に撮れるようになりました。これぞフィルターワークの勝利!
いかがでしたか?
後付けするフィルターの存在は、いってみれば異物。光学系の結像性能的には悪くなりこそすれ、良くなることはありません。それでもフィルターを使うのは、目的に照らしたメリットがあるからです。フィルターをうまく使えば、光害の影響の強い場所でも天体撮影が可能になったり、撮影対象の特性を生かした様々な表現が可能になります
そのためには、デメリットよりもメリットを大きくすること。それが一番のポイントです。どんなデメリットがあるのか、回避・低減する方法があるとすれば何なのかをしっかり把握して、貴方の天文ライフにお役立て下さいね!
第四回の次回では、天体撮影に役立つフィルターを総まくりでご紹介します。お楽しみに!
それでは皆様のご武運をお祈りします。またお会いしましょう!
- 本記事は天文リフレクションズ編集部が独自の費用と判断で作成したものです。文責は全て天文リフレクションズ編集部にあります。
- 記事に関するご質問・お問い合わせなどは天文リフレクションズ編集部宛にお願いいたします。
- 製品の購入およびお問い合わせはメーカー様・販売店様にお願いいたします。
- 本記事によって読者様に発生した事象については、その一切について編集部では責任を取りかねますことをご了承下さい。
- 特に注記のない画像は編集部で撮影したものです。
- 記事中の製品仕様および価格は執筆時(2020年9月)のものです。
- 記事中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
https://reflexions.jp/tenref/orig/2020/09/17/11654/https://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/06068a5eac32568f58d7f6a9facc4dd9-1024x538.jpghttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/06068a5eac32568f58d7f6a9facc4dd9-150x150.jpg編集部フィルターみなさんこんにちは!
フィルターワークの徹底解説連載。第一回では、「何のためにフィルターを使うのか」というフィルターワークの基本戦略を、第二回のセンサーとカメラの感度特性では、フィルターとペアになるカメラのセンサーと、カメラに組み込まれたフィルターの波長特性を解説してきました。
「よりよい像を結ぶ」という光学的な目的に照らすと、フィルターはある意味「邪魔者」です。大なり小なり「結像性能を悪化させる」要素を持つことを理解し、その副作用を減らすように使うのが肝要です。さらに、既存の光学系のどの位置にフィルターを置く(装着する)のかは、現実的な運用の問題であると同時に、結像性能をできるだけ悪化させないように配慮しなければなりません。
第三回の今回では、そんなフィルターの副作用と置き場所について解説します!
5つの大きなフィルターの副作用
フィルターがはっきりと「悪さをする」ケースは、大きく5つあります。特に、最近の天体写真の主流である干渉フィルター(*)では、色ガラスフィルターでは起きなかった問題が存在します。天体写真のフィルターワークでは、そんな干渉フィルターの特性をよく理解しておくことが必要です。
(*)光の「干渉」の性質を利用したフィルターで、ガラスの表面にごく薄い(光の波長のオーダー)誘電体の膜を、何層(多いものでは100層以上)にも蒸着したもの。色素による吸収によって透過波長を制御する「色ガラスフィルター」とは原理が異なり、原理的には自在な透過波長のコントロールが可能です。一方で製造コストははるかに高価になります。
焦点位置の移動とそれに伴う収差の増大
詳しい理屈は省略しますが、フィルターを光学系の中に入れると、光路長がより長くなり、ピント位置が近距離側に移動します。概算的には(*)、フィルターの厚みの1/3分だけずれると覚えておけばよいでしょう。
(*) 正確には、屈折率をn、厚みをdとしたとき、d×(n-1)/n。厚み2mm、屈折率1.5の場合0.67mm。
ピントがずれることによる問題は2つあります。一つはフィルターの厚みが異なる場合はフィルター交換によってピント合わせをやり直す必要があることです。しかしこれは、まあ合わせ直せば済むことではあります。
もう一つの問題は、光学系によっては焦点位置がずれることで、設計時に想定された光学性能が出なくなる場合があることです。屈折パワーのない(凸でも凹でもない)平面の薄いフィルターによる収差は本来は微々たるもの(*)なのですが、特定の条件下では悪影響が顕在化することがあります。
(*)対物レンズの前面に置く場合、フィルターの面精度や脈理などの影響を受けることはあります。
具体的に一番問題になるのは、近距離補正機能を持つ(超)広角レンズで、リア側(レンズ後端とセンサーの間)にフィルターを挿入した場合です。上の画像はその例ですが、レンズによっては周辺像が悪化することがわかります(*)。
(*)一般に広角レンズでは、近接撮影時に像面湾曲が発生し周辺像が悪化するのを抑制するため、レンズの繰り出し量に応じて像面湾曲を補正する(逆に発生させる)「近距離補正」機能を持たせることが多いのですが、フィルターによってピント位置がずれると無限遠であるはずの被写体でも近距離補正が効いてしまうことになり、像を悪化させてしまいます。筆者の経験では、超広角レンズほど影響が顕著なようです。
この問題を解決するにはスペーサ(シムリング)をかませるなどしてレンズとマウントの間の距離を調整し(*)、対象となる天体が本来の無限遠の位置で合焦するようにすればよいのですが、物理的になかなか難しい対応です。現実的には、フィルターを薄くすることで極力影響を少なくするしかないでしょう。最近のボディ内装着フィルターは薄いものでは0.5mm程度にまで薄型化された製品も存在するようです。
(*)社外品のマウントアダプタを使用する際にも同じような問題が存在するようです。最近の超広角レンズの性能向上はめざましいものですが、その分公差にも非常に敏感です。広角レンズの個体差の問題はそのへんにも原因があるのではないかと筆者は推測しています。
一方で、最近はミラーレス一眼用にフィルターボックスを持つマウントアダプタが登場しています。フィルター厚とそれによる焦点移動がきちんと考慮されているのであれば、根本的な解決となるはずです。
広角レンズ以外でも、レデューサ・フラットナーなどの補正レンズとセンサーの間にフィルターを置くと、バックフォーカスが設計値とずれることになります。2mm厚フィルターの場合の「約0.68mm」のずれがどの程度影響するかですが、光学系によっては(*)結像性能に差が出てしまうかもしれません。
(*)筆者の経験ではF7の屈折鏡筒に可変フラットナーを使用した場合、バックフォーカスが1mm違うと、等倍画像では四隅の像に悪化とはいかないまでも「変化」がありました。広角レンズほどではないものの、一定の影響があるようです。F値の明るい鏡筒ではさらに顕著になるかもしれません。
フィルターによる反射とゴースト・迷光
ガラスに色素を混ぜ込んだ色ガラスフィルターの場合、透過しない光はフィルター材が吸収します。吸収された光はそれ以上「悪さ」をすることはありません(*)。これは実は光学系としては非常にハッピーなことです。
(*)厳密には吸収された光はエネルギーとなって温度が上昇します。太陽観察ではフィルターが加熱され割れたり燃えたりする問題があります。
一方で、最近の天体撮影での主流である「干渉フィルター」の場合、カットされた光は基本的に全て反射されます。上の画像はいろいろな天体用フィルターですが、カットする光が多いほど、鏡のように輝いて見えることがわかるでしょう。
では、それの何が問題なのでしょうか?上図左は仮想的なフィルターの波長特性図です。このフィルターを光学系とセンサーの間に入れたと考えてみましょう。
①の波長656nmの光は、フィルターを透過して全てセンサーに到達します。②の波長680nmの光は、フィルターで全反射されて光学系に入射し、レンズの表面などで反射して一部の光が再び光学系に戻ってきますが、その光はフィルターで再び全反射され、センサーには到達しません。
問題は③の波長650nmの光です。この波長では50%の光が透過し、残り50%の光が反射されます。この反射光が再び光学系で反射されて戻ってきた際には、その光のうちの50%は透過されてセンサーに届いてしまうことになります。
その結果、多くの方がすでに経験されていることとは思いますが、上の例のように輝星のまわりに円形のゴーストが出ることがあります。これは2面あるフィルターの反射面で光が反射し、センサーに戻ってきてしまうために起こります。フィルターによってはどちらの面を対物側に向けるかによって出方が変わる(*)こともあるようです。
(*)ゴーストが最小になる前後の向きを示すマークがガラスに描かれている製品もあります。一方で2面とも特性が同じで前後の区別がないフィルターもあります。
ゴースト円の大きさは、センサーとフィルターの距離が離れるほど大きくなります。ゴースト円を大きくする(センサーから遠ざける)ことで単位面積当たりの光は弱くし、ゴーストを薄くするという戦略と、ゴースト円を小さくして輝星の滲みより小さくすることで目立たなくする戦略の2つが考えられますが、どちらがいいのかはケースバイケースになると思います(*)。
(*)中途半端がいちばんイケナイ気がします。
この手のゴーストは円形のマスクで比較的簡単に画像処理で軽減できるのですが、数が多くなるとあまりやりたくない処理ではあります^^;;
星景写真で干渉フィルターを使用する場合、ゴーストはもう少しややこしい症状として表れます。写野内に極端に明るい光源がある場合、上の画像の中の例のように、大小様々なゴーストが現れてしまうことがあります(*)。
(*)その点、色ガラス系のフィルターはカットする光を吸収してくれるので、ゴーストの点では有利です。しかし色ガラス系で天体写真に有効なフィルターは、選択肢がきわめて限られるのが現状です。
レンズの前面にフィルターを装着すれば、干渉フィルターのゴースト問題は回避できますが、逆に次項の斜入射光による特性変化の問題が起きてしまいます。
ゴースト問題は単純ではなく、決定版といえる対策も少ないのですが、まずは入射光がフィルターで一部反射・一部透過されることで問題が起きうる、ということを押さえておきたいと思います。
斜入射光による特性変化
干渉フィルターでは、斜めに入射した光に対しては特性が変化してしまいます。上のグラフはIDAS社の「LPS-D1」の波長特性ですが、入射角が10°傾いただけでも波長特性は7nmほどずれてしまいます。帯域の広い光害カットフィルターなら許容範囲はまだ広いのですが、狭帯域のナローバンドフィルターではこの問題が顕著になってきます。
この問題を回避するには、フィルターに対する入射角ができるだけ垂直になるようにすることです。具体的には、レンズ前面に装着する場合は焦点距離を長くすること。この場合、上記のLPS-D1フィルターでは「画角34°」の目安に従うと焦点距離約70mm以上でなければならないことになります(*)。
(*)この制限により、星景写真や広角の星野写真では、干渉フィルターのレンズ前面装着は不適だと考えるべきでしょう。
ボディ側に装着するときはF値を明るくしすぎないことです。デジタルカメラ用のレンズは一般に光がセンサー面にできるだけ垂直に入射するように設計されていますが、F値が明るくなると斜めに入射する光の成分が多くなり、影響がより大きくなります。特に半値幅3nmといった超狭帯域のフィルターでは、F5が限界であるという情報(*)も耳にします。RASAやεなどの明るい光学系を使用する場合、極端な狭帯域フィルターは避けた方が良いかもしれません(*2)。
(*)F5の光学系の場合、写野中心の対象からの最大入射角はtan-1(1/10)=約6度。斜め6度に入射した光は0度に入射した光と比較して1-cos(6°)=0.5(%)膜厚が厚くなるのと同等。656nmの0.5%は約3.2nm。
(*2)筆者は105mmF2.0や300mmF2.8のようなレンズで半値幅7nmのHα撮影をしていますが、これまで特に困ったことは感じていませんでした。厳密に比較すると実は光量を損しているのかもしれません。
この問題を波長特性の工夫で低減しようという製品を紹介しておきましょう。上のグラフはIDASのNB(ネビュラ・ブースター)シリーズの波長特性ですが、透過すべき輝線の波長に対して、フィルターの波長特性が長波長側に振られています。これにより、より斜めに入射した光でも、透過率の高い範囲に収めようというものです(*)。
(*)Baader社のF2対応を謳うナローバンドフィルターも同じ考え方で、透過率が最高になる中心波長をずらした製品です。Fの暗い光学系では逆に不利になることに注意が必要です、
フィルターによるケラレ
フィルターのサイズ・形状・置き場所によっては、光束が遮られケラレが発生することがあります。
まずはわかりやすい例。フィルターが小さすぎる場合です。上の画像はフルサイズのデジタルカメラですが、イメージサークル(44mm径)より小さい36mm径のフィルターを使用しました。ごらんの通り、周辺が完全にケラレています。センサーの近くにフィルターを置く場合、ケラレなく使用するためにはイメージサークルよりも大きなフィルター径が必要です。
次の例。上左の画像は、カメラボディに装着するクリップ型のフィルター(上画像右)によるフラット画像。フィルター枠によるケラレが出ています。
クリップタイプのフィルターは、干渉フィルターをカメラレンズで使用する数少ない選択肢なのですが、天体望遠鏡など長焦点の対物光学系で使用すると、ケラレがそれなりに出てしまいます。焦点距離のあまり長くない(*)カメラレンズ向けと考えるべきでしょう。
(*)入射瞳径が小さい光学系ほど、影響が小さくなるようです。
レンズ前面に装着するフィルターでは、広角レンズの場合フィルター枠でケラレることもあります。上の例は24mmの広角レンズにフィルターを2枚重ねして装着したものですが、最周辺がわずかにケラレていることがわかります。
ケラレの発生の原因と影響は、比較的シンプルに予想と対策が可能です。トレードオフの部分もありますし、機材を有効活用する意味では、時にはケラレ上等で撮ることもあるでしょう。
蒸着膜のムラと個体差
干渉フィルターの蒸着膜は、光の波長のオーダーの薄さで数十、多いものでは100層以上にも重ねられています。製造する際にその厚さに誤差やムラが発生すると波長特性が設計値からずれてしまい、部分的な「色むら」となって現れたり、本来透過させるべき輝線の透過率が低下してしまうことがあります。
蒸着技術は近年めざましく進歩していますが、逆にいえばビジネス的には過渡期でもあり、品質の低いフィルターが市場に混入している可能性はないとはいえない状況かもしれません。じゅうぶんな製造技術を持っている場合でも、透過帯域の狭い「攻めた特性」の製品ほど品質の歩留まりが悪化することになり、それは販売コストに跳ね返ってきます。場合によっては「当たり外れ」の差が大きくなるとも限りません。
とはいえ、今も世界各国で多くの企業が、よりよい製品を目指して努力しています。フィルターの性能と品質は今後ますます上がっていくことでしょう。
フィルターをどこに置くか
フィルターを使うためには、光学系の中のどこかの場所に、安定して装着しなければなりません。しかし、意外と制約条件が多く、悩みの種でもあります。本項では、さまざまなフィルターの装着方法について概説します。
レンズ前面
最も自然な装着場所がレンズ前面。写真レンズ用のフィルターの装着場所として古くから使用されてきました。カメラレンズを使用する場合はノーマルな手段ではほぼ唯一の方法でもあります。しかし、前述の入射角の制限や、大径の干渉フィルターは高価で製品バリエーションが少ないこともあり、あまりガチ撮影では利用されていないようです。
しかし、前面装着はゴーストや焦点移動の問題が最も少なくなります。最近増えてきた小口径のアストログラフでは、活用の余地があるかもしれません。人と違ったことをやってみたい人にはチャンスかも?
2022/3/10追記)
対物前面装着の場合、かなりまずいゴーストが発生する事例を確認しました。イメージセンサーで反射さらた光がフィルター面で反射し再度センサー側に入射し、再結像するものと考えられます。
光学系内部
一部の大口径カメラレンズでは、レンズ前面にフィルターを置くと巨大なフィルターが必要になるため、レンズの内部にフィルターを挿入(ドロップイン)できる仕組みになっています。
例えばキヤノンの「白レンズ」と呼ばれる300mmF2.8などのモデルでは、上の画像のように52mm径のフィルターを装着して入れ込めるようになっています。一部のレンズ限定になりますが、この機構があればかなり自由な(*)フィルターワークが可能になります。
(*)とはいえ、天体用フィルターは48mm径しか存在しない製品も多く、その対策は悩ましいところです。筆者は若干無理目の工作をして回避しています。
同じような機構をより汎用的に実現したのが、BORGの「フィルターBOXn【7519】」です。M57のオス・メスの延長チューブがフィルターボックスになった形で、径48mm/52mmの双方に対応しているので数多くのフィルターが使用可能。フィルターワークという観点でも、BORGは柔軟なシステムが組める製品だといえるでしょう。
カメラアダプタや接続スリーブ、フラットナー・レデューサなどの補正レンズには、フィルター装着用のネジが切ってあるものがあります。特に2インチスリーブにはほとんど全ての製品に48mmネジ(*)が、1.25インチスリーブには31.7mmネジが切られているので、大いに利用価値があります。
(*)48mmネジ≒2インチなのですが、微妙にネジピッチの異なるのか完全にねじ込めない組み合わせがあるようです。合わなくても1回転くらいで固定することができますが、無理にねじ込まないよう要注意です。
このタイプの装着方法の欠点は専用のフィルターボックスよりも交換が面倒なこと。組み付けをばらさないと交換ができない(*)ので、SAO合成のような用途では面倒な上に構図もずれやすいのが悩みの種。
(*)現場で交換するのもかなり気を遣います。筆者は過去2回脱着時に落としました^^;;;冬場は息や指の湿気で曇ってしまうのも悲しいところ。
カメラレンズ後面
いわゆる「出目金レンズ」と呼ばれるような前玉が大きく飛び出したレンズや、魚眼レンズのような画角の広いレンズの場合、レンズ全面にフィルターを装着するにはレンズよりも大きなフィルターが必要になり現実的ではありません。このため上の画像のように、レンズの後面にシート型の薄いフィルターを差し込めるようになっている製品があります。
しかし、ディープスカイ撮影では今のところあまり有効な使い道がありません。厚いガラスフィルターは差し込めない上に、前述の光路長変化による星像悪化のリスクがあります。極薄のフィルターは仮に入手できたとしても挿入時に割れてしまうかもしれません。
一方で、リア装着は星景写真でソフトフィルターを使用する良い方法です。前面装着で起きる、周辺の輝星が楕円になる現象を回避できるからです。
カメラボディ内
一般に「クリップタイプ」と呼ばれる、カメラボディ内に装着する特殊な枠を持ったフィルターが販売されています。レンズを選ばないメリットがある反面、脱着に神経を使うこと、前述のフィルター枠によるケラレや光路長変化による星像悪化の可能性などの欠点があります。
とはいえ一眼レフ機では、広角を含むカメラレンズで干渉フィルターを使うには、事実上この方法しかありません(*)。欠点をうまくカバー、ないしは受け入れて使うのが肝要です。
(*)ミラーレスカメラの場合は、前述のマウントアダプタに装着する方法があります。
センサー直前
センサーの直前は、実はフィルターにとっては特等席です。この場所がゴーストや収差などの光学的な副作用が一番少ない場所だからです。ゆえに、この場所にはすでにデジタルカメラが必要とする「UV-IRカットフィルター」などが鎮座していて、ユーザーの手で簡単に付け外しできる場所ではありません。現実的には利用できない(*)装着場所といえます。
(*)この場所に踏み込んでフィルターを交換するのが「天体改造」です。
そのほかの副作用
最後に、そのほかのフィルターによる副作用をまとめておきます。これらはいずれも特殊なケース・極端な使用方法でしか問題にならないレベルのものです。
光量の損失
フィルターの硝材が一定量光を吸収します。しかし、硝材の吸収による光量損失はほんのわずか(*)で、薄いフィルターにおいては誤差の範囲にもならないレベルです。
(*)最も広く使われている光学硝子材「BK7」の場合、可視光域では厚さ100mmでもわずか約1.6%です。一方で380nmよりも短波長では硝子材による吸収が顕著になってきます。
むしろ問題になるのは表面反射による損失ですが、これは昨今の高性能なマルチコートであれば2面で0.4〜1.0%程度です。これもほとんど気にしなくていいレベルです。
光学系の想定波長域からの逸脱
デジタルカメラは基本的に可視光線(400nm〜650nm)を想定して設計されているため、改造やフィルターを使用することでこれを大きく逸脱する場合は、問題が出てくることもあります。
上左の画像は近赤外による撮影ですが、ひどいゴーストが出ています。レンズのコーティングは可視光域で反射が最小になるように設計されているため、より波長の長い近赤外域ではレンズのコーティングの効果が薄れ、反射が大きくなってしまうためです。
上右は近赤外で撮影したカメラレンズと天体望遠鏡用のカメラアダプタですが、左のカメラレンズでは黒いはずの塗装が明るい灰色に。近赤外域では反射率の高い塗料が使用されていたようです。
一方で近紫外域では、BK7を始めとする多くの光学ガラスは紫外線を通しにくい(*)ため、本格的な紫外撮影はいろいろと制約が大きく撮るだけでも大変なようです。天体写真では金星の模様の撮影で使用されているのを見るくらいで、ディープスカイでの作例はまだほとんどないようです。
(*)合成石英と蛍石は比較的紫外線の透過率が高くなっていますが、一般に紫外撮影は紫外域の透過率の低い屈折系の光学系は大いに不利になります。
フィルターによる収差
薄い平行なガラスによる光学的な影響は軽微なものですが、それでも斜入射光に対しては色収差をはじめとする諸収差による結像性能の悪化が起こりえます。
これらの収差は、フィルターが薄いほど・屈折率が低いほど・分散が小さいほど、影響が少なくなります。光路長の問題と同様、合成石英などの硝子材を使用することは有効でしょう(*)。
(*)この件が理由かどうかは不明ですが、サイトロンジャパンのQBPフィルターはセカンドバージョンからは白板ガラスに替わって合成石英が使用されています。
フィルターの精度・品質の問題
フィルターの表面の研磨精度が低かったり、脈理(ガラス中の屈折率のムラ)がある場合、像の悪化の原因となります。しかし、現実的には写真撮影では、天体望遠鏡の対物レンズのような高い精度と品質は必要ありません(*)。
(*)フィルターで一番よく使用されているのはBK7のような光学ガラスですらく、より低価格な白板ガラス(屈折率nd=1.52、アッベ数νd=58.3:特性はBK7と類似)です。より高級な材質としては屈折率・分散ともにより低い合成石英(屈折率nd=1.46、アッベ数νd=67.9)も使用されます。
近年の光学製品の製造技術レベルからみると、よほどの粗悪品でない限り、影響は軽微(*)であると推測します。
(*)一方で、回折限界レベルの解像度が要求される対象で、レンズの前面など結像面から遠い場所にフィルターを置く場合は、対物光学系と同程度の高い精度が要求されるでしょう。
フィルターを重ねることによる問題
フィルターを重ねると、ごくわずかな問題も積算されていくことになります。極端な話、フィルターを5枚、10枚と重ねると悪化は顕著になるはずです。しかし、そんな使い方をすることは普通はないでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
後付けするフィルターの存在は、いってみれば異物。光学系の結像性能的には悪くなりこそすれ、良くなることはありません。それでもフィルターを使うのは、目的に照らしたメリットがあるからです。フィルターをうまく使えば、光害の影響の強い場所でも天体撮影が可能になったり、撮影対象の特性を生かした様々な表現が可能になります
そのためには、デメリットよりもメリットを大きくすること。それが一番のポイントです。どんなデメリットがあるのか、回避・低減する方法があるとすれば何なのかをしっかり把握して、貴方の天文ライフにお役立て下さいね!
第四回の次回では、天体撮影に役立つフィルターを総まくりでご紹介します。お楽しみに!
それでは皆様のご武運をお祈りします。またお会いしましょう!
本記事は天文リフレクションズ編集部が独自の費用と判断で作成したものです。文責は全て天文リフレクションズ編集部にあります。
記事に関するご質問・お問い合わせなどは天文リフレクションズ編集部宛にお願いいたします。
製品の購入およびお問い合わせはメーカー様・販売店様にお願いいたします。
本記事によって読者様に発生した事象については、その一切について編集部では責任を取りかねますことをご了承下さい。
特に注記のない画像は編集部で撮影したものです。
記事中の製品仕様および価格は執筆時(2020年9月)のものです。
記事中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。編集部山口
千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフOriginal


























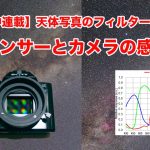
コメントを残す