星ナビ2025年1月号ご紹介
アストロアーツHPで星ナビ2025年1月号の内容が告知されています。発売は12月5日 木曜日です。
目次
今月の内容は!?
特別付録は2025年の現象がまとまった「星空ハンドブック2025」。毎年恒例の「星のゆく年くる年」で、2024年の振り返りと2025年の準備をしましょう。
星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13854_hoshinavi
■表紙
今回の表紙は露木孝範さん作の「紫金山・アトラス彗星と富士山」(星ナビギャラリー応募作品)。彗星と富士山による新年らしい作品です。
「富士山には大彗星がよく似合う」。今月の表紙は星ナビギャラリー応募作から。撮影者の露木さんは「星景写真を始めてまだ数年」とのことですが、素晴らしいチャンスをものにされました。わずか10行ですが、本誌の撮影者コメントをぜひごらんください。この作品にかけられた想いと感激が伝わってきます^^
今回の紫金山・アトラス彗星はいろいろな意味で歴史に残る大彗星だったと感じていますが、その1つに「肉眼で尾が見える彗星」を多くの方が初体験されたことがあると思います。まだ見ぬ次の大彗星では、さらに盛り上がるといいですね!
■ダストの尾とイオンの尾の見え方を検証 紫金山・アトラス彗星の尾(解説/菅原 賢)
太陽系の彼方から長い旅を経て訪れた汚れた雪玉が、太陽の力を借り、コマと尾をまとった彗星として舞台にあがる時間はほんの一瞬。「ステラナビゲータ12」のシミュレーション機能を使って、紫金山・アトラス彗星の尾にスポットをあてて振り返ってみましょう。
大彗星となった紫金山・アトラス彗星ですが、非常にダストが多く明るい尾が印象的でしたね。日々変わっていく彗星の尾の姿は多くの方の記憶にも鮮明に残っていることでしょう。
本記事では、紫金山・アトラス彗星の姿を時系列に辿りながら「なぜこんな姿をしているか」が天文学的に考察されています。「新しいダストと古いダスト」「シンクロン」「シンダイン」「β値」「ネックライン構造」など、馴染みの薄い専門用語も出てきますが、基本的には彗星とその軌道を立体的に考えれば、直感的に理解できるものです。ぜひ彗星のビジュアルとともに、じっくり読み進めてみてください。
さらに「ステラナビゲータ12」に実装されている「テイル編集」という、彗星の尾の形状をいくつかのパラメータを設定することでシミュレーションできる機能で、理論モデルと実際の形状の差を検証されているのにも注目です。
■2025年の天文トピック総まとめ 星のゆく年(まとめ/谷川正夫・中野太郎・塚田 健・川村 晶)
1月号恒例。2024年の天文界振り返り。最大のイベントが紫金山・アトラス彗星であったことは多くの方の共通認識かと思いますが、昨年同様「天文現象」「天文学・宇宙開発」「天文普及」「天文機材」の4つの視点で振り返る2024年です。
◎2024年の天文現象(まとめ/谷川正夫)
紫金山・アトラス彗星や低緯度オーロラ、ペルセウス座流星群などが話題になりました。
◎2024年の天文学・宇宙開発(まとめ/中野太郎)
月面に着陸した「SLIM」やH3ロケットの打ち上げ成功、X線衛星「XRISM」の稼働開始など、宇宙開発分野でも大きな飛躍がありました。
◎2024年の天文普及(まとめ/塚田 健)
プラネタリウム100周年を記念し、今年も各地でイベントが開催。天文宇宙関連のアニメやドラマも話題になりました。
◎2024年の天文機材(まとめ/川村 晶)
例年以上に話題が多かった2024年の天文機材市場。国内・海外の天体望遠鏡や双眼鏡、天体撮影機材をまとめました。
■2025年の天文現象ピックアップ 星のくる年(解説/浅田英夫)
2025年の天文界は、私たちにどんな天文ショーを見せてくれるでしょうか。土星の環の消失や好条件の皆既月食、4回のプレアデス星団食、火星接近、ふたご座流星群など2025年も楽しみが目白押しです。
こちらも1月号恒例。2025年の天文現象ピックアップ。9月8日の全国で好条件で見られる皆既月食がハイライト。M45すばるの月による掩蔽が4回もあったり、土星の環の消失や1月早々に接近する火星など、地味ながらも見逃せない現象は、例年の通り多数です。
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・Celestron天体望遠鏡 Origin
CP+2024でも出品されていたセレストロン社のスマート望遠鏡「Origin」。口径6インチ(152mm)F2.2のRASA光学系と1/1.8型のイメージセンサー使用し、スマート望遠鏡の中では最もハイエンドな製品の1つといえるでしょう。
Celestron 天体望遠鏡 Origin
https://www.vixen.co.jp/product/36232_5/
直販価格100万円越えとアマチュアが導入するにはやや敷居が高いですが、公共天文台や学校など天文普及分野での用途に最適かもしれません(*)。
(*)観望会ではF2.2による「ハイスピード」が大きく生きてくるものと推測
2024年の後半は各社のスマート望遠鏡の新製品ラッシュ。これからの広がりが楽しみですね。
■News Watch 秋空の下で星三昧(レポート●飯島裕/山口千宗)
11月上旬に開催された2つの星まつり「小海星フェス(八ヶ岳 星と自然のフェスタinこうみ)」と「星宴2024」。飯島裕さんと不肖・天リフ編集長のレポートです。
天文リフレクションズは、小海星フェス・星宴とも運営サイドのスタッフとして参加しましたが、どちらも前年を超える盛り上がりと内容の充実度であると実感しました。星まつりは参加者に喜んでもらえることがまず一番。来年以降はさらに一般層の参加者を増やし、天文趣味界のアウトリーチにも貢献したいと考えています。
■ネットよ今夜もありがとう
今月は木曽星の会(会長:清水醇さん)。2004年設立の比較的新しい?会です。東大の木曽観測所とさまざまな形で連携した活動を行われているのが大きな特徴。
木曽星の会
http://kisohosi.starfree.jp/index.html
毎年夏に行われる木曽観測所の特別公開ではスタッフとして協力されるなど、地域に密着した観望会や講演会を定期的に実施されています。

木曽星の会に於きましては、イベント等の情報及び日頃から木曽星の会に興味を持っていただいている方々の為にLINEアカウントをつくりました。また、星や宇宙に興味がある方々の為に色々な情報を流して行きたいとたいと思います。
下記URLまたはQRコードからご登録ください。
公式LINEアカウントもあります。ご興味のある方はHPのQRコードから友達登録してみてください!
■星ナビギャラリー
今回のトップ下は大ベテラン若杉さんの「紫金山・アトラス彗星」。若杉さんの作品を含め、上の画像の4ページ・8作品はいずれも秀作揃いです。
個人的イチオシは「もう全部」という感じです。薄明に負けない明るさだった紫金山・アトラス彗星ですが、そのことが地上風景の描写に有利に働いたのでしょう。それも、ほんのわずかな撮影時間とシャッターチャンスを逃さない撮影者様の熱意と技量があってこそですね。日頃の研鑽の結果が発揮されたといえるでしょう。
■特別付録 星空ハンドブック2025
2025年の毎月の星図と主な天文現象、惑星の動き、天体出没表などをまとめた便利なハンドブック。星撮りや観望など、フィールドで使いやすいサイズです。
1月号恒例の「星空ハンドブック」。毎月・毎日の基本データと主な天文現象が網羅されています。2025年のハイライトは「皆既月食(9月8日)」と4回もある「プレアデス星団食」です。ほかにも火星の接近(準・小接近?ですが)と土星の環の消失(太陽に近いのであまり条件が良くないですが)。ぜひチェックしてみてください!
■ Observer’s NAVI 各現象の注目ポイント(解説/佐藤幹哉、高橋 進、早水 勉、吉本勝己)
流星群、変光星、小惑星による恒星食、彗星、新天体・太陽系小天体について、2024年の成果と2025年の注目トピックをまとめました。
こちらも1月号恒例。「Observer’s NAVI」拡大版10ページ。「2025の三大流星群と興味深い流星群」「かんむり座T星の増光は?」「小惑星による恒星食ハイライト2025」「天文史に残る紫金山・アトラス彗星」「アトラス彗星(C/2024 G3)が太陽に接近」など。詳細はぜひ本誌で!
まとめ
いかがでしたか?
定番企画・記事の比率の高い1月号ですが、毎年1月号を目にすると「今年も1年が終わってゆくなあ」と感じますね。皆さんにとって、今年はどんな年でしたか?そして来年も充実した天文ライフが過ごせますように!
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、毎月5日は天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13854_hoshinavi
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
https://reflexions.jp/tenref/orig/2024/12/02/17162/https://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2024/11/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-1-1024x538.jpghttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2024/11/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-1-150x150.jpg雑誌・書籍星ナビアストロアーツHPで星ナビ2025年1月号の内容が告知されています。発売は12月5日 木曜日です。
今月の内容は!?
特別付録は2025年の現象がまとまった「星空ハンドブック2025」。毎年恒例の「星のゆく年くる年」で、2024年の振り返りと2025年の準備をしましょう。
星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13854_hoshinavi
■表紙
「富士山には大彗星がよく似合う」。今月の表紙は星ナビギャラリー応募作から。撮影者の露木さんは「星景写真を始めてまだ数年」とのことですが、素晴らしいチャンスをものにされました。わずか10行ですが、本誌の撮影者コメントをぜひごらんください。この作品にかけられた想いと感激が伝わってきます^^
今回の紫金山・アトラス彗星はいろいろな意味で歴史に残る大彗星だったと感じていますが、その1つに「肉眼で尾が見える彗星」を多くの方が初体験されたことがあると思います。まだ見ぬ次の大彗星では、さらに盛り上がるといいですね!
■ダストの尾とイオンの尾の見え方を検証 紫金山・アトラス彗星の尾(解説/菅原 賢)
大彗星となった紫金山・アトラス彗星ですが、非常にダストが多く明るい尾が印象的でしたね。日々変わっていく彗星の尾の姿は多くの方の記憶にも鮮明に残っていることでしょう。
本記事では、紫金山・アトラス彗星の姿を時系列に辿りながら「なぜこんな姿をしているか」が天文学的に考察されています。「新しいダストと古いダスト」「シンクロン」「シンダイン」「β値」「ネックライン構造」など、馴染みの薄い専門用語も出てきますが、基本的には彗星とその軌道を立体的に考えれば、直感的に理解できるものです。ぜひ彗星のビジュアルとともに、じっくり読み進めてみてください。
さらに「ステラナビゲータ12」に実装されている「テイル編集」という、彗星の尾の形状をいくつかのパラメータを設定することでシミュレーションできる機能で、理論モデルと実際の形状の差を検証されているのにも注目です。
■2025年の天文トピック総まとめ 星のゆく年(まとめ/谷川正夫・中野太郎・塚田 健・川村 晶)
1月号恒例。2024年の天文界振り返り。最大のイベントが紫金山・アトラス彗星であったことは多くの方の共通認識かと思いますが、昨年同様「天文現象」「天文学・宇宙開発」「天文普及」「天文機材」の4つの視点で振り返る2024年です。
◎2024年の天文現象(まとめ/谷川正夫)
◎2024年の天文学・宇宙開発(まとめ/中野太郎)
◎2024年の天文普及(まとめ/塚田 健)
◎2024年の天文機材(まとめ/川村 晶)
■2025年の天文現象ピックアップ 星のくる年(解説/浅田英夫)
こちらも1月号恒例。2025年の天文現象ピックアップ。9月8日の全国で好条件で見られる皆既月食がハイライト。M45すばるの月による掩蔽が4回もあったり、土星の環の消失や1月早々に接近する火星など、地味ながらも見逃せない現象は、例年の通り多数です。
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・Celestron天体望遠鏡 Origin
CP+2024でも出品されていたセレストロン社のスマート望遠鏡「Origin」。口径6インチ(152mm)F2.2のRASA光学系と1/1.8型のイメージセンサー使用し、スマート望遠鏡の中では最もハイエンドな製品の1つといえるでしょう。
Celestron 天体望遠鏡 Originhttps://www.vixen.co.jp/product/36232_5/
直販価格100万円越えとアマチュアが導入するにはやや敷居が高いですが、公共天文台や学校など天文普及分野での用途に最適かもしれません(*)。
(*)観望会ではF2.2による「ハイスピード」が大きく生きてくるものと推測
2024年の後半は各社のスマート望遠鏡の新製品ラッシュ。これからの広がりが楽しみですね。
■News Watch 秋空の下で星三昧(レポート●飯島裕/山口千宗)
11月上旬に開催された2つの星まつり「小海星フェス(八ヶ岳 星と自然のフェスタinこうみ)」と「星宴2024」。飯島裕さんと不肖・天リフ編集長のレポートです。
天文リフレクションズは、小海星フェス・星宴とも運営サイドのスタッフとして参加しましたが、どちらも前年を超える盛り上がりと内容の充実度であると実感しました。星まつりは参加者に喜んでもらえることがまず一番。来年以降はさらに一般層の参加者を増やし、天文趣味界のアウトリーチにも貢献したいと考えています。
■ネットよ今夜もありがとう
今月は木曽星の会(会長:清水醇さん)。2004年設立の比較的新しい?会です。東大の木曽観測所とさまざまな形で連携した活動を行われているのが大きな特徴。
木曽星の会http://kisohosi.starfree.jp/index.html
毎年夏に行われる木曽観測所の特別公開ではスタッフとして協力されるなど、地域に密着した観望会や講演会を定期的に実施されています。
木曽星の会に於きましては、イベント等の情報及び日頃から木曽星の会に興味を持っていただいている方々の為にLINEアカウントをつくりました。また、星や宇宙に興味がある方々の為に色々な情報を流して行きたいとたいと思います。下記URLまたはQRコードからご登録ください。
公式LINEアカウントもあります。ご興味のある方はHPのQRコードから友達登録してみてください!
■星ナビギャラリー
今回のトップ下は大ベテラン若杉さんの「紫金山・アトラス彗星」。若杉さんの作品を含め、上の画像の4ページ・8作品はいずれも秀作揃いです。
個人的イチオシは「もう全部」という感じです。薄明に負けない明るさだった紫金山・アトラス彗星ですが、そのことが地上風景の描写に有利に働いたのでしょう。それも、ほんのわずかな撮影時間とシャッターチャンスを逃さない撮影者様の熱意と技量があってこそですね。日頃の研鑽の結果が発揮されたといえるでしょう。
■特別付録 星空ハンドブック2025
1月号恒例の「星空ハンドブック」。毎月・毎日の基本データと主な天文現象が網羅されています。2025年のハイライトは「皆既月食(9月8日)」と4回もある「プレアデス星団食」です。ほかにも火星の接近(準・小接近?ですが)と土星の環の消失(太陽に近いのであまり条件が良くないですが)。ぜひチェックしてみてください!
■ Observer's NAVI 各現象の注目ポイント(解説/佐藤幹哉、高橋 進、早水 勉、吉本勝己)
こちらも1月号恒例。「Observer's NAVI」拡大版10ページ。「2025の三大流星群と興味深い流星群」「かんむり座T星の増光は?」「小惑星による恒星食ハイライト2025」「天文史に残る紫金山・アトラス彗星」「アトラス彗星(C/2024 G3)が太陽に接近」など。詳細はぜひ本誌で!
まとめ
いかがでしたか?
定番企画・記事の比率の高い1月号ですが、毎年1月号を目にすると「今年も1年が終わってゆくなあ」と感じますね。皆さんにとって、今年はどんな年でしたか?そして来年も充実した天文ライフが過ごせますように!
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、毎月5日は天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2025」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13854_hoshinavi
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
編集部山口
千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフOriginal
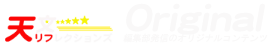

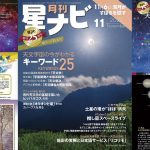



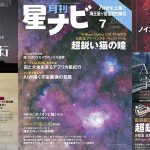
コメントを残す