星ナビ2025年9月号ご紹介
アストロアーツHPで星ナビ2025年9月号の内容が告知されています。発売は8月5日 火曜日です。
目次
今月の内容は!?
特集「Askar屈折望遠鏡のすべて」では、天体望遠鏡ショップ店員が多様な鏡筒の特長や特性を紹介します。9月8日には待ちに待った「皆既月食」もあります!
星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14110_hoshinavi
■表紙
今回の表紙は渡邉耕平さん撮影の「M31」。Askar 130PHQによる撮影です。特集「Askar屈折望遠鏡のすべて」ではAskarシリーズの豊富なラインナップを一覧できます。
今月の表紙は、大口径のフォトビジュアル鏡筒「Askar 130PHQ」によるアンドロメダ銀河M31です。総露光時間は昨今のディープスカイ撮影では短め?の2時間ですが、素晴らしくディテールが描出されています。
本誌記事の「Askar屈折望遠鏡のすべて」と合わせてごらんください!
■全ラインナップ研究 Askar屈折望遠鏡のすべて(紹介・作例/渡邉耕平)
中国・SHARPSTAR社のブランド「SHARPSTAR」と「Askar」は、屈折望遠鏡だけでも20種類以上の天体望遠鏡を発売し、その高い性能とコストパフォーマンス、デザインで、国内外から支持されてきました。天体望遠鏡ショップ店員が各シリーズの特長や特性を紹介します。
高品質で低価格の製品が続々と登場している中国製天体望遠鏡。その主力メーカーの1つが中国・SHARPSTAR社です。本記事では「誰よりもSTARPSTAR社の望遠鏡に触れてきた」サイトロンジャパン直営の天体望遠鏡ショップ・シュミットの渡邉耕平さんが、STARPSTARの様々な屈折天体望遠鏡を徹底解説。
SHARPSTAR社からは、フラッグシップの「SQAシリーズ」から、つい先日新発売された低価格の「80ED」まで、2020年以降でも実に20種類以上の製品が発売されていますが、それぞれのシリーズ・モデルの設計コンセプトや得意分野の違いがわかりやすく解説されています。
特に「目的と重さ、予算からあなたに最適の1本を見つけ出す」の項は、天体望遠鏡選びの留意点とノウハウが、過去イチレベルで整理されていて必読級です!
■未明の赤い月 9月8日皆既月食(解説/谷川正夫)

9月8日未明の皆既月食。1時27分に欠け始め、4時56分に部分食終了。日本全国で見られる好条件です。経験豊富な谷川正夫さんが、基本データから拡大撮影から皆既月食と風景の撮影までをナビゲートします。
日本国内で見られる皆既月食は、2022年11月8日の「天王星食付き」の皆既月食以来、約3年ぶりです。そこそこ食分が深い(最大食分1.36)ので、たとえば超広角レンズなら天の川と赤い月も撮影可能。事前にテーマを決めてじっくり取り組んでみたいものですね!
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・マルミ光機 マグネットスリム フォーカスエイド フィルター
ディープスカイ撮影で使用される「バーティノフマスク」と同じ原理で、カメラレンズでのマニュアルフォーカスを支援するフィルターです。同社のマグネット式のフィルター交換システム「マグネットスリム」に対応しているので、簡単に脱着してソフトフィルターや光害カットフィルターに換装できるのも大きな特徴。
星空のピント合わせは、慣れが必要で特に初心者には難しいもの。シーンに合わせて活用してみたいツールです。
マルミ光機 マグネットスリム フォーカスエイドフィルター
https://www.marumi-filter.co.jp/filternow/news/fa/
詳細は上記動画またマルミ光機のWebサイトでごらんください!
■3例目の恒星間天体 3I/ATLAS発見(解説/吉本勝己)
「太陽系の外からやってきた」3I/ATLASが、Observer’s NAVIで詳しく解説されています。上の画像は軌道図ですが、「ほぼ直線に近い双曲線軌道で高速に太陽系に入り、そして去っていく」「離心率6」という特異な軌道が見て取れます。
地球にも太陽にもあまり接近しないため、光度があまり上がらないのが残念ですが、最も明るくなる11月中旬の予想光度は15等。これならアマチュア機材でも存在を写すことは可能でしょう。記事には星図も掲載されていますので、ぜひ秋の撮影プランに追加してみてはいかがでしょう。
■星ナビギャラリー
今回のトップ下は村嶋陽一さんの「春濤に錨を上げる」。村嶋さんは様々な小物などで工夫した創作星景でたびたびギャラリーに掲載されている方ですが、今回の工夫は「ボトルメール」。春の穏やかに打ち寄せる波打ち際「春濤(しゅんとう)」の深い青い色は夜光虫なのでしょうか。
個人的イチオシは草野敬紀さんの「銀河系中心部」。「美しい星野写真のリファレンスとなるような作品を目指した」と撮影者コメントにありますが、まさにこれぞ天の川銀河中心部!と感じる仕上がりです。天体写真は宇宙のほんのわずかな光と色をデジタル処理で自在に強調できる世界ではありますが、暗黒星雲から明るい恒星・星雲の中心部までの階調をフルに生かしつつ、破綻のない美しいバランスで仕上げられています。
ネットよ今夜もありがとう〜藤のゆ のInstagram
今月は、岡山で星空案内人として活動中の藤原浩さん。これまでSNSには積極的ではなかったそうですが、周囲からの勧めで始められたとこのこと。
Instagram 藤のゆ
https://www.instagram.com/fujino._.yu/
ディープスカイから星空風景・観測風景まで、さまざまなジャンルの写真がアップされています。ぜひ「いいね」と「フォロー」を!
■ニュースを深掘り!V宙部 スマート望遠鏡Seestar借りてみた!(レポート/猫谷ここな)
天文系VTuberが話題のトピックを紹介するコーナー。やさしい星空解説で活躍中の猫谷ここなさんが望遠鏡レンタルサービス「レントミ」で「Seestar S50」を借りて配信に挑戦します!
ここにゃー!天文系VTuberの猫谷ここなさんが、天文ハウスTOMITAさんのレンタルサービス「レントミ」でSeestar S50を借りて(7泊8日で9,000円)使ってみるという企画。
猫谷ここなさんは、ふだんはビクセンのポルタIIA80Mfを使用されているそうですが、開梱から組立・使用まで「超簡単」「手軽」に使用することができたそうです。視聴者のリクエストに応えながら天体を見ていくというライブ配信も実施されたそうです。ぜひごらんになってください!
YouTube 猫谷ここな -Nekoya Cocona‐
https://www.youtube.com/@Nekoya_Cocona
Rentomi 【 レントミ 】 – 天文機材のレンタル専門店
https://rentomi.jp/
■ 星の街道をゆく プラネタリウムはじまりへの旅 後編(紀行/中山満仁)
プラネタリウムの源流を追い求めて旅をする筆者。前編(2025年8月号)では、紀元前1世紀に作られた「アンティキテラの機械」に行き着きました。後編では歴史をさらに遡り、青銅器時代のヨーロッパに存在した遺物「ネブラ・スカイディスク」を見るため、再びドイツに旅立ちます。
100年の歴史の「近代プラネタリウム」からさらに遡り、その源流を追い求める旅、後編。本記事のメインは、3600年前の青銅器時代に作られたという「ネブラ・スカイディスク」のお話です。
「ネブラ・スカイディスク」とは、1999年に発見された「太陽暦と太陰暦を組み合わせた天文時計」で、同時に発見された青銅器の年代測定からおよそ3600年前に作られたものと考えられているそうです。
発見(実は盗掘)から闇マーケットを経て博物館に収蔵されるまでの捕物劇や、考古学的・天文学的な正体を突き止めるまでの経緯はぜひ本誌記事でごらんください!
Wikipedia ネブラ・ディスク
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF
まとめ
いかがでしたか?
予想外に好天の続いた7月ですが、皆様星空は堪能できましたでしょうか^^今年の夏は大きなイベントこそ少ないですが、この好天が8月も継続するなら、天文ファンにとってはこの10年で最高レベルの夏になるかもしれませんね!
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、今月5日は天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14110_hoshinavi
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
https://reflexions.jp/tenref/orig/2025/08/04/18106/https://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2025/08/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-1024x538.jpghttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2025/08/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-150x150.jpg雑誌・書籍星ナビアストロアーツHPで星ナビ2025年9月号の内容が告知されています。発売は8月5日 火曜日です。
今月の内容は!?
特集「Askar屈折望遠鏡のすべて」では、天体望遠鏡ショップ店員が多様な鏡筒の特長や特性を紹介します。9月8日には待ちに待った「皆既月食」もあります!
星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14110_hoshinavi
■表紙
今月の表紙は、大口径のフォトビジュアル鏡筒「Askar 130PHQ」によるアンドロメダ銀河M31です。総露光時間は昨今のディープスカイ撮影では短め?の2時間ですが、素晴らしくディテールが描出されています。
本誌記事の「Askar屈折望遠鏡のすべて」と合わせてごらんください!
■全ラインナップ研究 Askar屈折望遠鏡のすべて(紹介・作例/渡邉耕平)
高品質で低価格の製品が続々と登場している中国製天体望遠鏡。その主力メーカーの1つが中国・SHARPSTAR社です。本記事では「誰よりもSTARPSTAR社の望遠鏡に触れてきた」サイトロンジャパン直営の天体望遠鏡ショップ・シュミットの渡邉耕平さんが、STARPSTARの様々な屈折天体望遠鏡を徹底解説。
SHARPSTAR社からは、フラッグシップの「SQAシリーズ」から、つい先日新発売された低価格の「80ED」まで、2020年以降でも実に20種類以上の製品が発売されていますが、それぞれのシリーズ・モデルの設計コンセプトや得意分野の違いがわかりやすく解説されています。
特に「目的と重さ、予算からあなたに最適の1本を見つけ出す」の項は、天体望遠鏡選びの留意点とノウハウが、過去イチレベルで整理されていて必読級です!
■未明の赤い月 9月8日皆既月食(解説/谷川正夫)
9月8日未明の皆既月食。1時27分に欠け始め、4時56分に部分食終了。日本全国で見られる好条件です。経験豊富な谷川正夫さんが、基本データから拡大撮影から皆既月食と風景の撮影までをナビゲートします。
日本国内で見られる皆既月食は、2022年11月8日の「天王星食付き」の皆既月食以来、約3年ぶりです。そこそこ食分が深い(最大食分1.36)ので、たとえば超広角レンズなら天の川と赤い月も撮影可能。事前にテーマを決めてじっくり取り組んでみたいものですね!
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・マルミ光機 マグネットスリム フォーカスエイド フィルター
ディープスカイ撮影で使用される「バーティノフマスク」と同じ原理で、カメラレンズでのマニュアルフォーカスを支援するフィルターです。同社のマグネット式のフィルター交換システム「マグネットスリム」に対応しているので、簡単に脱着してソフトフィルターや光害カットフィルターに換装できるのも大きな特徴。
星空のピント合わせは、慣れが必要で特に初心者には難しいもの。シーンに合わせて活用してみたいツールです。
マルミ光機 マグネットスリム フォーカスエイドフィルターhttps://www.marumi-filter.co.jp/filternow/news/fa/
詳細は上記動画またマルミ光機のWebサイトでごらんください!
■3例目の恒星間天体 3I/ATLAS発見(解説/吉本勝己)
「太陽系の外からやってきた」3I/ATLASが、Observer's NAVIで詳しく解説されています。上の画像は軌道図ですが、「ほぼ直線に近い双曲線軌道で高速に太陽系に入り、そして去っていく」「離心率6」という特異な軌道が見て取れます。
地球にも太陽にもあまり接近しないため、光度があまり上がらないのが残念ですが、最も明るくなる11月中旬の予想光度は15等。これならアマチュア機材でも存在を写すことは可能でしょう。記事には星図も掲載されていますので、ぜひ秋の撮影プランに追加してみてはいかがでしょう。
■星ナビギャラリー
今回のトップ下は村嶋陽一さんの「春濤に錨を上げる」。村嶋さんは様々な小物などで工夫した創作星景でたびたびギャラリーに掲載されている方ですが、今回の工夫は「ボトルメール」。春の穏やかに打ち寄せる波打ち際「春濤(しゅんとう)」の深い青い色は夜光虫なのでしょうか。
個人的イチオシは草野敬紀さんの「銀河系中心部」。「美しい星野写真のリファレンスとなるような作品を目指した」と撮影者コメントにありますが、まさにこれぞ天の川銀河中心部!と感じる仕上がりです。天体写真は宇宙のほんのわずかな光と色をデジタル処理で自在に強調できる世界ではありますが、暗黒星雲から明るい恒星・星雲の中心部までの階調をフルに生かしつつ、破綻のない美しいバランスで仕上げられています。
ネットよ今夜もありがとう〜藤のゆ のInstagram
今月は、岡山で星空案内人として活動中の藤原浩さん。これまでSNSには積極的ではなかったそうですが、周囲からの勧めで始められたとこのこと。
Instagram 藤のゆhttps://www.instagram.com/fujino._.yu/
ディープスカイから星空風景・観測風景まで、さまざまなジャンルの写真がアップされています。ぜひ「いいね」と「フォロー」を!
■ニュースを深掘り!V宙部 スマート望遠鏡Seestar借りてみた!(レポート/猫谷ここな)
ここにゃー!天文系VTuberの猫谷ここなさんが、天文ハウスTOMITAさんのレンタルサービス「レントミ」でSeestar S50を借りて(7泊8日で9,000円)使ってみるという企画。
猫谷ここなさんは、ふだんはビクセンのポルタIIA80Mfを使用されているそうですが、開梱から組立・使用まで「超簡単」「手軽」に使用することができたそうです。視聴者のリクエストに応えながら天体を見ていくというライブ配信も実施されたそうです。ぜひごらんになってください!
YouTube 猫谷ここな -Nekoya Cocona‐https://www.youtube.com/@Nekoya_Cocona
Rentomi 【 レントミ 】 - 天文機材のレンタル専門店https://rentomi.jp/
■ 星の街道をゆく プラネタリウムはじまりへの旅 後編(紀行/中山満仁)
100年の歴史の「近代プラネタリウム」からさらに遡り、その源流を追い求める旅、後編。本記事のメインは、3600年前の青銅器時代に作られたという「ネブラ・スカイディスク」のお話です。
「ネブラ・スカイディスク」とは、1999年に発見された「太陽暦と太陰暦を組み合わせた天文時計」で、同時に発見された青銅器の年代測定からおよそ3600年前に作られたものと考えられているそうです。
発見(実は盗掘)から闇マーケットを経て博物館に収蔵されるまでの捕物劇や、考古学的・天文学的な正体を突き止めるまでの経緯はぜひ本誌記事でごらんください!
Wikipedia ネブラ・ディスクhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8D%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF
まとめ
いかがでしたか?
予想外に好天の続いた7月ですが、皆様星空は堪能できましたでしょうか^^今年の夏は大きなイベントこそ少ないですが、この好天が8月も継続するなら、天文ファンにとってはこの10年で最高レベルの夏になるかもしれませんね!
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、今月5日は天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14110_hoshinavi
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
編集部山口
千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフOriginal
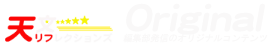

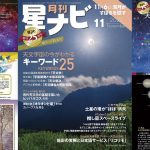


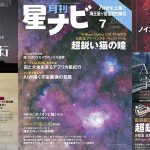

コメントを残す