星ナビ2025年6月号ご紹介
アストロアーツHPで星ナビ2025年6月号の内容が告知されています。発売は5月2日 金曜日です。
目次
今月の内容は!?
特集は星空の全情景を記録できる「星景リアルタイム動画」。プラネタリウムの始まりの街を巡る「プラネ三都物語」はプラネ100周年のフィナーレにピッタリ。
星ナビ6月号は「星空リアルタイム動画」と「プラネ三都物語」
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14007_hoshinavi
■表紙
今月の表紙は前田徳彦さん撮影の「星空への道標」。薄明の時間に青く変化する空と、消えゆくいて座の天の川を「星景リアルタイム動画」手法で撮影しているようすです。
今月の表紙は本誌記事で「星景リアルタイム動画」の記事を執筆された前田徳彦さんの撮影。ジンバルに搭載されたカメラの撮影風景が天文雑誌の表紙を飾るのは、筆者の記憶では初めて。
リアルタイム動画はタイムラプス動画と比較して圧倒的に光不足になる弱点はありますが、タイムラプス動画とは全く異なる世界を描き出すことが可能な手法です。ぜひ本誌記事と合わせてお読みください!
■高感度ミラーレスで光と音を録る 星空リアルタイム動画(文・写真・動画/前田徳彦)
星空がきれいに見える場所での情景を捉える方法には、星景写真やタイムラプス動画(5月号で紹介)、星景リアルタイム動画があります。今回紹介する「星景リアルタイム動画」は、星空を包みこむ全情景とその場の音までも記録することができる方法です。星景リアルタイム動画を録り続けてきた前田徳彦さんが経験をもとに解説します。
スチル写真(静止画)から始まった星空風景の撮影ですが、デジタル化で「タイムラプス動画」という手法が生まれました。そしてカメラの高感度化によって、星空を通常の動画と同じフレームレート(>15fps)で撮影することが可能になりました。本記事ではその「星景リアルタイム動画」の解説です。
LitLink 前田徳彦(starwalker0202)
https://lit.link/starwalker0202
記事を執筆された前田徳彦さんは7年近く「星景リアルタイム動画」に取り組んでいらっしゃいます。「圧倒的な光不足」をどうやってカバーするか、ジンバルやスライダーなどの機材の使いこなし方、タイムラプス動画との比較と使い分け、リアルタイム動画ならではの「音」の生かし方など、豊富な経験に基づいた入門者にもわかりやすい解説になっています。
特に、AIを活用したBGMの生成にも注目。音楽家でなくてもユーザーの立場で音楽を作れてしまうのはスゴいですね!
星ナビ6月号「星景リアルタイム」解説と作例動画を公開
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13996_realtimevideo
こちらの記事では、本記事に掲載された作例動画が紹介されています。ぜひ合わせてお読みください!
■Deepな天体写真 CMOSカメラのノイズ研究1 ノイズの種類とその原因の究明(解説/あぷらなーと)
星雲や銀河などの淡い天体の撮影は、天体写真の中でも非常に人気の高いジャンルです。デジタル技術の発展とともに主流となった「天体用CMOSカメラ」によって、撮影の難易度は飛躍的に下がりました。それでも、さまざまな種類のノイズが美しい作品作りを阻害します。今回は各種ノイズとその発生原因をまとめて紹介します。
あぷらなーと
https://apranat.exblog.jp/
「四国出身の邪悪なアマチュア天文家」あぷらなーと氏。5年ほど前からアマチュア天体写真界隈にさまざまなインパクトを与えてこられてきたことは、すでに天リフ読者は皆ご存じでしょう。氏の顔には主に2つの側面があります。ひとつは「邪悪な多連装(主にアクロマート)」に代表される「普通はやらねえよなー」的なセットアップと使いこなし。
一方で、氏のもう一つの側面は、緻密で徹底した検証によって、本来難しいことを誰にでもわかりやすく解説するという数々の仕事です。今回の記事はこちらサイドの内容。氏のライフワークのひとつである「天体用CMOSカメラ」のノイズ分析です。これまでブログやセミナーで発表されてきたことの総決算ともいえる内容。天体写真ファンは必見です。
詳細は本記事をお読みいただくとして、天リフ編集長が強調しておきたいのは、多くの人が何度も繰り返し目にしてきた「(露出不足の)天体写真のノイズ」の多くの部分は「カメラのせい」ではなく「自然現象」だったということです。「光子ショットノイズ」と呼ばれるこの概念(*)を、日本のアマチュア天文界に浸透させたことは、氏の最も大きな業績の1つだといえるでしょう。
(*)光子ショットノイズという現象は、まさに「光の粒子性」を可視化したもの。これを科学の市民化と呼ばずして何と呼びましょうや?
■プラネタリウムは終わらない 100周年フィナーレ!そして国際大会2026へ(紹介/井上 毅・田部一志)
ドイツの街に近代的なプラネタリウムが生まれてから1世紀。2023年10月に始まった「プラネタリウム100周年」もいよいよクライマックス。世界をつなぐフィナーレ・イベントで盛り上がるとともに、2026年に福岡で開かれる国際大会、そして次の100年に向けて踏み出しましょう。
「プラネタリウム100周年」に関する2つの事業の紹介記事です。詳細は記事を読んでいただきたいのですが、読者の皆様が見逃さないように以下箇条書きでご紹介します。
●国際プラネタリウム協会・オンライン記念行事・世界各地のプラネタリウムを結んだ中継が実施。日本からは明石市立天文科学館のプラネタリウムが中継会場。日本時間5月8日AM3:00〜、YouTubeライブ配信あり
●全国一斉プラネタリウム100周年フィナーレ・イベント・全国30以上のプラネタリウム館をオンラインで結ぶ。「全国リレー解説」も。YouTubeライブ配信あり
【終了しました】全国一斉プラネタリウム100周年フィナーレイベント(明石会場)
●2026年の「国際プラネタリウム協会(IPS)」総会が福岡で開催。日本のプラネタリウム関係者が大会に参加しやすくするために(*)、お近くのプラネタリウムで「ここのプラネタリウムは来年福岡で開かれるIPS大会に人を派遣するんですよね?」と聞いてみよう!
(*)出張予算を取りやすくするために「すごく重要なイベントが開催される」ことを刷り込むのが目的です^^
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・モンゴル「星空」ゲル・キャンプツアー
毎年(コロナ期を除く)実施されている、星ナビ協賛の「星空ツアー」です。天リフ編集長は2019年と2023年に星空アドバイザーとして参加しましたが(*)、最高の星空だけでなく、モンゴルという国と文化、自然に触れる素晴らしい体験でした。記載されている日程外でも、2名以上なら好みのスケジュールでアレンジできるそうです。
(*)今年も天リフ編集長は「星空アドバイザー」の一覧に記載されているようですが、今のところツアー参加の予定はありません^^;;
ワイルド・ナビゲーション
http://www.wild-navi.co.jp/
【連載・星旅リフレクションズ(2)】モンゴル・ゲルキャンプ星空ツアー
■NewsWatch 天文宇宙施設に小学生探偵
4月18日から公開されている映画「劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像(せきがんのフラッシュバック)」。国立天文台野辺山が舞台ということで、来場者が激増するなど、すでに天文界隈では盛り上がりを見せています。
劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像
https://www.conan-movie.jp/2025/
いずれにしても「野辺山」は日本の天文界隈の聖地。ぜひこの機会に、映画もリアルも合言葉は「ノベヤマ!」
――――――
📡お知らせ📡
――――――
バス案内🚎
・🚃野辺山駅 ↔︎ 📡天文台 (毎日)
・🚗臨時駐車場 ↔︎ 📡天文台 (休日のみ)
(平日は天文台駐車場が利用可)https://t.co/jIxfFjduT3
応援のお願い📡
・寄付 https://t.co/L7HXeYm4O1
・広告 https://t.co/vFE55gBJ1J pic.twitter.com/EOFf5Lf0BB — 国立天文台野辺山 (@NAOJ_Nobeyama) April 21, 2025
【連載・宇宙県の旅】第1回・野辺山宇宙電波観測所【ときどきナガノ】
■星ナビギャラリー
今回のトップ下は荒井俊也さんの「ガム星雲全景」。28mmカメラレンズにAPS-Cサイズの天体用CMOSカメラで総露光200分。ブロードバンドとデュアルナローの露光比率1:1の撮影で、赤い星雲だけでなく超新星残骸のOIIIのフィラメント構造もしっかり描出されているのが渋い。さすが、名手のリザルト。
個人的イチオシは南克樹さんの「開幕」。30秒1枚撮りですが、彩度を大幅に下げて暖色系に仕上げた色表現、後ろ姿でありながら「(夏の銀河シーズンの)開幕」のワクワク感の伝わる人物の「表情」、対角魚眼レンズの特徴をうまく使った作画(*)など、非常に緻密に構成された作品。
(*)使用しているシグマ15mmF1.4対角魚眼は解放でも使える画質ですが、人物のボケコントロールのためにF3.5で撮影されています。その上で赤道儀で追尾撮影し星を精細に撮るなど、実に緻密ですね。灯台の光芒の形も狙って絞られたのでしょう。
ネットよ今夜もありがとう〜しなの星空散歩会きらきら
今月は長野市立博物館の星空観望会参加者から誕生した「しなの星空散歩会きらきら(会長:是枝敦子さん)」。1992年の設立だそうです。このコーナーは個人のHPやブログがこれまで多かったのですが、最近は同好会・サークルのHPやSNSコミュニティも多く見かけるようになりましたね^^
しなの星空散歩会きらきら
https://www.facebook.com/p/%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%AE%E6%98%9F%E7%A9%BA%E6%95%A3%E6%AD%A9%E4%BC%9A-%E3%81%8D%E3%82%89%E3%81%8D%E3%82%89-100070858605259/
上のリンクは「しなの星空散歩会きらきら」のFacebookページですが、メンバーから寄せられた情報を元に主に管理者が投稿する運用のようです。同好会の活動として、こういうスタイルもありですね!
■天文外史 お江戸の夜空に星が舞う 浮絵に描かれた月と星(解説/塚田 健)
江戸時代に大きく発展し、西洋の画家にも大きなインスピレーションを与えた浮世絵。美人画や役者絵が有名ですが、その中でも“星空”は描かれてきました。浮世絵を皮切りに「描かれた月と星」を探ってみましょう。
今回のテーマは「浮世絵に描かれた月と星」。NHK大河ドラマ「べらぼう」で主人公の「蔦重」が版元として多くの浮世絵を世に送り出したことにちなんだ設定と思われます。
本記事では浮世絵で多く描かれていた「月」と、あまり描かれなかった「空」や「星」について、さまざまな作品を引用・検証しながら日本人の自然観に迫ります。
浮世絵を敬愛していたというゴッホの「ローヌ川の星月夜」も引用されています。本誌ではモノクロですが、Wikipediaにカラー画像があったので引用させていただきました。

■ 星の街道をゆく プラネ三都物語(紀行/中山満仁)
各地に点在するプラネタリウムをめぐるシリーズ。今回の旅ではプラネタリウムが生まれた街・イエナ、歴史の渦中にあったベルリン、そして現代も最先端を走るハンブルク、3つの街に出かけました。
プラネタリウムをめぐる旅シリーズ、今回はドイツ編。鉄分は今回はやや控えめですが、プラネタリウム愛は変わらず120%です。
「宇宙を実感できる」ことで、多くの人に人間と宇宙の存在の尊厳を伝えることのできるプラネタリウムですが、ドイツを巡る旅では「戦争」の歴史を実感されたようです。「プラネタリウムを通じて平和を訴える使命がある」という認識を再確認された、中山さんの旅はまだまだ続きます!
まとめ
いかがでしたか?
天文趣味の最大のジャンルの1つである「天体写真」は、デジタル技術の進歩によって画像処理技術や動画など大きく広がってきています。そういった進化を「星空の楽しみ」を広げていく方向で、ぜひ生かしていきたいものですね!
意外だったのは、現代よりもはるかに星がよく見えたであろう江戸時代において、浮世絵の「星空」の描写がいまひとつ豊かではなかったこと。文化の豊かさは、現実の対象の豊かさだけで決まるのではないということでしょうか。これは逆に、現代が美しい星空の多くが失われた時代であったとしても「星を見る」カルチャーを育み発展させることができることを意味しているのかもしれません。その成果の結実のひとつが「プラネタリウム」であるといえるでしょう。
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、毎月5日は天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ6月号は「星空リアルタイム動画」と「プラネ三都物語」
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14007_hoshinavi
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
https://reflexions.jp/tenref/orig/2025/05/04/17907/https://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2025/05/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-1024x538.jpghttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2025/05/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-150x150.jpg雑誌・書籍星ナビアストロアーツHPで星ナビ2025年6月号の内容が告知されています。発売は5月2日 金曜日です。
今月の内容は!?
特集は星空の全情景を記録できる「星景リアルタイム動画」。プラネタリウムの始まりの街を巡る「プラネ三都物語」はプラネ100周年のフィナーレにピッタリ。
星ナビ6月号は「星空リアルタイム動画」と「プラネ三都物語」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14007_hoshinavi
■表紙
今月の表紙は本誌記事で「星景リアルタイム動画」の記事を執筆された前田徳彦さんの撮影。ジンバルに搭載されたカメラの撮影風景が天文雑誌の表紙を飾るのは、筆者の記憶では初めて。
リアルタイム動画はタイムラプス動画と比較して圧倒的に光不足になる弱点はありますが、タイムラプス動画とは全く異なる世界を描き出すことが可能な手法です。ぜひ本誌記事と合わせてお読みください!
■高感度ミラーレスで光と音を録る 星空リアルタイム動画(文・写真・動画/前田徳彦)
スチル写真(静止画)から始まった星空風景の撮影ですが、デジタル化で「タイムラプス動画」という手法が生まれました。そしてカメラの高感度化によって、星空を通常の動画と同じフレームレート(>15fps)で撮影することが可能になりました。本記事ではその「星景リアルタイム動画」の解説です。
LitLink 前田徳彦(starwalker0202)https://lit.link/starwalker0202
記事を執筆された前田徳彦さんは7年近く「星景リアルタイム動画」に取り組んでいらっしゃいます。「圧倒的な光不足」をどうやってカバーするか、ジンバルやスライダーなどの機材の使いこなし方、タイムラプス動画との比較と使い分け、リアルタイム動画ならではの「音」の生かし方など、豊富な経験に基づいた入門者にもわかりやすい解説になっています。
特に、AIを活用したBGMの生成にも注目。音楽家でなくてもユーザーの立場で音楽を作れてしまうのはスゴいですね!
星ナビ6月号「星景リアルタイム」解説と作例動画を公開https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/13996_realtimevideo
こちらの記事では、本記事に掲載された作例動画が紹介されています。ぜひ合わせてお読みください!
■Deepな天体写真 CMOSカメラのノイズ研究1 ノイズの種類とその原因の究明(解説/あぷらなーと)
あぷらなーとhttps://apranat.exblog.jp/
「四国出身の邪悪なアマチュア天文家」あぷらなーと氏。5年ほど前からアマチュア天体写真界隈にさまざまなインパクトを与えてこられてきたことは、すでに天リフ読者は皆ご存じでしょう。氏の顔には主に2つの側面があります。ひとつは「邪悪な多連装(主にアクロマート)」に代表される「普通はやらねえよなー」的なセットアップと使いこなし。
一方で、氏のもう一つの側面は、緻密で徹底した検証によって、本来難しいことを誰にでもわかりやすく解説するという数々の仕事です。今回の記事はこちらサイドの内容。氏のライフワークのひとつである「天体用CMOSカメラ」のノイズ分析です。これまでブログやセミナーで発表されてきたことの総決算ともいえる内容。天体写真ファンは必見です。
詳細は本記事をお読みいただくとして、天リフ編集長が強調しておきたいのは、多くの人が何度も繰り返し目にしてきた「(露出不足の)天体写真のノイズ」の多くの部分は「カメラのせい」ではなく「自然現象」だったということです。「光子ショットノイズ」と呼ばれるこの概念(*)を、日本のアマチュア天文界に浸透させたことは、氏の最も大きな業績の1つだといえるでしょう。
(*)光子ショットノイズという現象は、まさに「光の粒子性」を可視化したもの。これを科学の市民化と呼ばずして何と呼びましょうや?
■プラネタリウムは終わらない 100周年フィナーレ!そして国際大会2026へ(紹介/井上 毅・田部一志)
「プラネタリウム100周年」に関する2つの事業の紹介記事です。詳細は記事を読んでいただきたいのですが、読者の皆様が見逃さないように以下箇条書きでご紹介します。
●国際プラネタリウム協会・オンライン記念行事・世界各地のプラネタリウムを結んだ中継が実施。日本からは明石市立天文科学館のプラネタリウムが中継会場。日本時間5月8日AM3:00〜、YouTubeライブ配信あり
●全国一斉プラネタリウム100周年フィナーレ・イベント・全国30以上のプラネタリウム館をオンラインで結ぶ。「全国リレー解説」も。YouTubeライブ配信あり
https://www.am12.jp/topics/pla100th-finale_akashi/
●2026年の「国際プラネタリウム協会(IPS)」総会が福岡で開催。日本のプラネタリウム関係者が大会に参加しやすくするために(*)、お近くのプラネタリウムで「ここのプラネタリウムは来年福岡で開かれるIPS大会に人を派遣するんですよね?」と聞いてみよう!
(*)出張予算を取りやすくするために「すごく重要なイベントが開催される」ことを刷り込むのが目的です^^
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・モンゴル「星空」ゲル・キャンプツアー
毎年(コロナ期を除く)実施されている、星ナビ協賛の「星空ツアー」です。天リフ編集長は2019年と2023年に星空アドバイザーとして参加しましたが(*)、最高の星空だけでなく、モンゴルという国と文化、自然に触れる素晴らしい体験でした。記載されている日程外でも、2名以上なら好みのスケジュールでアレンジできるそうです。
(*)今年も天リフ編集長は「星空アドバイザー」の一覧に記載されているようですが、今のところツアー参加の予定はありません^^;;
ワイルド・ナビゲーションhttp://www.wild-navi.co.jp/
https://reflexions.jp/tenref/navi/enjoy/hoshitani/10362/
■NewsWatch 天文宇宙施設に小学生探偵
4月18日から公開されている映画「劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像(せきがんのフラッシュバック)」。国立天文台野辺山が舞台ということで、来場者が激増するなど、すでに天文界隈では盛り上がりを見せています。
劇場版 名探偵コナン 隻眼の残像https://www.conan-movie.jp/2025/
いずれにしても「野辺山」は日本の天文界隈の聖地。ぜひこの機会に、映画もリアルも合言葉は「ノベヤマ!」
――――――📡お知らせ📡――――――バス案内🚎・🚃野辺山駅 ↔︎ 📡天文台 (毎日)・🚗臨時駐車場 ↔︎ 📡天文台 (休日のみ)(平日は天文台駐車場が利用可)https://t.co/jIxfFjduT3応援のお願い📡・寄付 https://t.co/L7HXeYm4O1・広告 https://t.co/vFE55gBJ1J pic.twitter.com/EOFf5Lf0BB
— 国立天文台野辺山 (@NAOJ_Nobeyama) April 21, 2025
https://reflexions.jp/tenref/orig/2017/11/06/2590/
■星ナビギャラリー
今回のトップ下は荒井俊也さんの「ガム星雲全景」。28mmカメラレンズにAPS-Cサイズの天体用CMOSカメラで総露光200分。ブロードバンドとデュアルナローの露光比率1:1の撮影で、赤い星雲だけでなく超新星残骸のOIIIのフィラメント構造もしっかり描出されているのが渋い。さすが、名手のリザルト。
個人的イチオシは南克樹さんの「開幕」。30秒1枚撮りですが、彩度を大幅に下げて暖色系に仕上げた色表現、後ろ姿でありながら「(夏の銀河シーズンの)開幕」のワクワク感の伝わる人物の「表情」、対角魚眼レンズの特徴をうまく使った作画(*)など、非常に緻密に構成された作品。
(*)使用しているシグマ15mmF1.4対角魚眼は解放でも使える画質ですが、人物のボケコントロールのためにF3.5で撮影されています。その上で赤道儀で追尾撮影し星を精細に撮るなど、実に緻密ですね。灯台の光芒の形も狙って絞られたのでしょう。
ネットよ今夜もありがとう〜しなの星空散歩会きらきら
今月は長野市立博物館の星空観望会参加者から誕生した「しなの星空散歩会きらきら(会長:是枝敦子さん)」。1992年の設立だそうです。このコーナーは個人のHPやブログがこれまで多かったのですが、最近は同好会・サークルのHPやSNSコミュニティも多く見かけるようになりましたね^^
しなの星空散歩会きらきらhttps://www.facebook.com/p/%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%AE%E6%98%9F%E7%A9%BA%E6%95%A3%E6%AD%A9%E4%BC%9A-%E3%81%8D%E3%82%89%E3%81%8D%E3%82%89-100070858605259/
上のリンクは「しなの星空散歩会きらきら」のFacebookページですが、メンバーから寄せられた情報を元に主に管理者が投稿する運用のようです。同好会の活動として、こういうスタイルもありですね!
■天文外史 お江戸の夜空に星が舞う 浮絵に描かれた月と星(解説/塚田 健)
今回のテーマは「浮世絵に描かれた月と星」。NHK大河ドラマ「べらぼう」で主人公の「蔦重」が版元として多くの浮世絵を世に送り出したことにちなんだ設定と思われます。
本記事では浮世絵で多く描かれていた「月」と、あまり描かれなかった「空」や「星」について、さまざまな作品を引用・検証しながら日本人の自然観に迫ります。
浮世絵を敬愛していたというゴッホの「ローヌ川の星月夜」も引用されています。本誌ではモノクロですが、Wikipediaにカラー画像があったので引用させていただきました。
■ 星の街道をゆく プラネ三都物語(紀行/中山満仁)
プラネタリウムをめぐる旅シリーズ、今回はドイツ編。鉄分は今回はやや控えめですが、プラネタリウム愛は変わらず120%です。
「宇宙を実感できる」ことで、多くの人に人間と宇宙の存在の尊厳を伝えることのできるプラネタリウムですが、ドイツを巡る旅では「戦争」の歴史を実感されたようです。「プラネタリウムを通じて平和を訴える使命がある」という認識を再確認された、中山さんの旅はまだまだ続きます!
まとめ
いかがでしたか?
天文趣味の最大のジャンルの1つである「天体写真」は、デジタル技術の進歩によって画像処理技術や動画など大きく広がってきています。そういった進化を「星空の楽しみ」を広げていく方向で、ぜひ生かしていきたいものですね!
意外だったのは、現代よりもはるかに星がよく見えたであろう江戸時代において、浮世絵の「星空」の描写がいまひとつ豊かではなかったこと。文化の豊かさは、現実の対象の豊かさだけで決まるのではないということでしょうか。これは逆に、現代が美しい星空の多くが失われた時代であったとしても「星を見る」カルチャーを育み発展させることができることを意味しているのかもしれません。その成果の結実のひとつが「プラネタリウム」であるといえるでしょう。
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、毎月5日は天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ6月号は「星空リアルタイム動画」と「プラネ三都物語」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14007_hoshinavi
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
編集部山口
千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフOriginal
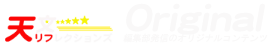

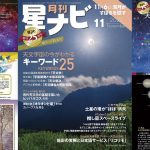



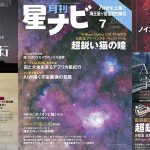
コメントを残す