星ナビ2025年11月号ご紹介
アストロアーツHPで星ナビ2025年11月号の内容が告知されています。発売は10月3日 金曜日です。
目次
今月の内容は!?
「星ナビ」は今月号で通巻300号。今月は32ページ増の特別号です。特集は25周年記念特集「天文宇宙の今がわかるキーワード25」。
星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14178_hoshinavi
■表紙
今回の表紙は飯島 裕さん撮影の「復円途上の赤い月と星空」。9月8日に起こった皆既月食の写真です。長野県の野辺山高原での撮影で、皆既食終わりの赤い月に光が戻るわずかな時間をとらえています。
今月の表紙は9/8の皆既月食。皆既月食の最大の魅力は、満月から皆既・そして満月に戻るまでの「月夜から闇、闇から月夜への緩やかな、そして劇的な変化」にあります。この作品はその中の「部分月食」のタイミングにスポットを当て、白く輝く月の光と赤く照らされた「地球の影」を、多段階合成で地上の風景とともに表現。
撮影された飯島裕さんは、本号掲載の連載記事「銀ノ星 四光子の記憶」で「皆既月食は空の暗い場所で見るに限る、と思っている」と書かれています。表紙の作品にも飯島さんのこのコメントにも、天リフ編集長は強く共感するものです^^ 月食の魅力と美しさを再発見できる傑作といえるでしょう。
■創刊25周年記念特集 天文宇宙の今がわかるキーワード25(解説/佐野栄俊・中野太郎・塚田 健・川村 晶)
「星ナビ」がこの2025年11月号で通巻300号。読者の皆さんや本誌を支えてくださる皆様のおかげで300号を迎えることができました。「天文学」「宇宙開発-太陽系探査」「天文普及」「天文機材と天体写真」の4分野・25のキーワードを通して、天文宇宙の“今”を見ていきましょう。
星ナビの創刊25周年特集、なんと30ページ(*)の超大型企画。天文宇宙界隈の「いま」を、幅広いジャンルとトピックから鋭く切り出した大作。このような情報発信は「専門系総合雑誌」でしかあり得ないでしょう。この記事だけのために本号をお買い上げになられても、決して損することはありません。ぜひこの先の25年もこの手の企画を継続してほしいものです^^
(*)天リフが星ナビ様の紹介記事を書くようになって以来では飛び抜けて最大です。
本記事では拙「天リフ」も「天文普及/天文宇宙系YouTuber & VTuber枠」で取り上げていただいています。苦節9年、天リフも「天文普及枠」に入れていただいたのかと思うと感無量。星ナビ50周年、天リフ34周年の際には、今度は天リフが「星ナビ50周年」を祝う特別企画をお届けすることをここに約束させていただきます^^
■Deepな天体写真 リモート天文台活用2 リモート天文台撮影の実際(解説/蒔田 剛)
シーイングの良い場所にある望遠鏡を自宅から操作するリモート撮影。海外のリモート天文台で撮影するサービスや、天体撮影サービス「リコリモ」が登場し、リモート天文台を活用した天文撮影がぐっと身近になりました。これらのサービスを比較しつつ、実際の撮影オペレーションを具体的に解説していきます。
連載第二回目。今回は蒔田さんが主に使用されているiTelescope社のサービスを、料金プランから画面操作・撮影データの取得、悪条件時の返金システムまで詳しく解説。日本のリコー社が運営する「リコリモ」との違いについても詳細に比較されていて、時間貸しリモート望遠鏡の利用を検討されている方には大いに参考になることでしょう。
さらに、「リコリモ」プロジェクト中の人が執筆の紹介記事も3ページ。プロジェクト立ち上げのきっかけ・現在のサービスに至るまでの経緯、そして「宇宙の美しさをもっと多くの人に届けたい」という思いが熱く語られています。
【TASC-onリコリモ】日本初のリザルトシェア型天体撮影サービス始めます。
「リコリモ」といえば天リフの「リザルトシェア」がなんと始動目前となりました。若干開始が遅れていますが、まもなく今後の詳細をアナウンスさせていただける見込みです。こちらもお楽しみに!
観測最高条件 2025年はこれが本命! 土星の環の準消失現象(解説/早水 勉)

わずか3秒角。2025年11月24日、土星の環が「準消失」となります。土星の環が「完全に消失して見える」のは、「環に太陽の光が真横から射し込むとき」と「地球からみた土星の環が真横になる(傾きが0°になる)とき」の2つの種類がありますが、11月24日の「準消失」は後者で、地球に対する環の傾きはわずか0.45°、見かけの土星の「厚み」は3秒角になります。
早水さんが今年5月7日に前者の消失を観測されたときは、土星面を横切る環が暗線となって見られたそうです。計算上は見かけの厚みはわずか0.33秒角で望遠鏡の理論解像度を下回っていたにもかかわらず暗線が視認されたということは、3秒角の厚みの今回の「準消失」は視認できるのか?それともできないのか?とにもかくにも、ぜひご自身の眼で確認してみてくださいね!
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・Sky-Watcher Hα太陽望遠鏡
黒点活動の極大期を迎えている太陽、今「Hα太陽望遠鏡」が熱い!Sky-Watcherが相次いで市場に投入した2台の太陽望遠鏡の広告です。
天リフ編集長はこの望遠鏡を実視しましたが、一言でいって「素晴らしく良く見える!」ものでした。特に低価格モデルの「フェニックス」は「Hα太陽望遠鏡」のエントリモデルでありながら、まったく不満のない見え味で、人差し指の押下を思いとどまるのに必死・・・^^;
黒点活動の極大期はまさに今!お買い上げになるなら、お早めに!
シュミット ・ACUTER OPTICS Hα太陽望遠鏡 フェニックス
https://www.syumitto.jp/SHOP/1140243/1172429/list.html
シュミット・Sky-Watcher 太陽望遠鏡 ヘリオスター76Hα
https://www.syumitto.jp/SHOP/SWB02032.html
■KAGAYA通信 Vol 506(presented by KAGAYA Studio)
星ナビは創刊25周年。その記念すべき号の「KAGAYA通信」です。まず「ん??」となったのは「Vol 506」の文字。25周年なら最大でもVol 300のはずなのに、、、記事を読んでなるほど!KAGAYAさんは81歳になられた(*)のですね^^
(*)という設定。創刊50周年記念号への寄稿、という形になっています^^
根っからのKAGAYAファンの天リフ編集長的には、25年後のKAGAYA通信を、87歳までの生きる目標とさせていただきます^^
■星ナビギャラリー
今月号は創刊25周年ということで、なんと「増ページスペシャル」。初掲載・掲載2回目までの方限定のギャラリーが追加に!今回の独断ピックアップはこちらからさせていただきます。
個人的イチオシは初掲載・前田恵里奈さんの「天の川を紡ぐ」。iPhone14を三脚に固定しての自撮り撮影と思われますが、「スマホだから掲載された」のではなく、作品としての評価によるものでしょう。もはやカメラに性能面での優劣で序列を付ける時代は終わったことをしみじみと感じる作品。
もうひとつのイチオシは石原啓司さんの「IC1396A 象の鼻星雲」。自前望遠鏡共同設置型の「南紀なんちゃってリモートビレッジ」による撮影で、総露光は10時間12分。もはや掲載回数でビギナー・ベテランが棲み分けられる時代もまた終わった、としみじみ感じる作品です。
■ネットよ今夜もありがとう
今月は、天文VTuberの筆頭格の星見まどかさん。紹介元は星見まどかさんが特別客員研究員を務める野辺山宇宙電波観測所の西村淳所長。
星見まどかの宇宙情報室
https://www.youtube.com/@Madoka_Hoshimi
星見まどかさんとそのご活躍については、本欄で当方が語るよりも、まず上記リンクをクリックして、面白そうな動画をまずご視聴いただくのが一番です。そして面白かったと思ったらぜひ「高評価」ボタンを。そして清きチャンネル登録をぜひ!
■宇宙を深掘り!V宙部 VTuberたちが宇宙へ! 推し宙スペースライブ(紹介/宇推くりあ)
VTuberたちをISSの「きぼう」実験棟に送る「推し宙スペースライブ」がついに打ち上げ。「コマンダー」を務める宇推くりあさんが紹介。 ぬいぐるみとアクリルグッズの姿で、総勢43名のVTuberたちが宇宙を目指します。
打ち上げ予定は10月25日。総勢43名のVTuberが(*)、種子島宇宙センターから打ち上げられるH3ロケット7号機に乗って、ISS国際宇宙ステーション「きぼう」に向かいます。
(*)もちろんVTuberは現実空間の存在ではないので「ぬいぐるみ」や「アクリルグッズ」の形で搭載されます。前出の星見まどかさんや星ナビで記事を書かれた猫谷ここなさんも参加VTuberです。
本記事はそのプロジェクトで「コマンダー」を務める宇推くりあさんのご執筆。プロジェクト「推し宙スペースライブ」のご紹介です。ISSの「きぼう」日本実験棟の船内からリアルタイムでライブ配信を行ったり、VTuberの分身ともいえるぬいぐるみやアクリルパネルの写真撮影をされるそうです。
このライブ配信、ちょっと見てみたくなりませんか?!
推し宙プロジェクト
https://oshisora.jp/
■ アテナイの学堂 古代ギリシアの天文学者ヒッパルコス後編(ナビゲーター/早水 勉)
天文愛好家なら一度はその名前を耳にしたことのあるヒッパルコス。天文学、数学、地理学に才能を発揮し、星表の作成、等級システムの考案、歳差の発見といった偉大な業績を残したヒッパルコスを、前編に続いて追いかけてみましょう。
「エーゲ海の風」の早水さんの連載第二回目、「ヒッパルコス」の後編。前編ではヒッパルコスのエキセントリックさが目立ちましたが^^;; 後編では「(世界最初の)星表」「恒星の等級システム」「歳差の発見」「恒星の固有運動の仮説」「太陽と月の大きさと距離の測定」「三角関数表」など、ヒッパルコスの業績の偉大な業績の数々が解説されています。
これまでの蓄積が何もない自然科学の黎明期において、このような業績を成し遂げたことはすごいことですが、個人的には「面白くてたまらなかっただろうな」との感想を持ちました。
もちろん研究に必要なさまざまな分野の前提知識がない中では、「真理」にたどり着けなかったり、間違った結論を出してしまうこともあるでしょう。でも、そこにはリアルな「未知の謎を科学的探究心と地道な観測を武器に解き明かしていく過程」があります。それを追体験できるのが、本連載の魅力ではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?
星ナビ25周年、天リフも来年3月で9周年。双方が「ご在命(^^);;」である限り、この差を追い越すことは永遠に不可能なのですが、「継続する」ことの重みをあらためて実感し始めた今日この頃であります。読者のみなさまにおかれましても、今後もご健勝で「N+1周年」が末永く継続されることを願って止みません。
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、今月は3日の天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14178_hoshinavi
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
https://reflexions.jp/tenref/orig/2025/10/04/18265/https://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2025/10/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-1024x529.jpghttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2025/10/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-150x150.jpg雑誌・書籍星ナビアストロアーツHPで星ナビ2025年11月号の内容が告知されています。発売は10月3日 金曜日です。
今月の内容は!?
「星ナビ」は今月号で通巻300号。今月は32ページ増の特別号です。特集は25周年記念特集「天文宇宙の今がわかるキーワード25」。
星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14178_hoshinavi
■表紙
今月の表紙は9/8の皆既月食。皆既月食の最大の魅力は、満月から皆既・そして満月に戻るまでの「月夜から闇、闇から月夜への緩やかな、そして劇的な変化」にあります。この作品はその中の「部分月食」のタイミングにスポットを当て、白く輝く月の光と赤く照らされた「地球の影」を、多段階合成で地上の風景とともに表現。
撮影された飯島裕さんは、本号掲載の連載記事「銀ノ星 四光子の記憶」で「皆既月食は空の暗い場所で見るに限る、と思っている」と書かれています。表紙の作品にも飯島さんのこのコメントにも、天リフ編集長は強く共感するものです^^ 月食の魅力と美しさを再発見できる傑作といえるでしょう。
■創刊25周年記念特集 天文宇宙の今がわかるキーワード25(解説/佐野栄俊・中野太郎・塚田 健・川村 晶)
星ナビの創刊25周年特集、なんと30ページ(*)の超大型企画。天文宇宙界隈の「いま」を、幅広いジャンルとトピックから鋭く切り出した大作。このような情報発信は「専門系総合雑誌」でしかあり得ないでしょう。この記事だけのために本号をお買い上げになられても、決して損することはありません。ぜひこの先の25年もこの手の企画を継続してほしいものです^^
(*)天リフが星ナビ様の紹介記事を書くようになって以来では飛び抜けて最大です。
本記事では拙「天リフ」も「天文普及/天文宇宙系YouTuber & VTuber枠」で取り上げていただいています。苦節9年、天リフも「天文普及枠」に入れていただいたのかと思うと感無量。星ナビ50周年、天リフ34周年の際には、今度は天リフが「星ナビ50周年」を祝う特別企画をお届けすることをここに約束させていただきます^^
■Deepな天体写真 リモート天文台活用2 リモート天文台撮影の実際(解説/蒔田 剛)
連載第二回目。今回は蒔田さんが主に使用されているiTelescope社のサービスを、料金プランから画面操作・撮影データの取得、悪条件時の返金システムまで詳しく解説。日本のリコー社が運営する「リコリモ」との違いについても詳細に比較されていて、時間貸しリモート望遠鏡の利用を検討されている方には大いに参考になることでしょう。
さらに、「リコリモ」プロジェクト中の人が執筆の紹介記事も3ページ。プロジェクト立ち上げのきっかけ・現在のサービスに至るまでの経緯、そして「宇宙の美しさをもっと多くの人に届けたい」という思いが熱く語られています。
https://reflexions.jp/tenref/orig/2025/09/12/18231/
「リコリモ」といえば天リフの「リザルトシェア」がなんと始動目前となりました。若干開始が遅れていますが、まもなく今後の詳細をアナウンスさせていただける見込みです。こちらもお楽しみに!
観測最高条件 2025年はこれが本命! 土星の環の準消失現象(解説/早水 勉)
わずか3秒角。2025年11月24日、土星の環が「準消失」となります。土星の環が「完全に消失して見える」のは、「環に太陽の光が真横から射し込むとき」と「地球からみた土星の環が真横になる(傾きが0°になる)とき」の2つの種類がありますが、11月24日の「準消失」は後者で、地球に対する環の傾きはわずか0.45°、見かけの土星の「厚み」は3秒角になります。
早水さんが今年5月7日に前者の消失を観測されたときは、土星面を横切る環が暗線となって見られたそうです。計算上は見かけの厚みはわずか0.33秒角で望遠鏡の理論解像度を下回っていたにもかかわらず暗線が視認されたということは、3秒角の厚みの今回の「準消失」は視認できるのか?それともできないのか?とにもかくにも、ぜひご自身の眼で確認してみてくださいね!
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・Sky-Watcher Hα太陽望遠鏡
黒点活動の極大期を迎えている太陽、今「Hα太陽望遠鏡」が熱い!Sky-Watcherが相次いで市場に投入した2台の太陽望遠鏡の広告です。
天リフ編集長はこの望遠鏡を実視しましたが、一言でいって「素晴らしく良く見える!」ものでした。特に低価格モデルの「フェニックス」は「Hα太陽望遠鏡」のエントリモデルでありながら、まったく不満のない見え味で、人差し指の押下を思いとどまるのに必死・・・^^;
黒点活動の極大期はまさに今!お買い上げになるなら、お早めに!
シュミット ・ACUTER OPTICS Hα太陽望遠鏡 フェニックスhttps://www.syumitto.jp/SHOP/1140243/1172429/list.html
シュミット・Sky-Watcher 太陽望遠鏡 ヘリオスター76Hαhttps://www.syumitto.jp/SHOP/SWB02032.html
■KAGAYA通信 Vol 506(presented by KAGAYA Studio)
星ナビは創刊25周年。その記念すべき号の「KAGAYA通信」です。まず「ん??」となったのは「Vol 506」の文字。25周年なら最大でもVol 300のはずなのに、、、記事を読んでなるほど!KAGAYAさんは81歳になられた(*)のですね^^
(*)という設定。創刊50周年記念号への寄稿、という形になっています^^
根っからのKAGAYAファンの天リフ編集長的には、25年後のKAGAYA通信を、87歳までの生きる目標とさせていただきます^^
■星ナビギャラリー
今月号は創刊25周年ということで、なんと「増ページスペシャル」。初掲載・掲載2回目までの方限定のギャラリーが追加に!今回の独断ピックアップはこちらからさせていただきます。
個人的イチオシは初掲載・前田恵里奈さんの「天の川を紡ぐ」。iPhone14を三脚に固定しての自撮り撮影と思われますが、「スマホだから掲載された」のではなく、作品としての評価によるものでしょう。もはやカメラに性能面での優劣で序列を付ける時代は終わったことをしみじみと感じる作品。
もうひとつのイチオシは石原啓司さんの「IC1396A 象の鼻星雲」。自前望遠鏡共同設置型の「南紀なんちゃってリモートビレッジ」による撮影で、総露光は10時間12分。もはや掲載回数でビギナー・ベテランが棲み分けられる時代もまた終わった、としみじみ感じる作品です。
■ネットよ今夜もありがとう
今月は、天文VTuberの筆頭格の星見まどかさん。紹介元は星見まどかさんが特別客員研究員を務める野辺山宇宙電波観測所の西村淳所長。
星見まどかの宇宙情報室https://www.youtube.com/@Madoka_Hoshimi
星見まどかさんとそのご活躍については、本欄で当方が語るよりも、まず上記リンクをクリックして、面白そうな動画をまずご視聴いただくのが一番です。そして面白かったと思ったらぜひ「高評価」ボタンを。そして清きチャンネル登録をぜひ!
■宇宙を深掘り!V宙部 VTuberたちが宇宙へ! 推し宙スペースライブ(紹介/宇推くりあ)
打ち上げ予定は10月25日。総勢43名のVTuberが(*)、種子島宇宙センターから打ち上げられるH3ロケット7号機に乗って、ISS国際宇宙ステーション「きぼう」に向かいます。
(*)もちろんVTuberは現実空間の存在ではないので「ぬいぐるみ」や「アクリルグッズ」の形で搭載されます。前出の星見まどかさんや星ナビで記事を書かれた猫谷ここなさんも参加VTuberです。
本記事はそのプロジェクトで「コマンダー」を務める宇推くりあさんのご執筆。プロジェクト「推し宙スペースライブ」のご紹介です。ISSの「きぼう」日本実験棟の船内からリアルタイムでライブ配信を行ったり、VTuberの分身ともいえるぬいぐるみやアクリルパネルの写真撮影をされるそうです。
このライブ配信、ちょっと見てみたくなりませんか?!
推し宙プロジェクトhttps://oshisora.jp/
■ アテナイの学堂 古代ギリシアの天文学者ヒッパルコス後編(ナビゲーター/早水 勉)
「エーゲ海の風」の早水さんの連載第二回目、「ヒッパルコス」の後編。前編ではヒッパルコスのエキセントリックさが目立ちましたが^^;; 後編では「(世界最初の)星表」「恒星の等級システム」「歳差の発見」「恒星の固有運動の仮説」「太陽と月の大きさと距離の測定」「三角関数表」など、ヒッパルコスの業績の偉大な業績の数々が解説されています。
これまでの蓄積が何もない自然科学の黎明期において、このような業績を成し遂げたことはすごいことですが、個人的には「面白くてたまらなかっただろうな」との感想を持ちました。
もちろん研究に必要なさまざまな分野の前提知識がない中では、「真理」にたどり着けなかったり、間違った結論を出してしまうこともあるでしょう。でも、そこにはリアルな「未知の謎を科学的探究心と地道な観測を武器に解き明かしていく過程」があります。それを追体験できるのが、本連載の魅力ではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?
星ナビ25周年、天リフも来年3月で9周年。双方が「ご在命(^^);;」である限り、この差を追い越すことは永遠に不可能なのですが、「継続する」ことの重みをあらためて実感し始めた今日この頃であります。読者のみなさまにおかれましても、今後もご健勝で「N+1周年」が末永く継続されることを願って止みません。
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、今月は3日の天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14178_hoshinavi
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
編集部山口
千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフOriginal
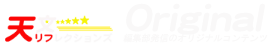




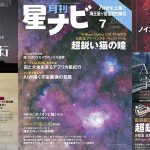

コメントを残す