星ナビ2025年12月号ご紹介
アストロアーツHPで星ナビ2025年12月号の内容が告知されています。発売は11月5日 水曜日です。
目次
今月の内容は!?
「星ナビ」は今月号で創刊25周年。皆様への感謝を込めて、望遠鏡やリモート望遠鏡利用券など豪華25アイテムをプレゼント。奮ってご応募ください。
星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14290_hoshinavi
■表紙
今回の表紙はKAGAYAさん撮影の「アイスランド一周中に出会ったオーロラ」。創刊25周年記念号らしい豪華な表紙です。撮影の旅の裏話は「KAGAYA通信」にて。
今月の表紙はKAGAYAさん撮影のアイスランドのオーロラ。ぜひ本誌「KAGAYA通信」も合わせてごらんください。
2週間の滞在中、撮影できなかったのは3日だけだそうで「念願の光景を多く撮影することができた」とのことですが、「ここで夜撮りたいと思う場所が、行く前より増えているのである」とも書かれています。これこそ、プロフェショナルとしても趣味人としても、「最高の状態」といえるのではないでしょうか。KAGAYAさんのこんな生き方と姿勢を、自分なりにぜひ見習っていきたいと感じます。
■特別付録 星空カレンダー2026
毎年恒例のカレンダーが特別付録。桜や蛍、蝉など、過去1年間の「星ナビギャラリー」掲載作から季節感あふれる9点をピックアップしました。2025年11月~2026年12月までのカレンダーなので、11月から飾って楽しめます!
毎年12月号恒例の綴じ込み付録。四季折々の星ナビギャラリー掲載作9点で構成されたカレンダーです。2025年ももうすぐ終了、2026年はどんな年になるでしょうか?!
■創刊25周年記念特集 感謝のプレゼント
「星ナビ」がこの12月号で「創刊25周年」となりました。創刊以来「星ナビ」を応援してくださった読者の皆さま、および天文趣味に関わるさまざまな団体や企業の方々のおかげです。ありがとうございます。各方面から提供いただいた25アイテムをご愛読への感謝として総計33名様にプレゼントします。綴込みのハガキやwebフォームからご応募ください。
星ナビ創刊25周年。口径30cmのドブソニアン望遠鏡からリモート望遠鏡の利用券まで、25アイテム33名に豪華賞品が当たる超大型プレゼント企画です。
なお、応募は「綴じ込みアンケートハガキ」から行いますが、電子版の方もQRコードから応募が可能です。ふるってご応募くださいね!
■Deepな天体写真 リモート天文台活用3 リモート天文台撮影の画像処理(解説/蒔田 剛)
レンタル望遠鏡での撮影では、露出時間に比例して撮影費用が嵩むため、露出不足となるのは避けられません。しかし、リモート天文台の立地条件から、露出時間がそれほど長くなくとも、高い解像度と発色の良い画像が期待できます。今回は、画像処理の全体像と画像処理、その背景にある理論概要を紹介します。
蒔田さんの「リモート天文台活用」連載の3回目。時間貸しリモート望遠鏡の宿命は「露光時間に比例して費用が増大する」こと。100時間露光するには、1時間露光の100倍の費用がかかってしまうのです。
このため、おのずと露光時間は「必要最小限」にならざるを得ず、ノイズ除去を含めた画像処理の重要度がより高くなります。本記事では、ノイズ除去に加えてエッジ強調・色彩調整などの、さまざまなテクニックが理論とともに解説されています。
【TASC-onリコリモ】日本初のリザルトシェア型天体撮影サービス始めます。
先月も少しご紹介しましたが、天リフの「リザルトシェア」サービスが期間限定で始まっています。「リザルトをシェアする」という発想で、単純な時間貸しサービスの利用よりも、はるかに高いコスパを実現しています。サービスは12月末まで。途中参加も可能ですので、ぜひご検討ください!
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・リコリモ(リコー)
なんとドカンと大きく猫谷ここなさんが!リコーのリモート天体撮影サービス「リコリモ」と、猫谷ここなさんのコラボ広告です。
こちらは星ナビとの連動企画の動画。猫谷ここなさんが「リコリモ」を使って実際に天体を撮影して画像処理も!これらの経緯は星ナビに記事を執筆されるそうなので、お楽しみに!
■編集後記
星ナビは創刊25周年。その記念すべき号の編集後記から。「余白はそれを書くには狭すぎる」は、有名な「フェルマーの最終定理」のリスペクトかと思われます。
実は、星ナビ25周年の今回をもって「星ナビ記事紹介」の連載を終了することにしました(*)。2018年6月号以来7年と7ヶ月、星ナビ本誌の25周年には遠く及びませんが、ずいぶんと長く書き続けてきたものです^^
(*)理由は天リフ全体の業務見直しの一環になります。
天リフ読者の皆様にも、感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。「狭すぎる余白」の紙メディアと「無限の余白」のWebメディア。無限の余白、無限の自由度を生かし、天リフは今後も読者の皆様の満足度向上につとめてまいりますので、今後もぜひご期待ください!
■星ナビギャラリー
今月のギャラリーは皆既月食特集と通常ギャラリーの2本立て。皆既月食特集のトップ下は行方聡さんの「山と月と旅人」。天リフ編集長の「今月のイチオシ」もこちらの作品です。行方さんのライフワークである「山岳自撮り」の会心の一枚。詳細の撮影記は以下のブログ記事をご参照ください!
山も星も 山と月と旅人
http://tukinoboru.cocolog-nifty.com/blog/2025/09/post-a56c6d.html
通常ギャラリーのトップ下は手塚昌克さんの「まばたき星雲 NGC6826」。口径122mm屈折望遠鏡で総露光はわずか1時間24分ですが、外殻の淡い部分まで描写されていて、選評では「本当に存在するのかを判断するための参照画像がない」ほどの写りのようです。
Astrobin NGC 6826 – Blinking Nebula in SHO
https://app.astrobin.com/i/xh0rie
こちらはAstrobinの画像ですが、口径40cmで総露光29時間。これと比べると、とうてい信じられないほどの写りですね!
■ネットよ今夜もありがとう
今月は、岡山県で星景写真を撮られている裕希さん。
Instagram yu_ki_7009
https://www.instagram.com/yu_ki_7009/
タイムラインにはレモン彗星や皆既月食、天の川などの星景写真、ディープスカイ天体が掲載されています。体の不自由な方向けの移動式プラネタリウムも始められたそうです。
■紫金山・アトラス彗星 解析進む大彗星(解説/小林仁美)
2024年の秋口から2025年の初頭にかけて、紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)とアトラス彗星(C/2024 G3)が話題になりました。2つの彗星が騒がれてから約1年、各所で観測成果が報告・発表されてきています。これら2つのアトラス彗星について、それぞれの特徴と最新の研究を紹介していきます。
「2024年の大彗星」紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)と、「2025年の大彗星」アトラス彗星(C/2024 G3)。いずれも天文界だけでなく、ネット界隈を巻き込んで大きな話題になりましたが、多くのプロ・アマ観測者がさまざまな観測を行った結果が、論文として発表されてきています。本記事ではそれらの概要を分かりやすく解説。
どちらの彗星も「ダストリッチ(塵成分が豊富)」な彗星でしたが、紫金山・アトラス彗星では「ネックライン構造」と呼ばれる、太陽の方向に細く長く伸びる尾が観測されていますが、これは太陽の輻射圧を受けにくい大きめの塵によるものと考えられているようです。また、偏光観測の結果ではウエスト彗星やハレー彗星と類似の結果となっているようです。
などなど、びっくりするような風変わりな結果は出ていないようですが、長期間観測が可能だった明るいこれらの2つの彗星は、彗星の研究において貴重な結果をもたらしたといえるでしょう。
■ 天文外史 「江戸天文学」ことはじめ(解説/塚田 健)
佳境を迎えつつあるNHKの大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢囃~』。舞台となっている江戸時代中期から後期は、日本の天文学においても画期となる時代でした。天文の“大衆化”がはじまったのもこの頃。蔦重の時代の日本の天文学事情を覗いてみましょう。
日本で初めて「天体望遠鏡を使った天体観望会(*)」が実施されたのは、1793年8月のことだそうです。これはNHK大河ドラマ「べらぼう」で描かれている時代とほぼ同じ。
(*)岩橋善兵衛製作の「外径8cm」の屈折望遠鏡が使用されたそうです。
本記事では、この少し前の8代将軍吉宗(在位は1716年 – 1745年)の時代から江戸後期までの間に、「限られた情報源から西洋の考えを取り入れようとした先人たちの努力」があったことがうかがえる、日本における暦や天文学の状況が解説されています。
まとめ
いかがでしたか?
星ナビ25周年、21世紀以降長く続く「出版業界冬の時代」の中、天文ガイドとともに2誌の天文雑誌が継続しているのはスゴいことですね!心から賞賛と敬意を表すものです。今後のさらなるご発展をお祈りいたします。
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、毎月5日の天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」
https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14290_hoshinavi
※本記事連載休止のお知らせ
天文リフレクションズでは2018年6月号以来、「星ナビ紹介記事」を連載してきましたが、本連載は今回をもって休止とさせていただきます。長い間、ご愛読ありがとうございました!
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
https://reflexions.jp/tenref/orig/2025/11/04/18345/https://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2025/11/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-1024x538.jpghttps://reflexions.jp/tenref/orig/wp-content/uploads/sites/4/2025/11/fc6927a4cd7fc6f068de9eb5d3ae4aff-150x150.jpg雑誌・書籍星ナビアストロアーツHPで星ナビ2025年12月号の内容が告知されています。発売は11月5日 水曜日です。
今月の内容は!?
「星ナビ」は今月号で創刊25周年。皆様への感謝を込めて、望遠鏡やリモート望遠鏡利用券など豪華25アイテムをプレゼント。奮ってご応募ください。
星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14290_hoshinavi
■表紙
今月の表紙はKAGAYAさん撮影のアイスランドのオーロラ。ぜひ本誌「KAGAYA通信」も合わせてごらんください。
2週間の滞在中、撮影できなかったのは3日だけだそうで「念願の光景を多く撮影することができた」とのことですが、「ここで夜撮りたいと思う場所が、行く前より増えているのである」とも書かれています。これこそ、プロフェショナルとしても趣味人としても、「最高の状態」といえるのではないでしょうか。KAGAYAさんのこんな生き方と姿勢を、自分なりにぜひ見習っていきたいと感じます。
■特別付録 星空カレンダー2026
毎年12月号恒例の綴じ込み付録。四季折々の星ナビギャラリー掲載作9点で構成されたカレンダーです。2025年ももうすぐ終了、2026年はどんな年になるでしょうか?!
■創刊25周年記念特集 感謝のプレゼント
星ナビ創刊25周年。口径30cmのドブソニアン望遠鏡からリモート望遠鏡の利用券まで、25アイテム33名に豪華賞品が当たる超大型プレゼント企画です。
なお、応募は「綴じ込みアンケートハガキ」から行いますが、電子版の方もQRコードから応募が可能です。ふるってご応募くださいね!
■Deepな天体写真 リモート天文台活用3 リモート天文台撮影の画像処理(解説/蒔田 剛)
蒔田さんの「リモート天文台活用」連載の3回目。時間貸しリモート望遠鏡の宿命は「露光時間に比例して費用が増大する」こと。100時間露光するには、1時間露光の100倍の費用がかかってしまうのです。
このため、おのずと露光時間は「必要最小限」にならざるを得ず、ノイズ除去を含めた画像処理の重要度がより高くなります。本記事では、ノイズ除去に加えてエッジ強調・色彩調整などの、さまざまなテクニックが理論とともに解説されています。
https://reflexions.jp/tenref/orig/2025/09/12/18231/
先月も少しご紹介しましたが、天リフの「リザルトシェア」サービスが期間限定で始まっています。「リザルトをシェアする」という発想で、単純な時間貸しサービスの利用よりも、はるかに高いコスパを実現しています。サービスは12月末まで。途中参加も可能ですので、ぜひご検討ください!
◎天リフ独断ピックアップ
■広告ピックアップ・リコリモ(リコー)
なんとドカンと大きく猫谷ここなさんが!リコーのリモート天体撮影サービス「リコリモ」と、猫谷ここなさんのコラボ広告です。
こちらは星ナビとの連動企画の動画。猫谷ここなさんが「リコリモ」を使って実際に天体を撮影して画像処理も!これらの経緯は星ナビに記事を執筆されるそうなので、お楽しみに!
■編集後記
星ナビは創刊25周年。その記念すべき号の編集後記から。「余白はそれを書くには狭すぎる」は、有名な「フェルマーの最終定理」のリスペクトかと思われます。
実は、星ナビ25周年の今回をもって「星ナビ記事紹介」の連載を終了することにしました(*)。2018年6月号以来7年と7ヶ月、星ナビ本誌の25周年には遠く及びませんが、ずいぶんと長く書き続けてきたものです^^
(*)理由は天リフ全体の業務見直しの一環になります。
天リフ読者の皆様にも、感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。「狭すぎる余白」の紙メディアと「無限の余白」のWebメディア。無限の余白、無限の自由度を生かし、天リフは今後も読者の皆様の満足度向上につとめてまいりますので、今後もぜひご期待ください!
■星ナビギャラリー
今月のギャラリーは皆既月食特集と通常ギャラリーの2本立て。皆既月食特集のトップ下は行方聡さんの「山と月と旅人」。天リフ編集長の「今月のイチオシ」もこちらの作品です。行方さんのライフワークである「山岳自撮り」の会心の一枚。詳細の撮影記は以下のブログ記事をご参照ください!
山も星も 山と月と旅人http://tukinoboru.cocolog-nifty.com/blog/2025/09/post-a56c6d.html
通常ギャラリーのトップ下は手塚昌克さんの「まばたき星雲 NGC6826」。口径122mm屈折望遠鏡で総露光はわずか1時間24分ですが、外殻の淡い部分まで描写されていて、選評では「本当に存在するのかを判断するための参照画像がない」ほどの写りのようです。
Astrobin NGC 6826 - Blinking Nebula in SHOhttps://app.astrobin.com/i/xh0rie
こちらはAstrobinの画像ですが、口径40cmで総露光29時間。これと比べると、とうてい信じられないほどの写りですね!
■ネットよ今夜もありがとう
今月は、岡山県で星景写真を撮られている裕希さん。
Instagram yu_ki_7009https://www.instagram.com/yu_ki_7009/
タイムラインにはレモン彗星や皆既月食、天の川などの星景写真、ディープスカイ天体が掲載されています。体の不自由な方向けの移動式プラネタリウムも始められたそうです。
■紫金山・アトラス彗星 解析進む大彗星(解説/小林仁美)
「2024年の大彗星」紫金山・アトラス彗星(C/2023 A3)と、「2025年の大彗星」アトラス彗星(C/2024 G3)。いずれも天文界だけでなく、ネット界隈を巻き込んで大きな話題になりましたが、多くのプロ・アマ観測者がさまざまな観測を行った結果が、論文として発表されてきています。本記事ではそれらの概要を分かりやすく解説。
どちらの彗星も「ダストリッチ(塵成分が豊富)」な彗星でしたが、紫金山・アトラス彗星では「ネックライン構造」と呼ばれる、太陽の方向に細く長く伸びる尾が観測されていますが、これは太陽の輻射圧を受けにくい大きめの塵によるものと考えられているようです。また、偏光観測の結果ではウエスト彗星やハレー彗星と類似の結果となっているようです。
などなど、びっくりするような風変わりな結果は出ていないようですが、長期間観測が可能だった明るいこれらの2つの彗星は、彗星の研究において貴重な結果をもたらしたといえるでしょう。
■ 天文外史 「江戸天文学」ことはじめ(解説/塚田 健)
日本で初めて「天体望遠鏡を使った天体観望会(*)」が実施されたのは、1793年8月のことだそうです。これはNHK大河ドラマ「べらぼう」で描かれている時代とほぼ同じ。
(*)岩橋善兵衛製作の「外径8cm」の屈折望遠鏡が使用されたそうです。
本記事では、この少し前の8代将軍吉宗(在位は1716年 - 1745年)の時代から江戸後期までの間に、「限られた情報源から西洋の考えを取り入れようとした先人たちの努力」があったことがうかがえる、日本における暦や天文学の状況が解説されています。
まとめ
いかがでしたか?
星ナビ25周年、21世紀以降長く続く「出版業界冬の時代」の中、天文ガイドとともに2誌の天文雑誌が継続しているのはスゴいことですね!心から賞賛と敬意を表すものです。今後のさらなるご発展をお祈りいたします。
そんな中でも毎日一度は天文リフレクションズ、毎月5日の天文雑誌!今月号も楽しみですね!
星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」https://www.astroarts.co.jp/article/hl/a/14290_hoshinavi
※本記事連載休止のお知らせ
天文リフレクションズでは2018年6月号以来、「星ナビ紹介記事」を連載してきましたが、本連載は今回をもって休止とさせていただきます。長い間、ご愛読ありがとうございました!
※アストロアーツ様より告知文・内容サンプル画像の転載許可をいただいています。
天文ガイドも合わせて読みたいですね!!
編集部山口
千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフOriginal
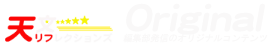
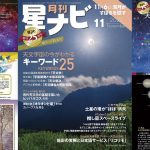



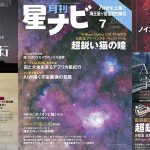

コメントを残す