【純正天体用一眼カメラ】E-M1 MarkII ASTROレビュー【OM SYSTEM】
みなさんこんにちは!
赤い星雲はお好きですか?美しい星空をカメラでとらえたいと思ったとき、あるときはアクセントとなり、またあるときはメインの被写体となるのが「赤い星雲」です。宇宙空間に漂う電離した水素ガスが発する深赤色の「Hα線」がその正体。ところが、市販されているデジタルカメラの多くでは、赤い星雲はあまり写りません。

そこで登場するのが「天体用カメラ」です。上の作例は「みんな大好き」なオリオン座の馬頭星雲ですが、この赤いモクモクがよく写るのが「天体用カメラ」の最大の特徴です。
本記事では、OMデジタルソリューションズ社から販売されている、現在唯一の「メーカー純正天体用一眼カメラ」(*)、E-M1 MarkIII ASTRO(以下記事中ではOMD ASTROと表記)について、みっちりご紹介したいと思います!
(*)2025年3月現在。
OMデジタルソリューションズ・E-M1 MarkIII ASTRO
https://jp.omsystem.com/product/astronomical/em1mk3_astro/index.html
目次
- 1 「天体用カメラ」とは?
- 2 OMD ASTRO活用シーン(1)
- 3 OM STSTEMの特徴と星空写真適性
- 4 OMD ASTRO活用シーン(2)
- 5 OMD ASTROを使いこなす
- 6 M.ZUIKO DIGITALレンズ インプレッション
- 7 どんな人に向いているか
- 8 OMD ASTROに望むこと
- 9 まとめ
- 10 補足)
「天体用カメラ」とは?
なぜ「普通のカメラ」は「赤い星雲」が写りにくいのか

上の画像は「天体用カメラ」と「ノーマルカメラ」で同じ馬頭星雲を撮影したものですが、ノーマルカメラでは赤いはずの星雲の色が「青っぽい赤(マゼンタ)」になっていますね。これは、カメラの赤のHα線の感度が低いために、星雲の青い光(*)がより優位になっているからです。
(*)馬頭星雲は同じ水素が発する別の輝線「Hβ線(波長486nm、青色)」でも発光しています。
では、なぜ「普通のカメラ(ノーマルカメラ)」では赤い星雲が写りにくいのでしょうか?その答は簡単。人間の眼はHα線のような波長の長い光の感度が低いからです。Hα線の波長は656nm。これは赤とはいっても近赤外線に近く、眼で見ると「深い赤色」に見えます。人間の眼は波長555nm付近(緑色)に感度のピークがあり、それより波長が長くなるほど感度が低下していきます。600nm付近ではけっこう感度があるのですが(これが普通の赤です)、656nmともなるとピークの1/10程度まで感度が低下してしまうのです。
参考)Wilipedia 比視感度
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E8%A6%96%E6%84%9F%E5%BA%A6
え?人間の眼とカメラと何の関係があるのかって?はい、カメラは眼で見た通りに写ってほしいですよね?そのため、民生用のデジタルカメラは「人間の眼が見た映像をできるだけ忠実に再現する」ように作られていて、「わざわざフィルターを入れて眼の特性に合わせている」のです。このため「赤い星雲」はあまり写らないのです。
赤い星雲を写すためにはどうすればいいか?

一方で、現在のデジタルカメラで使用されているCMOSセンサーは、「素のまま」では紫外線(350nm)から近赤外線(1000nm)まで広く感度があり、本来は「赤い星雲」はバッチリ写るはずなのです。そうです、赤い星雲をよく写るようにするには「わざわざ入れられたフィルター」を外せばいいのです!
簡単に丸めると「赤い星雲を写すにはフィルターを外す」なのですが、実際にはもう少し事情は複雑です。そのあたりの詳しいお話は記事末の「補足・天体用カメラの仕組み」にまとめていますので、そちらをごらんください。
理由の詳細は抜きにして、まずは「赤い星雲」を写したければ「天体用カメラ」を使えばよい。それだけご理解いただければ、ここではじゅうぶんです!
天体用カメラを入手するには
手持ちのカメラを「天体改造」する

では「赤い星雲がよく写る」天体用カメラが欲しいと思ったとき、どんな選択肢があるのでしょうか。まず、一つめは「天体改造」することです。日本にはいくつかの専門の業者(*)があり、デジタルカメラの「わざわざ入れられたフィルター」を換装することで、天体撮影に適した特性になるよう改造してもらうことができます。
(*)「ハヤタカメララボ」など、いくつかの改造業者があります。改造費用は4万円程度から。機種によってはそもそも改造することが不可能な場合もあります。個人で改造してしまう強者もいて、ヤフオクなどに出品されていることがあります。
しかし、このような「改造」はメーカーから見ると想定外。一度天体改造してしまうと、メーカーの保守サポート対象外となってしまうという弱点があります。
天体用CMOSカメラを購入する

別の選択肢として、天体撮影専用の「天体用CMOSカメラ」を購入する方法があります。このカメラは10年くらい前からディープな天文ファンを中心に急速に利用が広がってきました(*1)。しかし、まさしく「天体専用」で、液晶モニターもなければ内蔵電池やメモリカードスロットもなく、PCやスマートフォンを接続して、専用の制御ソフトウェアから使うことが前提。一般の人が気楽に手を出せるものではありません。また、星空風景の撮影には利便性が極めて低く(*2)、使用されている方はほぼいらっしゃらないと思います。
(*1)ペルチェ素子を内蔵し外気温から30〜40°低い低温に冷却することでノイズを低減することができるモデルがガチ天体写真ファンには人気です。より高品質な画像が得られるモノクロセンサーを利用できるのはこのタイプしか現状ありません。現時点で「最強のガチ天体撮影カメラ」といえるでしょう。
(*2)やってやれないことはないのですが、電源含めて制御用の機材を一緒に持ち歩く必要があります。そもそもカメラレンズを制御する機構を持たないため、絞り・ピントを全てマニュアルで制御できるレンズを使用する必要があります。
メーカー純正の「アストロモデル」を購入する

手軽に使えてメーカーのサポートも受けられるという意味では、デジタル一眼カメラのメーカー純正「アストロモデル」が一番安心です。しかし、アストロモデルは一般マーケットと比較してまだまだ市場規模が小さく、過去散発的に各社からリリースされているに過ぎない状態です(*)
(*)キヤノンの「EOS 20Da(2004年9月発売)」が最初のメーカー純正アストロモデルでした。キヤノンはその後「EOS 60Da(2012年4月発売)」「EOS Ra(2018年10月発売)」をリリースしていますが、現行品にはアストロモデルはありません。ニコンからは「D810A(2015年 5月発売)」がリリースされていますが、こちらも終売となっています。
そして2025年3月現在、唯一の現行品「アストロモデル」が、OMデジタルソリューションズの「E-M1 MarkIII ASTRO」なのです。
OMデジタルソリューションズ・E-M1 MarkIII ASTRO
https://jp.omsystem.com/product/astronomical/em1mk3_astro/index.html
OMD ASTRO活用シーン(1)
ややこしい話はここまでにして、OMD ASTROを使用した作例をごらんいただきましょう。
赤い星雲が写る星空撮影カメラとして

「赤い星雲が写る」OMD ASTROの特性は、天の川付近を撮影する際に最も発揮されます。上の画像は昇る夏の天の川をOMD ASTROで撮影したものですが、三脚固定の8秒1枚露光にもかかわらず、天の川に沿って赤い星雲が点在しているのがわかります。

こちらはノーマルモデルのE-M1 MarkIIIで撮影。別の日・別の場所ですが、レンズも露光条件も同じ。ノーマルモデルでは赤い星雲があまり赤く写っていませんね。天の川がまだ低く眠たい感じですが、赤い星雲がもっと鮮やかだったら、もう少し違った印象になるとは思いませんか?
このように、星空風景を撮影する場合、アストロモデルとノーマルモデルの一番の違いは「赤い星雲のアクセント」の有無になります。ここにこだわるのかどうかが、アストロモデルをチョイスするかどうかのひとつの分かれ道です。
もっと赤い星雲が写る・ボディマウント光害カットフィルターの活用
「赤い星雲が良く写る」OMD ASTROですが、標準で同梱される「ボディーマウント光害カットフィルター BMF-LPC01」を使用すると、さらに赤い星雲がよく写るようになります。上の画像は同一光学系で同フィルターの効果を比較したものですが、ノーマルモデルはアストロモデル並みに、アストロモデルはさらに赤い星雲が明瞭に写っていることがわかります(*)。
(*)ただし光の総量は半分くらいになってしまうため、露光時間をその分延ばさないとノイズが目立ってきます。
https://jp.omsystem.com/product/astronomical/em1mk3_astro/index.html
この「ボティマウント光害カットフィルター」はごく薄い(0.5mm程度)ガラス板に蒸着加工を施したもので、星雲の輝線はほぼ全透過する一方で、市街光に含まれる水銀やナトリウムなどの輝線をカットする仕組みです。ボディ内にフィルターを装着するため、どんなレンズでも使用できるのが特徴(*)。
(*)超広角レンズでは周辺の星像が大きく流れることがあります。詳細は「補足・ボディマウントフィルターによる星像悪化」をご参照ください。

前節の作例と同じ日・同じ場所で、アストロモデルにボディマウント光害カットフィルターを使用して、換算60mmの焦点距離で昇る天の川銀河を撮影してみました。点在する赤い星雲が鮮やかに写っていますね。

光害カットフィルターを使用すると総光量が約半分になり、三脚固定の一枚撮りでは常用ISOの最大の6400でもかなりの露出不足になってしまいます。上の画像は撮って出しのjpegですが、まるで露光不足です。画像処理で持ち上げて無理矢理仕上げましたが、ボディ内光害カットフィルターを使用する場合は通常の一枚撮りでは光量不足は否めず、少々の星の流れは受け入れて露出時間を長めにした方がよいでしょう。
「これ以上露光時間を長くすると星が流れていまう!」ような場合は、後述の「手持ちハイレゾショット」の出番です。
ライブコンポジットで星の光跡を撮る

エントリ機であるE-M10シリーズを含め、OM SYSTEMのほとんどのカメラには「ライブコンポジット」機能が搭載されています。この機能はいわゆる「比較明合成」をカメラ内で行ってくれるものです。
操作は一度覚えてしまえば簡単。モードダイヤルを「B」に設定し、リヤダイヤルを回して「LIVE COMP」を選択し、モードボタンで1コマのシャッター速度を設定します。あとはシャッターを押すだけ。上の画像は撮影風景をスナップ的にライブコンポジットで撮影したものです。通常の後処理による比較明合成では、こういった「カジュアルな風景」は手間とデータ量にひるんでしまいがちですが(*)、ライブコンポジットならその場で比較明合成されるので気楽に撮影することができます。
(*)比較明合成を後処理で行うためには大量の素材データを使用して後処理を行う必要があります。

さらに、ライブコンポジット機能が素晴らしいのは「現在の状態」をモニターで確認しながら撮影できること。星の軌跡がほどよい長さになったと思ったらそこでシャッターボタンを押せば、その状態で撮影が終了します。一枚撮りと全く同じ簡単さです。OMDが一台手元にあれば、さまざまな思い出を記録できることは間違いありません(*)。
(*)一点だけ注意を。ライブコンポジットの際のコンポジット枚数はAdobe Bridgeのメタ情報からは確認できないようです。OMデジタル純正の「OM Workspace」を使用すれば参照できます。

こちらは一生懸命撮影している自分をライブコンポジットで。なんだか幽霊みたいになりましたが、こういう運次第のスナップもサクサク撮れるのがライブコンポジットの真骨頂です。
ライブタイムで豊かな色の星の光跡を

ライブコンポジットとよく似た別の機能に「ライブタイム」という機能もあります。こちらはシャッターを一度押すと開きもう一度押すと閉じる「タイム」撮影なのですが、ライブコンポジット同様、モニター上に現在の状態が表示される(*)のがミソ。
(*)常時更新されるわけではなく、更新間隔を0.5〜30秒の間で設定します。更新可能な最大回数が決まっていて、ISO400の場合は19回です。
ライブタイムが最も生かせる使い方が「長秒一枚撮りによる光跡撮影」。この手法は低ISOで絞り込んで長時間露光で星の光跡を撮る手法ですが、比較明合成と違って空の暗い場所でも光跡が色鮮やかに、そしてマイルドに写る特徴があります。
上の作例は月の出のタイミングを狙って沈む冬のダイヤモンドの光跡を撮影したものですが、ベテルギウスや火星の赤色、シリウスやリゲルの青色、オリオン大星雲のピンク色などが優しく描写されています。
また、遠くの山が月の出の光で赤く照らされていますが、この部分の露光条件をモニター画面で確認しながら撮影終了タイミングを決められるのが「ライブタイム」機能の素晴らしいところで、普通なら難しい撮影を簡単に撮ることができました。

朝焼けの空に昇る夏の銀河。薄明下での光跡撮影も「ライブタイム」機能の得意分野。急速に空が明るくなってくる中で、朝焼けの明るさと色を見ながら終了タイミングを決めることができました。ライブタイム機能は筆者の所有する古い「E-M5(初代)」でも使用できるため、今後積極的に使っていこうと思います。
OM STSTEMの特徴と星空写真適性
ここで、OM SYSTEMのカメラの特徴について簡単にまとめておきましょう。一般的なカメラとしての特徴は本記事ではごく基本的なところにとどめ、星空を撮るカメラとしての特徴を中心に解説します。
小型軽量・マイクロフォーサーズのメリット

OM SYSTEMのカメラは「マイクロフォーサーズ」のミラーレス一眼です。「マイクロフォーサーズ」のイメージセンサーはフルサイズのイメージセンサーと比較して、長さで約半分・面積で1/4の一回り小さなセンサーです。出発点は極めてシンプル。
そして、全てのメリットとデメリットは「より小さなセンサーを搭載した」というところから始まります。フォーサーズ規格のカメラがこの世に生まれた2002年以来、フォーサーズとフルサイズの対決的な言説はそれこそ世の中に山のようにありますが、2025年現在のカメラのテクノロジーで(*)改めて結論だけをまとめます。
(*)過去は小さなセンサーでピクセルピッチを微細化すると入射した光をじゅうぶんに取り込めない(開口率の問題)など「微細ピッチセンサー」固有の課題がありましたが、現在では裏面照射センサーなどの技術でほぼ解決しているといえます。ちなみにE-M1 MarkIIIは「表面照射センサー」のようです。

小さいセンサーの最大のメリットはシステム全体を小型・軽量化できること。単純計算では、カメラシステムを相似的に「長さを半分」にすると体積は1/8になり、重量も最大1/8になります。現実にはバッテリや液晶モニタ、メモリカード、コネクタなどはこれ以上小さくできないのでカメラボディは「一回り」ほど小さくなるだけですが、レンズはかなり小さくできます(*)。
(*)レンズエレメントは正味1/8くらいにまで小型化できる可能性がありますが、マウント径が余裕のあるサイズとなっているため(内径40mm・ソニーEマウントは内径46mm)レンズのメカ部分の大きさは一回り小さい程度です。それでも重量で半分以下にすることができます。
光学系の能力をフル発揮できる高精細ピッチのセンサー

「小さなセンサー」は副次的には他のメリット(*)がいくつかありますが、その中でも星空撮影(特にディープスカイ天体写真)で決定的に有利な点が一つあります。それはセンサーのピクセルピッチが高精細なことです。これは、よく言われる「フォーサーズは望遠に強い」という言説と基本的には同じことです。
(*)センサーユニットが小さく軽量になるためセンサーシフト型の手振れ補正をより高性能化できる、焦点深度が深くなる、センサーに対してマウント径のサイズに余裕があるためレンズ設計の自由度がより高い、小さいイメージセンサーは大きなイメージセンサーより低価格である、など。
一般に高精細なセンサーほど微細な加工技術が必要になるため、より難しく製造コストも高くなります。また、画素数を多くしすぎるとデータ量が多くなり様々な後工程を圧迫します。このため、デジタルカメラではさまざまなトレードオフを考慮し最適な画素数(ピクセルサイズ)が選択されることになります。現在のフルサイズ一眼カメラでは3000万画素前後がボリュームゾーンでしょうか。

ところが、昨今の光学系の性能向上はめざましく、天体望遠鏡(アストログラフ)の分野では「ほぼ無収差」の製品も出てきていて、センサーの解像力が光学系の解像力についていけない傾向が強まっています。フルサイズカメラで最もピクセルピッチが細かい(画素数が多い)クラスは6200万画素(ピクセルピッチ3.76μm)ですが、このレベルでも若干センサーが負けていると感じることもあります。しかも、このクラスのデジタル一眼カメラは非常に高価です(*)。
(*) SONY α7RVの実売価格は2025年3月現在で52万円前後。
一方でOMD ASTROなどのOM SYSTEMのカメラは2037万画素ですが、ピクセルピッチは3.36μmとフルサイズの最高画素クラスよりもさらに微細。高精細なセンサーのカメラをより低価格で入手できるのもフォーサーズのメリットだといえるでしょう。
マイクロフォーサーズのデメリット

一方で、センサーを小さくすることによるデメリットもあります。そのデメリットは大きく2つ。一つめは、フォーサーズは背景(前景)があまりボケません。写真用語でいうと「焦点深度が深くなる」のです。これは簡単な物理的現象なのですが(*2)、メリットになることも同じくらいにあるので、一長一短ではあります。
(*2)仮に、カメラと被写体の両方の大きさを相似的に1/2にしたとします。このとき、カメラがとらえる映像は全く何も変わりません(光の波動性を無視した場合)。一方で「カメラだけ」大きさを相似的に1/2にすると、被写体が2倍遠くにあるのと同じことになります。このため、アウトフォーカス時のボケ量が1/2になります。

ふたつめは、システムを相似的に小型化するとセンサーが受光する総光子数がその分少なくなることです。同じF値・シャッター速度であっても、フォーサーズのイメージセンサー面積はフルサイズの1/4ですから、センサーが受ける総光子数も1/4になります。
このことが実写画像でどのような結果をもたらすかを検証したのが上の画像です。左はE-M1 MarkIII 40mmF2.8で4/3センサーサイズいっぱいの画像。右は焦点距離20mmで2倍にトリミングしたもので、面積1/4の2/3サイズのセンサーのカメラを使用した場合に相当します。
上段はISO400の適正露光条件でで撮影したものですが、ほとんどノイズ感に差はありません。光量が豊富な条件では、光子数の1/4の違いは大きな差にはなりません。一方で、下段はわざと光量を1/512にして無理矢理ISO感度とレタッチで持ち上げたものですが、ノイズ感の違いは明らかです。
このように、暗い被写体においてはセンサー面積が小さいことによる総光子数の差がダイレクトに効いてきます。フォーサーズセンサーは暗い被写体においてはフルサイズセンサーの1/4不利である。このことはフォーサーズのカメラを選ぶ時点で認識する必要があります(*)。
(*)この事実だけをストレートに言っても営業的には何のメリットもないのでメーカーサイドから大きな声で発信されることはないのですが、特に天体を撮影する上ではユーザーにとっては重要な事実です。ごまかしても仕方ないのではっきりと書きました。
そしてこの不利と引き換えに手に入れたのが「小型軽量のシステム」なのです。「より小さなカメラシステムを手にしたときにどんな風にそれを生かせるか」。OM SYSTEMのカメラを選ぶ際に重要なポイントとなるでしょう。
コンピューテーショナル フォトグラフィ
デジタル処理をフルに活用する

OM STSTEMのカメラは「デジタル写真」のメリットを最大限に生かすべく、カメラ内でのさまざまな画像処理を活用した機能が実装されています。OM SYSTEMではこれらの機能を「コンピューテーショナル・フォトグラフィ」と呼んでいます。他社製のデジタルカメラでも多かれ少なかれこのような機能を持っていますが、レンズ交換式デジタルカメラ(*)で一番進んでいるのがOM SYSTEMだといえるでしょう。
(*)実はこの分野で一番進んでいるのはスマホカメラかもしれません。
ここでは、星に対して最も効果を発揮するといえる「(手持ち)ハイレゾショット」について詳しく解説しましょう。
ハイレゾショットとは

「ハイレゾショット」とは、元々は複数枚の画像を「センサーをごくわずかシフトして」撮影し、それらを合成してより高い解像度の画像を得るための機能です。「複数枚」撮影している間は被写体が動かないことが前提となるため、三脚に固定する必要があります(被写体も静止している必要があります)。

一方で「手持ちハイレゾショット」は、手持ち撮影の際には「手ブレ」によって各コマが微妙にズレているであろうことを逆用し、複数枚の撮影画像をカメラ内で「自動的に位置合わせ」して高解像度の画像を生成します。
「ハイレゾショット」はその名の通り「解像度を上げる」撮影機能ですが、星空の撮影の場合「高解像度」のメリットより、むしろ「総光子数アップによる低ノイズ化」の恩恵が大きくなります。「三脚」「手持ち」のいずれのハイレゾショットの場合も、複数の画像を「加算平均(*)」することになるため、暗所の被写体では枚数分だけのノイズ低減効果があり、E-M1 MarkIIIの「手持ちハイレゾショット」の場合は16枚分、露光時間4段分の効果があるのです。
(*)解像度をアップさせる処理が含まれているため単純な加算平均ではありません。天体写真でいうDrizzleのようなものだと推測します。
星空撮影に適した「手持ちハイレゾショット」

この「露光時間4段分」の効果のある「手持ちハイレゾショット」は星空の撮影で特に威力を発揮します。星空は日周運動で少しずつ移動しています。そこで、カメラを三脚に固定して「手持ちハイレゾショット」を使用すれば(*1)、日周運動によるズレはカメラが自動的に補正してくれることになり、「1コマ分」の画像で星が流れてさえいなければ(*2)、露光時間を16倍にしたメリットだけを生かせるのです。
(*1)三脚固定で「手持ちハイレゾショット」を使う、というのは、ちょっとわかりにくいですね。マーケティング的にも、何か別のよい呼び名があるとよいのですが。ダーク減算を行えるようになった時点で「ナイトモードハイレゾ」と呼んで別機能にするのはどうでしょうか?
(*2)OMDで星空を撮る場合、「200/fルール(露光時間が200をレンズの焦点距離で割った秒数以下なら星はほぼ流れない)」を目安にするのがよいでしょう。これは焦点距離25mm(フルサイズ換算50mm)の場合「最長8秒」となります。「500/fルール」では流れすぎます。
星空AF
OMDの大きな特徴が「星空AF」。これは「キラー機能」と呼んでもいいくらいの便利な機能で、OMD ASTROだけでなく、OM STSTEMのE-M1 MarkIII以降の機種(OM-1 、OM-3、OM-5)でも使用することができるす。
星空撮影では「ピント合わせ」が初心者にとって最大の関門の1つ。通常のAFは木星や金星くらい明るい星でないと動作しないため、マニュアルフォーカスでやるしかないのですが、小さなモニター画面でピントの山を探るのは簡単ではありません。老眼の高齢者にとってはさらに厳しいタスクです。
ところが、星空AFを使用すれば、若干の注意はあるものの、この難関を誰でもクリアできるのです。素晴らしい!
「星空AF」は「シングルAF」などを選択するフォーカスモードの一つになっていて、フォーカス機能の1つとして簡単に選択して使用することができます(*)。起動方法はシャッターボタン半押しではなく「AEL/AFL 」ボタンの押下。いわゆる「親指AF」の起動と同じです。上の動画でぜひ動作をごらん下さい。レンズによっても違いますが、「速度優先」モードなら8秒程度で合焦しています。
(*)星空撮影がここまでメジャーになったのか!と胸熱。OMデジタル様ありがとう!
星空AFについては、実写による歩留まり検証などの詳細を記事末の「検証・星空AF」にまとめています。こちらもご参照ください。
高い防水防塵性能
この実験、一度やってみたいのですが怖くて結局できていません^^;;; https://youtu.be/yZ2rEdLQ1mA?si=atKyKb9RtGoWJgCH
俗に「水洗いできるカメラ」とまで言われるOMD。その防塵防水性能の信頼度はデジタル一眼随一でしょう。天体撮影では雨中の撮影はほぼないでしょうが、突然の降雨のダメージは確実に小さくなるでしょう。

それよりも、天体撮影では「センサーにゴミがつきにくい」メリットが大。これは撮像素子面に付着するゴミやホコリを、30,000回/秒以上の超高速振動で強力にはじき飛ばすSSWF(スーパーソニックウェーブフィルター)の効果。
今回のレビューを通じで筆者は一度もセンサーにブロアを吹き付けたことはありませんが、まったくゴミの写りこみはありませんでした。フィールドでもレンズ交換をゴミを気にせず行える、圧倒的な信頼性です。
OMD ASTRO活用シーン(2)
三脚で手持ちハイレゾ・1/4のハンディを逆転する

OM SYSTEMの「手持ちハイレゾショット」機能を使用することで、赤道儀を使用しない三脚固定のみの撮影でも、総露光時間を長く(数分程度)した撮影が可能になります。上の作例は1コマの露光時間はわずが10秒ですが、16枚の画像を星の位置を合わせてスタックしてくれる「手持ちハイレゾショット」のお陰で、総露光時間は160秒(2分40秒)分。このくらい露光時間を確保できればより強い強調処理が可能になり、淡い赤い星雲をあぶり出すことが可能になります(*)。
(*)画像処理はかなりガチなことをやっています。撮って出しではこんな風には写りません。ポテンシャルはこのくらいあるとご理解ください。
「手持ちハイレゾショット」は通常の撮影と同様、raw形式(*.ORF形式)で画像が保存されるため、Photoshop(Camera raw)などの「強化(AIノイズ低減)」を使用することができます。この組み合わせは非常に強力で、ざっくり4枚スタックした画像と同じくらいのノイズ感になります。これら両方を組み合わせれば、1コマ10秒の固定撮影でも(*)総露光5分〜10分くらいの低ノイズの画像が得られるのです。
(*)手持ちハイレゾショットは16コマ撮影してスタックするので、1コマ当たり10秒とはいっても、撮影の所要時間は160秒+スタック処理時間になります。

星空風景の撮影でも「手持ちハイレゾショット」は威力を発揮します(*)。上の作例は昇る夏の天の川を7mm(フルサイズ換算14mm)で撮影したものですが、こちらはややこしい画像処理なしでcamera rawのみでの仕上げ。「強化」も使用していませんが、充分なクオリティを確保できたといえるでしょう。
(*)手持ちハイレゾショットの位置合わせは、画像を複数の領域に分割してそれぞれに対して位置合わせを行っているような挙動をしますが、被写体や条件によっては位置合わせに失敗することがあります。
このように「手持ちハイレゾショット(*)」を使用することで、星空の撮影においては「露光時間16倍分」の効果が得られます。これはセンサー面積が1/4であるハンディキャップを差し引いても、4倍の効果が残ることになります。「手持ちハイレゾショット」のような機能を持たないフルサイズデジタル一眼カメラよりも「4倍有利」となって、1/4のハンディを逆転することができるのです。
(*)ハイレゾショットには「三脚ハイレゾショット」というもう一つの機能があります。こちらはより高解像度の画像を得られるのですが、撮影枚数が8枚と手持ちハイレゾより少ないこと、使用できる最大ISO値が1600と低いこと、低輝度の星空撮影においては実質的な解像度を増すためには露光時間を長くする必要があることなどから、星空撮影には手持ちハイレゾほぼ一択だと思います。
天の川アーチ〜手持ちハイレゾでパノラマ撮影

手持ちハイレゾショットはパノラマ合成でも絶大な効果を発揮します。パノラマ合成とは、カメラを一定角度づつ水平・垂直方向にズラして複数の画像を撮影し、後で専用のソフトウェアで繋ぎあわせることで、広い画角と柔軟な投射方法によるリザルトを得ることができる手法で、「天の川アーチ」が典型的な被写体です。
上の画像は換算24mmのレンズで4×3、12枚のパノラマ合成で撮影した、いて座からケフェウス座までの天の川アーチ。パノラマ合成では赤道儀を併用することが簡単ではなく、1コマ当たりの露光時間が「星が流れない」範囲に制約されてしまうのですが、ここで手持ちハイレゾを使用することで1コマ96秒相当の露光時間を確保することができました。

こちらは同じ手法で海岸から薄明の中の天の川。手持ちハイレゾショットは数多くの撮影シーンで活用することができるOMDのキラー機能の1つといえるでしょう。
小型赤道儀で「お手軽」ディープスカイ撮影

「手持ちハイレゾショット」を使用することで、三脚だけの固定撮影でもディープスカイ撮影にある程度チャレンジできますが、より露光時間を長くして淡い赤い星雲を写しだすにはやはり限界があります(*)。また、焦点距離の長いレンズになると、さらに露光時間を短くしなくてはなりません。
(*)三脚固定のみの手持ちハイレゾショット撮影では最大の総露光時間は4分程度が限界です。(星が流れずに写る露光時間を15秒とした場合)
「赤道儀」を使用して星を追尾すれば、さらに長い露光時間を確保でき、もう一段階淡い暗い天体にもチャレンジが可能になります。上の作例はビクセンの小型赤道儀「ポラリエ」を使用して星を追尾したものですが、換算200mmのレンズでも1コマ20秒の露光時間を確保でき(総露光5分20秒)、オリオン大星雲付近の淡い星雲も出てきました。

撮影風景。ポラリエ赤道儀は本体重量約740gの小型赤道儀のため、あまり重い機材を搭載することはできないのですが、OMD ASTROと40-150mmF2.8レンズの総重量は1460g。なんとか換算200mmで20秒の追尾をクリアすることができました。フルサイズ一眼とレンズの重量では満足に追尾することはできなかったでしょう。こういうシーンでも、OM SYSTEMの小型軽量が生きてくるのです。

こちらは換算焦点距離50mmの画角でオリオン座とバラ星雲。1コマ60秒の手持ちハイレゾショット撮影の2コマ分をphotoshopで重ねて加算平均、総露光は24分相当です。このくらい露光時間をかけるとさらに強い強調が可能になり、オリオン座のバーナードループが鮮やかに、そしてリゲルの右の「魔女の横顔星雲」も浮かび上がってきました。この撮影はちょっと大きめのSWAT-310赤道儀を使用しましたが、この焦点距離ならポラリエ赤道儀でも充分チャレンジできる範囲です。

上の画像は同じ作例の「カメラ撮って出し」jpeg画像。光害カットフィルターの特性で大きく青に転んでいますし、赤い星雲も淡くしか出ていませんが、raw画像を丁寧に画像処理し強く強調すれば、画像データに潜んでいる宇宙の姿をあぶりだせるのです。このような「ディープスカイ天体撮影」にチャレンジする場合は、カメラやレンズなどの機材を揃えること以上に天体写真の画像処理をマスターすることが必要になってきます(*)。
(*)決して簡単ではないのですが、最近はネット上に有益な記事が多数公開されているため、やる気さえあれば自力でもマスター可能です。


換算300mm相当の望遠撮影で「カリフォルニア星雲」と「バラ星雲」。どちらも赤道儀追尾による手持ちハイレゾショット、1コマ60秒の総露光16分です。これくらいの焦点距離になるとより「天体写真」っぽくなってきますね。このレンズで60秒流れずに追尾するにはポラリエでは厳しく、より堅牢な赤道儀(本作例ではユニテック社のSWAT-350赤道儀)を使用しています。
手持ちハイレゾショットの天体撮影は通常のディープスカイ天体写真と違って「スタッキング」の処理が不要で、後処理がかなり楽になります。総露光16分なら1時間で3対象、一晩8時間あれば、なんと24対象!も撮影することができます。「一晩一対象」のガチガチディープスカイ天体写真と、スマート望遠鏡によるお手軽撮影の間くらいに位置するスタイルですね。
カメラレンズでガチ・ディープスカイ撮影

「手持ちハイレゾショット」の場合、最長の露光時間は1コマ60秒16枚の16分。これよりももっと長い露光時間をかけたい場合は、通常の天体写真と同じ「多数枚撮影・スタッキング」が必要になります。上の作例はさそり座のアンタレス付近、俗に「カラフルタウン」とも呼ばれる領域です。2分50枚の総露光100分。
この付近は赤・青だけでなくオレンジなど、様々な色の星雲が散在していますが、いずれも淡いため美しく描写するには最低でも1時間の露光時間が必要でしょう。さらにセンサー固有の輝点ノイズを低減するための「ダーク減算」処理と、レンズの周辺減光を補正する「フラット補正」を行っています。
ここではっきり言っておきたいことは、OMD ASTROはガチなディープスカイ撮影でも充分に使える、ということです。一昔前はフォーサーズのデジカメでこのような写真を撮る人はほとんどいませんでしたが、センサーの性能も向上し、元々優秀だったM.ZUIKO DIGITALレンズともあいまって、フォーサーズでもガチに戦えるのです。

同じ対象をノーマルモデルでも撮影してみました。同時刻、同一総露光時間ですが、アストロモデルとノーマルモデルの差が如実に出ています。特にアンタレスの左下の領域に注目。赤い星雲の写りが全く違うことがわかるでしょう。
天体望遠鏡でガチ・ディープスカイ撮影

OMD ASTROは天体望遠鏡(アストログラフ)を使用した撮影でも威力を発揮します。上の作例はぎょしゃ座の「勾玉星雲」付近を焦点距離243mmの小型アストログラフで撮影したもの。フルサイズ換算では約500mmの画角です。
天体望遠鏡(アストログラフ)はカメラの望遠レンズと比較して、星に対してより高性能な光学系をより低価格で(作例で使用した製品は実売価格8万円前後です)実現できるメリットがあります。なぜなら、無限遠の性能のみに特化した設計が可能であること、オートフォーカス機構や手振れ補正機構が不要なためレンズ構成がシンプルになり製造公差の影響がより少なくなるなどがその理由です。
このような高性能な光学系を使用し長時間(数時間〜数十時間)の露光する場合、フォーサーズセンサーのカメラは「面積1/4」の不利はいぜん残るものの、解像の意味ではむしろ有利に働いていきます。フルサイズ2000万画素のような「ピッチの粗い」センサーでは、光学系の性能にセンサーが負けてしまうのです。OMD ASTROはフルサイズでいえば8000万画素に相当する3.36μmの高精細ピッチですから、高性能な光学系の能力をフルに発揮できるのです。

おおぐま座のM81/M82銀河を焦点距離380mmの天体望遠鏡(アストログラフ)で撮影。銀河のような小さな天体を撮影する場合、よほど長い(1000mm以上)の焦点距離の光学系を使わない限り、大きなセンサーサイズのカメラで撮っても結局トリミングする結果になります。そのため、面積1/4のフォーサーズセンサーでもまったく不利になりません。むしろ粗い画素ピッチのフルサイズカメラよりも有利といえるでしょう(*)。
(*)天体用CMOSカメラを使用するの分野では、1インチ〜フォーサーズでピクセルピッチ4μm前後のカメラがボリュームゾーンになっています。これはフルサイズセンサーのカメラが非常に高価(実売60万円以上)であることもありますが、小さなセンサーは周辺減光や周辺像の流れの影響も少なくなるなどのメリットも大きいからではないかと推測しています。
赤外撮影

こちらはオマケですが、OMD ASTROは「赤外撮影」もある程度可能です。上の画像はカットオフ波長720nmのシート型フィルターをレンズに装着して撮影したもの。720nmではあまり強い赤外効果は出ないものの(*)、青空が暗く・雲が真っ白になり、木々の緑が明るく写るようになります。
(*)SC86フィルターも使用してみましたが6段以上暗くなりレンズのフレアも大きくなるなど、ちょっと「普通ではない」写りでした。
筆者は赤外写真の専門家ではないのでこれ以上は言及しませんが「赤の感度を高めた」OMD ASTROはノーマル機よりははるかに赤外撮影にチャレンジしやすいことだけは確かです。
OMD ASTROを使いこなす
本項ではOMD ASTROを使用する際のいくつかの注意点と使いこなしのポイントを、星空の撮影を中心に解説します。
基本操作を必ず確認しよう
左は筆者の所有する「E-M5」の背面レイアウト。右は「E-M1 markIII」の背面レイアウト。同じメーカーの製品であっても操作レイアウトは異なるのがデジタル一眼カメラの「常識」。 https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/omd/em1mk3/design.html https://jp.omsystem.com/product/dslr/em5/design.html
まず最初に。デジタル一眼カメラは、残念ながらまったく初めての人が、いきなりすぐ使えるものではありません。OMD ASTRO(E-M1 MarkIII)の場合、17個のボタン・3個のダイアル・2個のレバー、そして十字キーとジョイスティックがあります。全部で、、、24個!(*)
(*)中級向け以上のモデルであれば、OMDに限らず各社ともだいたいそんなものでしょう。音声認識で機能設定を呼び出せればめちゃくちゃ便利になると思うんですがねえ、、
さらに「カスタム設定」でこれらのボタンやダイヤルにさまざまな機能を割り当てたり、割り当てを変更することができます。デジタル一眼カメラを「便利に」使う上では「カスタム設定」は欠かせないものとなっています。
このことはすでにデジタル一眼をお使いの方にとっては「当たり前」ですが、これから初めて「デジタル一眼」を使う方には最初のハードルです(*)。しっかり事前に操作体系を勉強しておきましょう。
(*)筆者はたいていのツールはマニュアルを開くことなく使えていますが、デジタル一眼はそうはいかないツールの1つです。
※記事末の補足に筆者が行った「カスタム設定」の一覧を書いています。ご参考まで。
ライブビューブースト

一昔前の多くのデジタルカメラでは、ライブビュー画面では構図を決められるほどには星空は見えませんでした。しかし、最近のカメラでは、その多くに暗所でのライブビュー性能を上げる(ブースト)するための機能が設けられるようになっています。
OMD ASTRO(のベースモデルであるE-M1 MarkIII)でも「ライブビュー(LV)ブースト」という設定が可能になっています。LVブーストには「on1」と「on2」の2つのモードがあります。上の画像は「on1」ですが、このモードはブースト率が低いかわりに画面表示のフレームレートが低くならず、構図を微調整したりMFでピントを合わせるのに適しています。
LVブーストを「on2」にすると、さらに感度が上がってもっと星が見えるようになりますが、フレームレートは低下するため、かなり「カクカク」した表示になります(*)。
(*)マニュアルフォーカスでピント合わせする場合、「on2」だとリングの回転に表示画像が追いつかずちょっとイラッとします。構図合わせの時もカメラの動きとライビューの表示にタイムラグがでてしまいます。このため筆者はもっぱら「on1」で使っていました。
とはいえ、ライブビューブーストは星空撮影では必須に近いものです。カスタムキーに割り当てて(*)すぐに呼び出せるようにするのが便利でしょう。
(*)OMD ASTROでは出荷時の状態で録画ボタンがLVブーストの切替設定となっています。録画ボタンの長押しでフロントまたはリアダイヤルを回すとモード切替も可能です。
なお、ライブビューブースト状態ではカメラ側の露出設定は反映されません。モニター上で明るく見えているからといってその通りには写らないことに注意が必要です。メニューの「セットアップメニュー」で「撮影確認」をON(*)にしておくことを推奨します。
(*)出荷時設定ではOFFになっています。
長秒・多数枚露光する方法
OMDでは長秒・多数枚の撮影を行える機能が複数用意されています。一番簡単なのはカスタムセルフタイマー機能です。撮影間隔を指定して10枚までの連続撮影を行うことができます。例えば、露出時間5秒で10枚撮影して後で自分で画像をスタックするような場合に便利に使えるでしょう(*)。

インターバル撮影機能を使用すればさらに自由度が上がります。1コマ当たりの露光時間が60秒以下であれば、外付けリモコンは不要といってよいでしょう。インターバル撮影で撮影した画像でタイムラプス動画を自動保存することも可能です。
1コマあたり60秒を超える露光時間で連続撮影したい場合は外部リモコンが必要になります(*)。筆者は中華製のワイヤレスリモコンを使用しました。カメラ側の端子はステレオミニジャックです。同じ規格なら他社製のリモコンも使用できるでしょう。
(*)シャッター速度に90秒/120秒/180秒が設定できればほぼ外部リモコン不要になるのですが。これは全てのカメラメーカー様への要望ですが、長秒シャッター速度の上限はもっと柔軟にしてほしいものです。
「連続撮影」ではなく単写の場合は「BULB/TIMEリミッター」の設定によって最大30分の長秒露光が可能になります。これは「この時間経過すると強制的にシャッターを閉じる」機能です。
AIノイズ処理の活用
「コンピューテーショナル フォトグラフ」においてAI機能は重要な柱であることは間違いありません。AdobeのPhotoshop(Camera raw)/LightroomにAIノイズ低減機能(「強化」)が2023年に実装されましたが、OMデジタル社も自社製の画像処理ソフト「OM workspace」にAIノイズ低減の機能をリリースしています。
OM Workspace
https://software.omsystem.com/omworkspace/ja/
上の画像は1枚画像と16枚の手持ちハイレゾショット画像に対して、それぞれのソフトを使用してノイズ処理結果を比較したものです。 10秒1枚画像では非常にノイジーだったものが、AIノイズ処理でびっくりするほと滑らかになることがわかります。塗り絵っぽい感じにはなりますが、ノイズ感だけで評価すれば「もうこれで充分」といってもいいくらいです。
一方で星の色は10秒露光ではほとんど白色になってしまい、10秒16枚の画像との差は明らかです。被写体の本来の姿を描写するためには、やはり露光時間が正義といえるでしょう。
とはいえ、露光不足のノイジー画像を救済できるという意味ではAIノイズ処理は非常に強力なツールです。光量不足に悩まされがちなマイクロフォーサーズのカメラにおいては、フルサイズカメラ以上に使いでがあることは間違いありません。
手持ちハイレゾは万能ではない

非常に使いでのある「手持ちハイレゾショット」ですが、自動位置合わせの機能は万能ではありません。上の画像は1コマ15秒、総露光3分間の手持ちハイレゾショットです。この場合星は日周運動で移動していきますが、風景は移動しません。こんな動きの異なる2つの被写体が映り込んだ画像を手持ちハイレゾショットはどのように処理してくれるのでしょうか。
リザルトを細かく見てみましょう。①の中心部の星はほとんど流れることなくスタックされています。一方で④の周辺部の星は位置合わせがうまくいかず、複数の像に分かれてしまっています。②の地上風景はしっかり位置合わせしてくれていますが、③の地上風景は少し流れた感じです。
このように手持ちハイレゾショットは単純に画像全体をズラして重ねるのではなく、それ以上に「賢い」やり方(*)で「がんばって」位置合わせしてくれますが、それでも場合によっては位置合わせが完全でないこともあるようです。
(*)比較は行っていませんが、これはSequatorのようなソフトウェアでも起きうることです。

天の川や明るい星の多い条件ではなかなか好成績だった「手持ちハイレゾショット」ですが、地味な春の星座では失敗が多かった印象。上の作例の場合、①の地上風景はしっかり位置合わせされているものの、②③④では明るい星は位置合わせされている一方、多くの暗い星は位置合わせされておらずほぼ日周運動の光跡を描いています。一方で⑤のようにだいたい位置合わせされている領域もあります。
上の作例は総露光時間160秒ですが、地上と風景の入った撮影の場合はもっと露光時間を短くした方がよいかもしれません(*)。
(*)「1コマ2秒で総露光32秒」「1コマ3秒で総露光48秒」くらいで使用したいのですが、露光時間が短いと画像が暗くなりすぎて、最後のスタック処理の際に失敗する確率が上がってしまいます。ISO25600くらいの感度が使えるようになれば、その問題は軽減すると思われます。
元々違う動きをしている被写体を撮っているのですから、頑張って位置合わせしてくれているだけでもありがたいことです。ユーザー様には「長すぎない適切な露光時間を」、メーカー様には「より賢いアルゴリズムの開発と使えるISO感度設定のアップを」とお願い申し上げます。
M.ZUIKO DIGITALレンズ インプレッション
今回のレビューでは7本のM.ZUIKO DIGITALレンズをお借りしました。それぞれのレンズの特徴や作例をご紹介します。
お約束)本節の内容は特定の個体における撮影結果です。検証には細心の注意を払ってはいますが、この結果のみが製品の性能を示すものではありません。また撮影時の条件(ピント位置、大気のゆらぎなど)にも依存します。
M.ZD ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
OM SYSTEM M.ZUIKO Digital ED 8mmF1.8 PRO 製品情報
https://jp.omsystem.com/product/lens/single/pro/8_18pro/index.html
対角線魚眼としてF1.8という画期的な明るさを持つレンズです。この明るさだけでもフルサイズのF4対角魚眼レンズよりも総光子数で上回ることになり、OM SYSTEMの魅力を大きく後押ししてくれるものです。
中心星像は極めてシャープ。周辺画質も倍率色収差が若干あるものの良好で、開放では若干青ハロがあるもののそれさえ許容すれば開放F1.8から使えます。イヤな流れやコマが少なく、星空を撮影する上でストレスの少ないレンズです。なお、F3.5に絞っても周辺・中心とも青ハロ改善以外はあまり画質は変わりませんでした。
ボディ内フィルターを装着しても星像悪化が少ないのが特筆で(*)、超広角域の常用レンズとしても活用できるでしょう。
(*)筆者所有の他社製魚眼レンズでもこの傾向があります。一般に魚眼レンズはリアフィルターによる光路長変化に強いといってよいと思います。

実写作例。冬のダイヤモンドに木星と火星が加わった賑やかな空を対角魚眼で一網打尽。対角魚眼レンズは地平線がこのように円形に歪みますが、周辺でも星座の形が崩れにくいため星空撮影に適しているといえます。
M.ZD ED 7-14mmF2.8 PRO
OM SYSTEM M.ZUIKO Digital ED 7-14mmF2.8 PRO 製品情報https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/pro/7-14_28pro/index.html
星空風景で最も多用されるであろうフルサイズ換算14-28mmのF2.8ズームです。これ1本(534g)とOMD ASTROボディ(580g)、1kgの小型三脚を使用すれば総重量はわずか2.1kg。フィールドで星空を狙うのには最軽量クラスのシステムになります。
広角端の中心星像は開放でも素晴らしいものです。四隅では放射状に少し流れますが、超広角としては優秀な部類でしょう。望遠側ほど中心は若干星像径が大きくなり、周辺ではコマが若干目立ちますが、星空撮影用としても非常に高性能なレンズです。

実写作例。このレンズは本記事の他の作例でも多数使用していますので、ここではライブコンポジットの作例を。月夜の海岸で昇ってくる春の星座の光跡をとらえました。換算14mmの超広角は遠景だけで作画すると平板になってしまいがちですが、光跡撮影では天の赤道から北と南の光跡の弧が逆向きに描かれ、地球の自転がよりリアルに感じられる形になりました。
M.ZD ED 12-40mmF2.8 PRO
OM SYSTEM M.ZUIKO Digital ED 12-40mmF2.8 PRO 製品情報
https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/pro/12-40_28pro/index.html
一般撮影で最も用途の広いであろうフルサイズ換算24-80mmのF2.8ズームです。このスペックのレンズの重量がわずか382gに収まるのがマイクロフォーサーズの強み。星空撮影においては広角側がもっと広ければと感じることもあるでしょうが(*)、星空を「自分の視点で切り取る」という意味で、最も使いこなし甲斐のあるレンズかもしれません。
(*)このレンズの広角端12mmの画質は、7-14mmの望遠側12mmのそれを上回っていると感じました。ぜひ両方手に入れたいところ。
広角端12mmでは、開放でも中心の星像はとても小さくシャープで、軸上色収差も気になりません。望遠端40mmでは開放では羽根状のコマが大きく中心像も若干赤ハロが感じられ、星用途にはF4まで絞った方がよさそうです。

実写作例。夜明け前の薄明の空の夏の天の川を広角端12mmで。このレンズも広角側ほど星空撮影においては高性能であると感じました。
望遠端では若干星像が甘く感じることもあり、星撮り用にはもうひと頑張りしてくれると嬉しいのですが、このレンズの実売価格が9.6万円前後(*)であることを忘れてはなりません。他社のフルサイズミラーレスカメラの純正F2.8標準ズームレンズと比較すれば、はるかに低価格です。コスパの高いレンズといえるでしょう。
(*)OM-1 markIIではこのレンズとボディのセット版が、本体価格の約5万円増しで販売されています。ハイグレードのキットレンズと考えれば非常にコスパが高いといえるでしょう。

夜明け前に昇ってきた細い月を望遠端40mmで。筆者の場合、大きく重いフルサイズの撮影システムを使用する際は、望遠側のレンズが「お留守番」になることがよくあるのですが、フルサイズ換算80mmまでカバーできるこのレンズはわずか382gで星空を撮る際は常に持ち歩ける軽さ。「軽いレンズ」は撮影機会を拡大してくれると感じました。
あえてユーザーとしてのワガママを投下するとすれば、7-14mmと同様「周辺をもっと点に!」してほしいところ。ここ数年で各社から「周辺でも星が流れず点になる」レベルの高性能レンズが発売されてきています。このレンズは2013年の発売ですが(*)、次期モデルではレンズ設計のさらなる進化を期待したいところです。
(*)2013年時点で評価すれば、画期的な高性能レンズであったといえると思います。2022年に「II型」にリニュアルされていますが、主にコーティングやメカ部の改良のようで、基本光学設計は同じのようです。
M.ZD ED 12mmF2.0
OM SYSTEM M.ZUIKO Digital ED 12mm2.0 製品情報
https://jp.omsystem.com/product/lens/single/premi/12_20/index.html
わずか130g、たった130gの明るい広角単焦点レンズです。質感が高く、眺めているだけでもご飯が進みます^^ 価格も実売5万円程度と手ごろで「ついポチリ」しそうなレンズといます。
開放F2.0では軸上色収差によるハロが大きく、強く強調すると微光星の赤ハロが目立ち、クオリティ重視の星野撮影にはちょっと苦しいところがありますが、F2.8でかなり改善しF3.5まで絞ればF2.8標準ズームとも遜色ないほぼ満足できる画質になります。周辺像は若干流れますが、こちらも一段絞ることでかなり改善します。手持ちハイレゾショットと組み合わせて露光時間を稼げば、マイクロフォーサーズでも最軽量級の星空撮影システムになるでしょう。

実写作例。実はこれはOMDの初代機である「E-M5」で2015年に撮影した画像を再処理したものです。内地では考えられないような暗い空だったのですが、今回最新のツール(camera rawの「強化(AIノイズ処理)」で画像処理したこともあり、驚くほど良く写っています。
古いOMDでも、最新の画像処理を行えば、じゅうぶん星空撮影でも高性能を発揮することを感じました。最新のOMD ASTROで、もう一度波照間島で撮影したいものです。
M.ZD ED 17mmF1.2 PRO
OM SYSTEM M.ZUIKO Digital ED 17mmF1.2 PRO 製品情報
https://jp.omsystem.com/product/lens/single/pro/17_12pro
F1.2の明るさを誇る、OM SYSTEMのフラッグシップともいえる広角単焦点レンズです。このレンズもわずか390gと軽く、同スペックのフルサイズレンズの半分以下の重量です。
ただし、F1.2開放では、中心星像に巨大なフレアが取り囲み、普通ではない写りです。しかし、少し絞るだけで急激に改善し、F1.8で許容範囲となり、F2.5で星空撮影でもまず満足の画質になります。絞っても周辺が若干流れる傾向は変わらないので、星空を撮る場合はF1.8〜F2.5くらいの間で撮るのが得策でしょう。

実写作例。絞りF2.2ですが、最周辺部もまずまずの画質です。よほど「画質より明るさが欲しい」ようなケース以外にF1.2開放で使用するのはオススメしませんが、F2.8のズームレンズよりは1絞りほど明るいレンズになります。実売16万円前後のハイグレードレンズですが、なかなか悩ましい選択です。
M.ZD ED 75mmF1.8
OM SYSTEM M.ZUIKO Digital ED 75mmF1.8 製品情報
https://jp.omsystem.com/product/lens/single/premi/75_18/index.html
フルサイズ換算150mmの望遠単焦点レンズです。重量は305g。フルサイズでこの焦点距離の単焦点レンズはほとんどありません(*)。脳みそがバグりそうな軽さです。
(*)生産終了品ですがシグマAPO MACRO 150mmF2.8の場合1150g。
EDレンズを3枚使用していて期待値は高くなるのですが、開放では軸上色収差が大きく、ディープスカイ撮影では絞って使うことを推奨します。F2.5でもまだ青ハロが大きく厳しいですが、F3.5まで絞れば青ハロ赤ハロともにかなり減少しディープスカイでもじゅうぶん使えるクオリティになります。
フルサイズ換算150mmの画角のレンズがたった300gで使えるのであれば「少々絞っても腹は立たない」といえるのではないでしょうか。昼間の撮影ではF1.8の明るさによるボケを生かした撮影が楽しめますし、F2.8望遠ズームより手ごろな価格(実売10万円前後)なので、こちらも「1本ポチリ」してしまうレンズかも。
こちらも勝手な要望ですが、発売から12年経過したこのレンズは、そろそろリニュアルしてほしいもの。軸上色収差をさらに低減し開放でも使えるレンズになれば、OM SYSTEMの神レンズの1本に入ることは間違いありません。

実写作例。こちらはノーマルモデルの「E-M10 MarkIV」で撮影しました。E-M10シリーズはOMDシリーズのエントリモデルですが、E-M1 MarkIIIと遜色のない写りです。ただし「ハイレゾショット」を使用することはできません。ライブコンポジットは使えますので、実売9.5万円前後と入手しやすい価格でもあり、サブ機として活躍してくれるでしょう。
M.ZD ED 40-150mmF2.8 PRO


OM SYSTEM M.ZUIKO Digital ED 7-14mmF2.8 PRO 製品情報
https://jp.omsystem.com/product/lens/zoom/pro/40-150_28pro
フルサイズ換算80mm〜300mmのF2.8望遠ズームレンズです。俗に「大三元」と呼ばれるF2.8通しのズームレンズの場合、望遠側の焦点距離は70〜200mmの製品が大半ですが、マイクロフォーサーズのメリットを生かしてこのレンズの望遠端は換算300mmです。重量は三脚座込みでわずか880g。フルサイズではこの重量と価格はとうてい実現できないことでしょう(*)
(*)キヤノンのRF100-300mm F2.8 L IS USM」は2580g、実売価格135万円です。
中心星像径は若干大きめで少し軸上色収差が目立ちます。望遠端は最周辺でややコマ収差が、広角端は倍率色収差が大きめ。しかし、ディープスカイ天体写真の場合はBXTなどのツールを使用することで十二分な像質になります。
さすがに昨今の高性能アストログラフには及びませんが、小型軽量であること、星空AFが使えること、ズームのメリットを生かした自由な作画など、カメラ用望遠レンズならではの使いやすさがあります。

実写作例。ノーマルモデルのE-M1 MarkIIIで撮影しました。赤い星雲を写すにはアストロモデル(+光害カットフィルター)が圧倒的に有利ですが、アストロモデルでないと星や赤い星雲の写真が撮れないというわけではありません。
お手持ちのカメラがノーマルモデルであっても、対象をうまく選べば天体写真にチャレンジすることは可能です。ただし、かなりの長時間露光と丁寧な画像処理が必要になります。
M.ZUIKO DIGITALレンズ総括
M.ZUIKO DIGITALレンズは、どれをとっても小型軽量で耐候性・耐寒性が高く、アウトドアで使用する上でも、とても信頼できるパートナーです。開放の周辺減光も少なく(*)、光学性能もバランスのいい高性能・・・です。ただ、繰り返しになりますが、ユーザーのワガママとしては「星撮りに最適な神レンズが欲しい」。M.ZUIKO DIGITALレンズは高性能ですが、(星撮り用に)突き抜けているわけではないのです。
(*)M.ZDレンズは、camera raw現像の際にレンズのプロファイル補正が常に適用されOFFにすることはできないようです。PixInsightでrawデータをディベイヤーして確認するかぎりはプロファイル補正に大きく頼っているわけではなさそうです。全般に周辺減光は開放でも少なめであると感じました。
焦点距離のラインナップとしては、8〜10mmの明るい(F1.8〜F1.4)広角単焦点が欲しいところです。一方で発売から長い時間が経過している既存レンズをリニュアルすることも、星撮り用途以外への訴求も含めて喫緊の課題でしょう。
レンズの品揃えを充実させるのは長期戦です。まずは1本でも「本気の星撮りレンズ」と呼べるような、神レンズがリリースされることを切望するものです。
どんな人に向いているか

軽いシステムでフットワーク良く星空を撮りたい人に

OM SYSTEMの最大の特徴は、アウトドアに適した小型軽量・防水防塵のカメラであること。天体のような暗い対象を撮影する場合は、センサー面積の大きな中判カメラ・フルサイズカメラと比較して不利な点(*)はあるものの、用途によってはそれを補って余りあるメリットがあります。
(*)大事なことなので繰り返しますが、同じF値・画角のレンズを使用した場合、同一露光時間で捕捉できる総光子数はセンサー面積に比例します。マイクロフォーサーズのセンサー面積はフルサイズの1/4、その分だけ不利になります。

さらに、センサー面積が小さいデメリットは「手持ちハイレゾショット」などの「コンピューテーショナルフォトグラフ」機能により、大幅に縮小・時には逆転することもあります。「フォーサーズのカメラは天体に不向き」という考え方はもう過去のものとなりました。貴方の目的や指向がマッチするのであれば、OMD ASTROは最適な選択肢となることでしょう。
自分だけの「体験」を重視したい人に

画質だけにこだわるのであれば、暗い被写体を対象にする天体撮影においては特に、センサー面積のより広いカメラに軍配があがります。これは「物理的事実」であり、どうすることもできません(*)。
(*)フルサイズカメラのセンサー面積は4/3の約4倍。同じ画角・同じF値であれば、4倍の光子を捕獲することができます。低照度の被写体を撮影する天体写真では、この「捕獲光子数」の差が大きく画質に効いてきます。
しかし、貴方が求めるものはリザルトの画質だけなのでしょうか?もし、貴方が自分の足で被写体のもとに赴き、五感で被写体と対話するという体験を重視したいのであれば、小型でアウトドアに強いOMD ASTROは力強いパートナーとなってくれることでしょう。
↑こちらはOMD ASTROで山に登ってきましたという動画です。
天体改造という「冒険」はしたくない人に

これまで、天体用のカメラは専門の業者で「天体改造」することが一般的でした。このようなメーカーの手によらないカメラの「改造」を行うと、保障期間中であっても無償修理対応ができなかったり、修理のためには「改造」を「原状回復」する必要が起きたりします。当然とはいえ、改造後のリスクはすべてユーザー側の負担となります。こんな「冒険」は普通はあんまりしたくないものです。
メーカー純正の「天体モデル」のメリットはまさにここにあります。しかし、メーカー純正の「天体モデル」も過去散発的に発売されたことがあるものの、2025年3月現在新品で購入できる純正の天体用カメラは「OMD ASTRO」だけなのです。
さらに、デジタル一眼カメラの中ではOM SYSTEMのマイクロフォーサーズカメラは比較的お手ごろな価格。最新のフラッグシップモデルである「OM-1 MarkII」でも量販店価格は27万円前後、OMD ASTROは同30万円前後(*)です。
(*)ボディマウントフィルター2種が付属する(単体販売では6.5万円前後)ことを考慮すると、この価格はほぼ適正価格といえるでしょう。
大手3社のフルサイズミラーレスカメラの価格が高騰してしまった昨今、OMD ASTROは「お財布にも優しい」といえるのではないでしょうか。
OMD ASTROに望むこと
手持ちハイレゾショットにダーク減算を

前項でも触れたとおり、OMDの「手持ちハイレゾショット」は、フォーサーズセンサーの「面積1/4」の不利を逆転できる、星撮りにおけるキラー機能といえます。しかし「星撮り」においては若干不十分なところがあります。第一には「ダーク減算」です。
上の画像は、センサー固有の「輝点ノイズ」が、手持ちハイレゾショットで悪さをしている例。このような挙動の問題は天体写真においては古くから問題視されていて「ダーク減算」という手法で解決することが一般的です(*)。
(*)ほとんどのデジタル一眼カメラが備えている「長秒時ノイズ低減(シャッターを閉じて同じ露光時間・ISO感度の画像を撮影し、元画像から減算して補正する)」と同じ手法です。
この事象は、OMDでは「手持ちハイレゾショット」の際にダーク減算が行われないのが原因です(*1)。元々の「手持ちハイレゾショット」が星撮りのような低照度・長時間露光を想定していなかったであろうことは理解しますが、ぜひ高いプライオリティで実装されること(*2)を望むものです。
(*1)パナソニックの「LUMIX S5Ⅱ&S5ⅡX」では、最長露光時間8秒という上限が痛いものの、長秒ノイズ低減に対応しています。
(*2)センサーの特性によっては、ダーク減算の優先順位が大きく下がる可能性もあります。たとえば、ピクセルマッピングで正常な挙動ではないピクセルをより広く補間してしまえば、ダーク減算を行わなくても充分な画質が得られる可能性もあります。
もうひとつオマケですが、(手持ち)ハイレゾショットでは「最初の一枚」だけがraw形式で保存されますが(*)、これを「全てのコマを保存」する設定があるととても嬉しいです。ハイレゾショットは最後の合成(スタック)で失敗してしまうことがあり、16分の撮影がおシャカになるとけっこう悲しいものがあるので・・
ソフトフィルターの効果がやや弱い

前項でも触れた通り、OMD ASTROにはボディ内装着型の「ソフトフィルター(BMF-SE01)」が同梱されており、明るい星を滲ませることでより人間の視覚に近い星空の姿を撮影することができます。
しかし、ソフト効果は若干弱めです。星空撮影でよく使用されるケンコーの「プロソフトンクリア」よりもさらに一段階ほど弱い感じ(*)です。
(*)「LeeのNo1〜2相当」と感じました。
もちろん、ソフトフィルターの効き具合は個人の好みの領域でもあるのですが、想定ユーザーニーズを最大公約数的に見ると、やはり「一段階弱い」といえるのではないでしょうか(*)。
(*)別売にしてユーザーが好きなものを選べばよい、という考え方ももちろんありますが、光害カットフィルターの同梱も含めて「トータルでの星空撮影ソリューション」を低価格で提供するための「同梱」戦略と理解しました。それならば、なおさらユーザーニーズによりヒットするソフト効果を選択するのが良いと感じました。なお、光害カットフィルターの効果(波長特性)については、ジャストストライクだと思います。
もっとISO感度を上げて撮影したい
OMD ASTROのライブコンポジットでは、ISO感度の上限は「1600」、手持ちハイレゾショットのISO感度の上限は「6400」となっています。動画撮影もISO6400以上の設定はできません。一方で通常撮影の場合の「常用ISO感度(*)」は200〜6400、「拡張ISO感度」の上限は25600です。
(*)「常用感度」と「拡張感度」が具体的に何が違うのかは、どのメーカーも明言しておらずカメラの謎の1つなのですが、筆者は「常用ISO感度域では主にCMOSセンサーのGain(信号値をアナログアンプで増幅する)の調整で実現」「拡張ISO感度域ではデジタル的に信号値を乗算して実現」されているものと推測しています。ちなみに、最新モデルのOM-1/3では最大ISO感度は102400に、手持ちハイレゾショット(撮影枚数は12枚)の設定感度上限も同じ102400に拡大されています。
元々のISO感度よりも高く設定できないことは理解できるのですが、ノイズが目立ったとしてももっとISO値を上げたいシーンがあります。たとえば、ライブコンポジットでISO25600が使えたとしたら、流星群をF2.8 ISO25600 4秒露光でライブコンポジットで撮影ることで、流星がぽつぽつと増えていくさまをライブ配信できることになりますし、星空のリアルタイム動画においては最大ISO6400では全く歯が立ちません。
このようなISO感度の上限設定が、どのような理由によるものかは不明ですが「そんなにISOを上げるとノイズが増えすぎるため実用的でない」という理由なら上限は設けないでほしいところです。天体の撮影ではノイズは普通にそこにあるもの(友達!)です。びっくりするほどノイジーな元画像であっても、あの手この手でキレイに仕上げることが可能なのが「天体写真」なのです。暖かくユーザーの手に委ねていただけると嬉しいです(*)。
(*)もうひとつ、CMOSセンサーの内部的なゲイン値についてですが、もしかしたら敢えて「控えめ」になっているのでしょうか?昨今のCMOSセンサーはかなりの高ゲインを設定できるはずで、1万円しない家庭用監視カメラでもかなりの暗所性能を発揮します。なぜそれよりはるかに大きな4/3センサーで「(常用)ISO6400」程度しか実現できないのだろうと思ってしまいます。
より低価格で型落ちでないボディのアストロモデルを
OM SYSTEMの最新モデル「OM-3」。これのアストロモデルが発売されたら超胸熱なのですが^^ https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om3/index.html
OMD ASTROのベースモデルである「E-M1 MarkIII(2020年2月発売)」は2世代前のフラッグシップモデルになります。ニッチな「星空撮影」に向けて商品を投入する上で諸事情があったことは推察しますが、ユーザー的にはより最新のモデルで実現してほしいところです。
さらに、星撮りにおいては「フラッグシップモデル」である必要はまったくありません。高速連写・高速AFは不要、高度な被写体認識AFも不要、EVFですらなくても困りません。より低価格な普及モデルでも充分なのです。(*)
現在のラインナップでいえば、アストロモデルに最適なベースモデルは「OM-5(実売価格14.5万円前後)」でしょうか。一方で、最新モデルのOM-1/3ではセンサーの性能向上だけでなく、より星空に適したライブビューブーストなど、星空撮影に魅力的な機能が多数追加されています。悩ましいところですね(*)。
写真家 飯島 裕 × OM-1 ~OM-1の写真がつなぐ星とヒト、磨き上げられた星空撮影の実力~
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/om/om1/special/review/iijima-yutaka/index.html
(*)理想は裏面照射センサー搭載のOM-1/3なのですが、価格的にだいぶ上になってしまいます。E-M10 MarkIV(実売価格9万円前後)は低価格ではありますが、手持ちハイレゾショットが使用できないのが厳しいところ。OM1/3と同じセンサーを搭載したPENシリーズがより安く製品化されれば、こちらが第1候補になるでしょう。個人的には・・・OM-3 ASTROがぜひ欲しいです^^
いずれにせよ、E-M1 MarkIIIは販売が終了した製品なので、いずれ在庫が払底しその時には「E-M1 MarkIII ASTRO」も終売とならざるを得ないでしょう。その時に後継となるアストロモデルが「型落ちでないモデル」で製品化されることを切に願うものです。
「色調整フィルター」による「ふだん使い」対応
OMD ASTROは、2世代前のモデルとはいえ、ベースはフラッグシップカメラです。天体以外の写真も普通に撮影したいと思いませんか?

ところが、前項でも触れた通り、OMD ASTROは天体撮影に特化した分光感度特性となっているため、メーカーでも「一般撮影には向かない」ことを明言しています。カラーバランスを細かく調整することで(*)、ある程度普通っぽくなりはしますが、近赤外の反射率が高い一部の被写体(上の画像における「樹木の緑」など)においては、レタッチでは埋め切れないレベルの色の差が残ってしまいます。
(*)「色温度」「色合い」だけの調整ではかなり乖離が大きく、ハイライト・中間調・シャドウのそれぞれを調整する必要がありました。
これは、人間の視感度特性とCMOSセンサーの感度特性が一致しないがゆえに、デジタルカメラにはそれを補正するためのフィルターがわざわざ装着されているのに、赤い星雲を撮りたいがためにそれを外してしまったのが原因です。それなら、外したフィルターを外付けすればいいのではないか?!

アリエクで「ノーマルモデルと同じ(近い)分光感度特性」っぽい上のフィルターを探してみました(*)。
(*)日本のアマゾンでは見つけられませんでした。シグマ光機や住田光学ガラスからも入手できそうですが、けっこうなお値段がします。
このフィルターは、なだらかに波長が長いほど光を吸収する色ガラスフィルターです。グラフから読み取るとHα線の透過率は30%程度。
試写結果。「色調整フィルター」を装着することで、ほぼノーマル機と同等のカラーバランスとなりました(*)!
(*)厳密にはボディ側の波長特性に最適化された波長特性ではないため、ほんの少しブルー寄りの色になったため、クリックホワイトバランス調整で補正しています。
同様のものと思われるフィルターは、日本のよしみカメラ様でも販売されています。こちらは赤のカットオフ特性を4種類選ぶことができるようで、よりベースのカメラの特性に合わせた選択が可能になっているようです。
STC社製 UV-IR CUTフィルター(吸収タイプ)
https://yoshimi.ocnk.net/product/261
もちろん、純正ノーマルカメラと厳密に全く同じカラーバランスにはなりませんが、よほどシビアな用途でなければ充分使えるものと感じました。アストロモデルにこのようなフィルターが(できればクリップ型で!)付属すれば、天体用・一般用の両刀使いのカメラとなり、ユーザーの利便性がより向上するのではないでしょうか。
長秒露光を想定した際のUI向上

星空の撮影は「待ち時間」の多い撮影です。露光時間を30秒に設定したら30秒間待たなくてはなりません。ところが、OMDの「ハイレゾショット」や「インターバル撮影」では、それに対する若干の配慮不足を感じます。
例えば、インターバル撮影では撮影の「残り枚数(*)」が画面に小さく表示されるのですが、これは撮影のコマ間の待ち時間の間しか表示されません。もっと大きな文字で撮影中にも「残り枚数/全撮影枚数」を表示してほしいところ。
(*)「残り枚数」なのか「撮影済み枚数」なのかが明記されていないのも悲しいところ。ちなみにOMDはセルフタイマーでも10枚までの連写が可能でこれもお手軽インターバル撮影に便利なのですが、こちらも同じく枚数は表示されません。
また、ハイレゾショットでも「今何枚目の撮影なのか」が表示されません。60秒16枚のハイレゾショット撮影を始めてしまうと、あとどのくらいで終了するのか皆目見当が付かなくなってしまいます。ぜひこちらも「残り枚数/全撮影枚数」を常時表示してほしいところです(*)。
(*)古い話ですが、キヤノンのEOS Kiss X5はバルブ撮影時に経過時間が大きくモニタに表示されとても便利だったのですが、上位機種であるはずの5DMarkIII/6Dではそのような表示はありません。このあたり、メーカー側でも一貫した方針を共有できていないのかもしれません。
これらはいずれもシャッターが一瞬で切れる昼間の撮影では全く問題にならないのですが、露光時間の長い撮影ではとても便利になるものです。ぜひご検討いただければと思います。
PD給電時のバッテリ表示
E-M1 MarkIIIはUSB-PDに対応しており「給電しながらの撮影」が可能になりました。これは星空撮影でもとても有用な機能なのですが、2点細かい要望があります。

ひとつは、バッテリを接続したときも「そのUSB-C、何に使うんですか?」とカメラが聞いてくるところ。カメラ側で接続先がPDであることは認識できると思うのですが、これは自動化できないのでしょうか?(*)
(*)パソコンやスマホなど、USB-Cでデータ通信しつつ給電も可能なデバイスがありますが、その2つを同時にカメラ側が対応できないために選択の必要があると言うことでしょうか。
もうひとつは、給電を開始し「カメラが現在外部USB-PDで動作している(*)」状態が明示的に表示されないこと。よくあるのは充電中のときはバッテリインジケーターに雷マークが表示される仕様ですが、E-M1 MarkIIIは「バッテリインジケーター表示そのものが消える」のです。わかってしまえば・・わからないこともないのですが、ここは「バッテリインジケーター+雷」がわかりやすいように思います。
(*)PD規格はバッテリ・ケーブルの相性問題が存在するので、ちゃんと充電できているかを確認するのはけっこう重要なポイントです。
Rバンドのカットオフ波長の最適値は?
https://jp.omsystem.com/product/astronomical/em1mk3_astro/index.html
赤の長波長側はどこまで透過するのが天体写真にとって一番最適なのでしょうか?
OMD ASTROの商品ページには「Hα線(656nm)に加えSⅡ線(672nm)までほぼ100%透過します」と書かれています。上の画像は商品ページに掲載されているOMD ASTROに使用されているUV/IRカットフィルターの分光特性グラフですが、少なくともSII線(672nm)まではほぼ100%の透過率があると推測されます。
一方で、従来の一眼カメラの天体改造サービスで使用されるUV/IRカットフィルターは、Hα線はほぼ100%透過するものの、それより長波長側は急激にカットされるものが多いようです(*)。つまり、OMD ASTROはSII線を100%透過するというメリットの代わりに「赤の長波長側の帯域が広い」結果となります。
(*)参考)https://www.hayatacamera.co.jp/astrophotography/

これは一長一短のトレードオフです。赤(Rチャンネル)の帯域が広いということは、Rチャンネル内での相対的なHα線の輝度が下がることを意味します。実写でもOMD ASTROは、他の天体改造機よりも若干Hαの赤い星雲の写りが弱いように感じました(*)。
(*)このOMD ASTROの特性は、天体専用のカメラであるASI6200MCPのUV/IRカットフィルターとほぼ同じ特性であり、それ自体が悪いというものではなく「できるだけ広いバンドの光を透過し、そこから先はユーザーに委ねる」といいう考え方です。また、Hα線が減衰しているわけではないので、HαのS/Nが低下するわけではありません。

SII線の感度が高いことはOMD ASTROの強みではありますが、一般にSII線の輝度は非常に低い上にHα線と同じ赤色なので、ナローバンドフィルターを使用する場合以外はほとんどリザルトに寄与しないでしょう。「赤い星雲がよく写る」ことをストレートに訴求するなら、SII線の透過率にこだわらない選択肢もあったかもしれません(*)。
(*)なお、同梱の光害カットフィルター(BMF-LPC01)を使用すればRチャンネルはだいぶ絞られるので、赤い星雲ははるかに良く写るようになります。また、長時間露光で星雲を強く強調する場合はHα線の赤が強くなりすぎる場合もあり「写りすぎるのはいいことばかりでもない」という逆のトレードオフもあります。目的によって得失の分かれる判断ではないかと思われます。
もっと「コンピューテーショナル・フォトグラフィー」を
ここまでは割と現実的?な要望でしたが、ここからはだいぶハードルの上がった要望になります。カメラに搭載された画像処理プロセッサでどこまでのパフォーマンスで実現できるのか?など、その分野の素人である筆者にはわかりかねるところもありますが、、世界の別の場所ではすでに実現していることばかりです。ぜひ、デジタルカメラという日本発のイノベーションを、さらに前進させてほしいと強く願うものです。
「ナイトモード」の実現

ライブコンポジット、ハイレゾショットやライブND、OM-1 MarkIIに搭載されたライブグラデーションNDなど、「コンピューテーショナル・フォトグラフィー」機能はOM SYSTEMの大きなコンセプトであり差別化機能となっています。
そこで「星撮り」のニーズから、さらなる展開をぜひ期待したいと思います。具体的には、まずは「手持ちハイレゾショット」をさらに進化させた「ナイトモード」の実現です。皆様ご存じの通り、昨今のスマートフォンには「ナイトモード」と呼ばれる「短秒多数枚スタックによる低照度被写体への対応」が実現されています。天の川がスマホの手持ち撮影でも写せる時代になったのです(*)。
(*)「もうデジカメはいらないのでは?」という気の早い意見もありますが、低照度下では「センサー面積」は物理法則からくる揺るぎのないアドバンテージです。フルサイズよりマイクロフォーサーズは4倍不利ですが、逆にスマホのセンサーと比較すると8倍有利です(1/2.3センサー(6.2×4.7mm)の場合、4/3センサー(17.2×13mm)の1/7.6の面積)。
もしOMDにナイトモードが搭載されれば(*)、高性能な手振れ補正機能ともあいまって、スマホよりもはるかに暗所でも良く写る(しかも手持ちで撮れる!)一眼カメラとなることでしょう。
(*)具体的には「ハイレゾにしない手持ちハイレゾショット」で、撮影枚数をより長く(200枚なら1/20秒露光で総露光4秒相当)設定できる形でしょうか。処理が重くなりすぎないようにビニングしてもいいと思います。
ダークライブラリによる長秒時ノイズ低減

もうひとつ。これは世の中全てのデジカメにいえることなのですが、「長秒ノイズ低減」はなぜ「毎回」ダーク画像を取得しなければならないのでしょうか。星空撮影で「長秒ノイズ低減」は一定の効果がありぜひ使いたいのですが、長秒撮影で「同じ時間だけ待たされる」ことは受忍しがたいところがあります。その日に最初に一度ダーク画像を取得しておけば、あとはそれを使い回すようにできないはずはない(*)と思うのですが、、この仕組みが実現すれば、前述の「手持ちハイレゾショットにおけるダーク減算」の解決にも利用できると思います。
(*)SharpCapなどの天体撮像ソフトや、最近急速に伸びている「スマート望遠鏡」では普通に実現されています。スマート望遠鏡では環境温度を記録することで、気温が一定範囲を超えて変動した際には再取得が要求される仕様の製品もあります。
より進んだ天体撮影用のセンサーキャリブレーション機能
天体撮影ソフト「ステライメージ10」に実装されたピクセルマッピング機能。ダーク撮像画像の輝度だけでなく、複数枚の画像における輝度値の散らばりがら異常値ピクセルの特性をグラフ化し、特定の傾向をもつピクセルをグラフ上のエリアを指定して無効化することができます。https://www.astroarts.co.jp/products/stlimg10/index-j.shtml
さらに、センサー固有の輝点などの「異常なピクセル」の影響を除去するために「ダーク画像を減算することが果たして最適解なのか?」という問題があります。最近のアマチュア天文家による研究では、天体撮影において悪影響を及ぼす異常ピクセルには幾つかのタイプがあり、ダーク減算で対処できるのは「常に輝点」となるピクセルだけで、「常に暗点」だったり「一定の値を取らず異常値が変動する」場合には無力であるというレポートがあります。
参考・ステライメージ10に『邪崇帝主』の機能が実装③
https://apranat.exblog.jp/37584435/
上のリンクにあるように、単純にダーク減算するのではなく、センサーのピクセル毎の挙動を事前に多数のダークファイルから分析し、異常ピクセルをまとめて補間(ピクセルマッピング)する手法が開発されています。このような機能がカメラ側で実現されれば、ダーク減算という処理そのものが不要になる可能性もあるかもしれません(*)。
(*)OMDのカメラには実は「ピクセルマッピング」という「撮像素子 (CCD や MOSセンサー) と画像処理機能のチェックと調整を同時に行う機能」があります。実行すると短秒と長秒のダークデータを4枚程度撮影しているようです。実際に試してみたのですが、実行の前後で同じ輝点が残っている場合もあり、顕著なダークノイズの変化は感じられませんでした。
2025.5.25追記)
ダーク減算とピクセルマッピングの効果を比較検証してみました。結論から言って「ダーク減算が不要になる可能性」という推測は過剰な期待でした。詳細は以下の一連のツイートに書いていますが、簡単にまとめると以下の通りです。
- ISO200/30分露光の比較では、ダーク減算による補正がはるかに勝る
- ダーク減算とピクセルマッピングを組み合わせると、より効果的な補正が可能
- ピクセルマッピングは少数(多くても全ピクセルの数%程度)の異常ピクセルを補正するには有効だが、長時間露光においては補正すべきピクセルの比率はかなり高く(5%程度でもまだまだ足りたい)「ピクセルを無効化する」アプローチは不適切
「長秒1枚撮り」におけるピクセルマッピングによる輝点・暗点ノイズ補正について検証してみました(長文)。
狙いは2つありました。… pic.twitter.com/HO1npPjBor — 天リフ編集部 (@tenmonReflexion) May 23, 2025
カラーバランスの自動調整

星空の色温度は何度なの?とても難しい問題です。市街光や薄明光、大気光などさまざまな外部要因で星空のカラーバランスは「一概に言えない」のです。さらに、OMD ASTROに同梱されている「光害カットフィルター」を使用すると大きくカラーバランスが崩れます(*)。
(*)OMD ASTROの「C1」「C2」のカスタムモードではデフォルトのカラーバランスが天体用カメラを想定した設定になってはいるのですが、光害カットフィルターを使用すると青に大きく転びます。希望を言えば「光害カットフィルター使用時用のプリセット」も欲しかったところ。
しかし「なんとなくカラーバランスを合わせる」ことは、ソフトウェアで簡単に実現できます(*)。星空撮影用途に「ホワイトバランスを撮像画像から自動的に調整する(背景の空がニュートラルグレーになるように調整する)機能があると、アストロモデルがより使いやすくなるのではないでしょうか。
(*)多くの天体撮像・画像処理ソフトやスマート望遠鏡に実装されています。
デコンボリューションによる超解像と収差補正

ここ数年、天体写真において「デコンボリューション(逆畳み込み法)」による超解像処理が急速に広がりました(*)。これは古くからある理論的に確立された超解像手法です。
(*)現時点では画像処理ソフトウェアPixInsightのアドイン機能であるBXT(BlurXTerminator)が優秀でほぼ一択の状況です。理想的な結像からどのように画像が崩れているかを示す「PSF関数」をAIによって自動生成するようです。
天体写真においてBXTの効果は圧倒的で、本記事の作例画像でも多用していますが、ディテールを描出するだけでなくカメラレンズの積年の課題である「周辺の流れ」を飛躍的に補正し点像にする効果があります。もしこの機能がカメラ側・ないしはアストロモデル付属のソフトウェアで簡単に実行できるようになれば、飛躍的にリザルトの質があがることでしょう。天体写真においては(*)レンズの収差をこれ以上改善する必要がないと思えるほどの効果があるのです。
(*)天体写真は一般写真と異なり「常に点像であるはずの被写体=星」が画像全体にくまなく分布しています。このため、デコンボリューションのためのPSF関数の推定がより簡単になるメリットがあります。逆に、一般の写真に対してBXTを行うと、ただの画像上のテクスチャーを星(本来点像であるべき対象)だと誤認してアーティファクトが多く出てしまいます。その意味ではBXTは「星専用」のツールです。
スマート望遠鏡におけるトレンド

「より簡単に、見栄えの良い天体画像を取得する」という意味で、今最もホットなのは「スマート望遠鏡」の分野です。スマート望遠鏡は5年ほど前に市場に出てきた「デジタル天体望遠鏡」です。当初は単純なライブスタッキングとオートストレッチを活用した天体撮影ツールでしたが、最近ではより高度なAIノイズ低減、観測衛星のデータを使用した色補正・強調、(おそらく前述のデコンボリューションに相当すると思われる)超解像処理、自動モザイク合成(ステッチング)などが実現されています。
デジタルカメラとスマート望遠鏡は本来成り立ちの異なるもので一括りにはできませんが、「天体用デジタル一眼」のユーザー層・ユーザーニーズとの共通点は多いといえるでしょう。市場的にはすでに「ライバル」なのかもしれません。ぜひスマート望遠鏡に一泡も二泡も吹かせられるようなテクノロジの実現に期待します。
まとめ

いかがでしたか?
大事なことなので何度も言いますが、「フォーサーズのカメラは星には不向き」というのは過去の話です。センサー面積がフルサイズの1/4という不利はあるものの、それを補う別のメリットがたくさんあるのが「フォーサーズ」。アウトドア仕様の軽量なボディとレンズシステムのメリットを生かし、貴方を「フルサイズのカメラでは行けない・行こうとはしない」ような場所に連れて行ってくれます。
しかもOMDには「星空AF」や「手持ちハイレゾショット」「ライブコンポジット」などの優れた「コンピューテーショナル・フォトグラフィー」機能が数多く備わっています。
そんなOM STSTEMのカメラとOMD ASTRO。貴方はこのカメラを手にして、どんな冒険に出かけられますか?
- 本記事はOMデジタルソリューションズ様 より協賛および機材貸与を受け、天文リフレクションズ編集部が独自の判断で作成したものです。文責は全て天文リフレクションズ編集部にあります。
- 記事に関するご質問・お問い合わせなどは天文リフレクションズ編集部宛にお願いいたします。
- 本記事の作例画像は特に注記のない限り、天体撮影用の強い画像処理を行っています。カメラの「撮って出し画像」とは大きく異なります。
- 製品の購入およびお問い合わせはメーカー様・販売店様にお願いいたします。
- 本記事によって読者様に発生した事象については、その一切について編集部では責任を取りかねますことをご了承ください。
- 特に注記のない画像は編集部で撮影したものです。
- 記事中の製品仕様および価格は注記のないものを除き執筆時(2025年3月)のものです。
- 記事中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。
補足)
本項ではOMD ASTROにおける様々な検証や、より詳しい解説をまとめています。
天体用カメラの仕組み
本節では一般的なデジタルカメラと「天体用カメラ」の構造の違いについて簡単に解説します。一般的なデジタルカメラの仕組みから見ていきましょう。
CMOSセンサーの「素の」感度特性
まず、CMOSセンサーそのものは紫外線から近赤外線まで広く感度を持っています。もし仮にこのままの特性でデジタルカメラを実現するとどうなるでしょうか?
ベイヤーセンサーの色別感度特性
https://www.zwoastro.com/product/asi6200/
カラータイプのイメージセンサーはベイヤー型配列と呼ばれる赤・緑・緑・青の4つのピクセルが一組になり、色情報と輝度情報を取得しますが、各色それぞれの感度特性はだいたい上の画像のような感じです。
UV/IRカットフィルター
OMD ASTROのUV/IRカットフィルター特性
このままでは2つ問題があります。一つめは写真にとって有害な紫外線と近赤外線にも感度を持ってしまうこと。どちらも人間の眼では感度のない(感度が極めて低い)光なので、眼で見たイメージとは異なるイメージが記録されてしまいます(*)。このため、多くのデジタルカメラには「UV/IRカットフィルター」という紫外線と近赤外線を鋭くカットする「干渉型」のフィルターが使用されます。
(*)理由は実はこれだけではありません。レンズのコーティングや色収差補正は近赤外線を想定していないものがほとんどであり、近赤外線が入ってくるとフレアやゴーストが一気に増大します。またカメラによってはメカ制御のために近赤外線を照射するパーツが組み込まれていることがあり、これを遮断しないとかぶりが発生する場合があります。
色調整フィルター
住田光学ガラスSC807シリーズ https://www.sumita-opt.co.jp/ja/products/ir-sc807.html
しかしUV/IRカットフィルターだけでは不十分です。近赤外線と紫外線をカットしてもなお、CMOSセンサーの色別の感度特性は人間の眼とは乖離があります。主に「長波長(赤;波長600〜700nmくらいの間)の感度が高すぎる」のが問題になります(*)。
(*)他にも理由があるかもしれません。
そこで、UV/IRカットフィルターに加えて上の画像の「ような(*)」感度特性を持つ水色の「色調整フィルター」と呼ばれるものが使用されます。このフィルターは「色ガラス型」のフィルターで、斜入射光による特性の変化が比較的少ないものです。
(*)住田光学様の製品は筆者がネットで見つけただけで、デジタルカメラに実際に使用されているのかどうかは不明です。
筆者の知る限りにおいては、ほとんど全ての一般向けデジタルカメラのイメージセンサーの前には、上記の「UV/IRカットフィルター」と「色調整フィルタ−」の2つが配置されています(*)。
(*)もうひとつ「ローパスフィルター」と呼ばれるベイヤーセンサーの偽色・モアレ対策のためのフィルターがありますが、最近の高画素のカメラでは省略される製品も多くなりました。またメーカーによっては全てのフィルターを総称して「ローパスフィルター」としている場合もあるようです。
この「2つのフィルターを組み合わせる」という手法が一般向けデジタルカメラの重要なポイントです(*)。
(*)色補正フィルターだけでは有害な赤外線を完全に除去できず、UV/IRカットフィルターだけでは肉眼で見たとおりのイメージにならないのです。また、色ガラス式の色補正フィルターで長波長側をなだらかに落とすことは、干渉型フィルターの斜入射光問題も緩和してくれるのでしょう。
天体用カメラの仕組み
ハヤタカメララボ・天体写真撮影用/赤外写真撮影用デジタルカメラ改造処理のご案内
https://www.hayatacamera.co.jp/astrophotography/
では、天体用カメラの仕組みはどうなっているのでしょうか。考え方としては「UV/IRカットフィルター」と「色調整フィルター」を別の組み合わせに変更することになりますが、現在の主流は「色調整フィルターを除去し素通しのガラスフィルター(*)に換装する」というものです。
(*)フィルターを除去するだけだとレンズに対する光路長が変動し収差増大の原因となってしまいます。このため「同じ厚み」の透明なフィルターに換装することで光路長を一定にします。また、カメラによっては色調整フィルターとUV/IRカットフィルターが一体化されている場合もあり、その場合は全てのフィルターを除去し同じ光路長のUV/IRカットフィルター(目的によっては透明ガラス)と換装することになります。
天体専用のCMOSカメラの場合は、透明なカバーガラスで密封されUV/IRカットフィルターはユーザー側で必要に応じて使用する想定の製品と、密封用カバーガラスにUV/IRカットフィルターを使用している製品(*)の2つのタイプがあります。
(*)フィルターはゴーストの原因にもなるため、できるだけフィルターを少なくするという考え方です。
OMD ASTROの場合は「UV/IRカットフィルター」をより長波長側のカットオフをより広げたものを使用し、色調整フィルターのかわりに透明なガラスが使用されているものと考えられます。
ノーマルカメラのHα線透過率の違い

住田光学ガラスのHPを見ると、水色の「色調整フィルター」の特性にはバリエーションがあります。主にどれくらい長波長側を減衰させるかの違いと推測しますが、あるカメラがどんな目的でどんな特性の色調整フィルターを使用しているかについては筆者の知見ではわかりません。
ただ、天体写真界隈では「Hα線がよく写る」カメラと「あまりHα線が写らない」カメラがあると言われています。また、富士フイルムは「当社のカメラは天体写真のためにHα線の透過率をあまり下げないようにしている」と明言しています。色調整フィルターを除去しなくても、ある程度Hα線の写りをよくすることは「色調整フィルター」の特性を変えることで可能であるといえるでしょう。
ただし、今回筆者は手持ちのノーマルカメラの写りを実写比較しましたが、メーカー・機種による顕著な違いは見出すことができませんでした。本項は筆者の少ない経験による感想である、とご理解ください。
検証)ボディマウントフィルターによる星像悪化
https://jp.omsystem.com/product/astronomical/em1mk3_astro/index.html
OMD ASTROには「ボディマウント型」のフィルターが2種付属します。BMF-LPC01は光害カットフィルター、BMF-SE01はソフトフィルターで、フロント装着型のフィルターと違ってレンズを交換しても同じ効果のフィルターを使用できるメリットがあります。
ただし、薄型(肉厚0.5mm程度)とはいえ、光学系の間に「異物」であるフィルターを入れると、何らかの結像悪化要因となります。それを実写で検証してみました。結論を先にいうと超広角レンズほど周辺像に大きな影響があります(*)。
(*)これは薄い平面ガラスによって主に非点収差が発生することと、光路長が変化しレンズ側のピント位置が変動することで「近距離補正」がズレることが原因であると推測しています。
M.ZUIKO DIGITAL ED8mmF1.8Fisheye
フィルターを入れると放射状方向の流れがわずかに増大しましたが、像の悪化はさほどないとみてよいと思います。筆者が所有する魚眼レンズ(キヤノン8-15mmF4L、シグマ15mmF1.4)でも顕著な星像変化はありませんでした。魚眼レンズはリアフィルター適性が良好だと考えてよいでしょう。
M.ZUIKO DIGITAL ED7-14mmF2.8広角端
フィルターを使用すると最周辺ではかなり流れます。この流れがどのくらい許容できるかは個人の好みと作画意図によるとは思いますが、星のクオリティを重視する撮影では避けた方が無難そうです。
なお、流れは広角端ほど大きくなります。望遠端でも影響はありますが、流れは少なくなります。
M.ZUIKO DIGITAL ED17mmF1.2
フィルターを使用することで結像状態は若干変化しやや肥大しますが、悪くなったという感じは受けません。このレンズの場合は心配せず使って問題なさそうです。
M.ZUIKO DIGITAL ED40-150mmF2.8 望遠端
フィルターの使用による結像状態の変化はほとんどありません。ソフトフィルターによる滲み効果の違いと、ピント合わせ精度の違いのほうが大きそうです。筆者の経験則でも望遠レンズにおいては厚めのフィルターであっても結像変化はほとんどありません(当たり前ですが、焦点位置の移動は光路長変化の分だけあります)。望遠系のレンズの場合は心配なくフィルターを使っても大丈夫でしょう。
検証)星空AF
検証概要
OMDの星空AF(*)の合焦精度を検証しました。4本のレンズについて、熟練者によるマニュアルフォーカス、星空AF(速度重視)、星空AF(精度重視)のそれぞれを5回行い、結果を比較しています。また、ボディ内ソフトフィルター(BMF-SE01)の有無の比較も行いました。
合焦エリアは最も小さい枠に設定し、枠内に中心近くの明るい星を設定してAFまたはMFを実行しています。
M.ZD ED 7-14mmF2.8 PRO
星空風景の撮影で最も多用されるであろうF2.8広角ズームです。MF・AFともに歩留まりは100%といえます。このレンズをはじめ、広角系のレンズでは速度重視と精度重視に顕著な差は感じられませんでした。精度重視の方が安定している感じですが、速度重視の方がAFが速く完了するので、どちらを選ぶかは撮影者の目的と撮影シーン次第と感じました(*)。
(*)筆者なら、通常は速度重視で使用すると思います。また、ピントを外したくないケースでは撮影後に撮像画像をモニタでチェックすることになるでしょう。
M.ZD ED 8mm F1.8 Fisheye PRO
モニター上で見える星が一番少ないと思われる対角線魚眼レンズの場合です。星空AFは1コマ(ソフト使用・速度重視の1枚目)を除き、ほぼジャスピンといえるでしょう。
このレンズのように、若干星像径が大きく、ピントの山がややつかみにくい傾向がある場合は星空AFの恩恵が大きくなると感じました。MFで星にピントを合わせることは、ある程度慣れれば慎重に行うことで外すことはあまりないのですが、モニタを拡大してピントを合わせて元に戻すなど、けっこう手間も神経も使います。「精度良くピント合わせする」だけでなく「ピント合わせを楽に済ませる」ことができるのも、星空AFの大きなメリットだと感じました。
M.ZD ED 17mmF1.2 PRO
星空AFは絞り値の設定によらず常に絞り開放で実行されているようです。このレンズは若干「くせ玉」で、絞り開放では中心部の星に大きなハロが生じるのですが、そんな場合でも星空AFが正しく実行されるかを確認してみました。
結果は何の問題もありませんでした。星空AFは天体望遠鏡の電動フォーカサー(EAF)によるAFと基本的には原理は同じで、ピント位置を少しづつずらして星のボケ量のグラフを描き、一番「谷底(星像径が最も小さい)」になる合焦ポイントを導き出していると推測していますが、少々の収差が残存していても「谷底」の判定には問題ないのでしょう。
ただし、軸上色収差や球面収差によるハロを「天体写真的に最適化」したい場合に星空AFが全てを解決してくれるとは思わない方がよいかもしれません。ただし、今回使用したZDレンズではそこまでの細かな調整は必要ありませんでした(*)。
(*)例えば、若干軸上色収差の大きい「M.ZD75mmF1.8」を開放近くの絞り値で使用する場合はピント位置の調整で青ハロが減るかもしれませんが、やや絞って収差を低減させれば星空AF任せでも充分でした。
M.ZD ED 40-150mmF2.8 PRO
今回使用したレンズの中で最も長焦点のF2.8望遠ズームです。長焦点レンズのMFは、ピントリングを回す際にブレで星が踊ってしまうことがあり、ピント合わせに苦労することが多いのですが、星空AFなら楽ちんでした。
ただし「速度重視」の設定では若干ピントの歩留まりが低いように感じられます。望遠レンズの場合「精度重視」の設定にした方が良いかもしれません。
望遠レンズでは、大気の揺らぎの影響を受けやすくなるため、MFでもAFでも、ベストのピント位置を決めるのが難しくなります。星空AFは大変有効なツールですが、最終的には「撮像画像を拡大しピントを確認する」ことが重要です(*)。
(*)とはいえ、星空AF頼りでも、さほど大きな失敗は起きないものと思います。
星空AFに失敗するケース
星空AFはとても便利で有用なツールですが、万能ではありません。フォーカスエリアに目立った星が存在しない場合(*1)など、星空AFが失敗することもあります。AFに成功したときの「ピッ」という合焦音を確認することは必須です(*2)。
(*1)今回合焦エリアを最も狭く設定したため、毎回星のある場所に合焦エリアを調整しましたが、けっこう面倒です。その点では、合焦エリアを広めに設定したほうがよいのかもしれません。
(*2)画面上にも赤文字で「星空AFが完了しませんでした」と表示してくれるとより便利なのですが、、
また、レンズによっては星空AFとの相性の悪いレンズも存在するようです。筆者の環境では、M.ZD ED 12mmF2.0では一度も星空AFが成功しませんでした。
いずれにしても、より少ないアクションでピント合わせができる「星空AF」は、OMD(*)の「キラー機能」の1つといえます。高齢者にとっては、特に便利なものとなることでしょう。
(*)星空AFは「OMD ASTRO」だけでなく、E-M1 MarkIII、OM-5、OM-1、OM-3シリーズでも使用することができます。
筆者が行ったカスタム設定
- ピント拡大(ライブビュー画面の表示を拡大する機能)をB1メニューで露出補正ボタンに割当。(アストロモデルC1/C2の設定と同じ)。この設定はメニューの中深くに入っていて、見つけ出すのにけっこう苦労します。
- LVブースト(D2)を録画ボタンに割当。(アストロモデルC1/C2の設定と同じ)
- フォーカスロック。B1メニューでISOボタンに割当(アストロモデルC1/C2の設定と同じ)。この機能はピントリングの操作を無効にするもので、露よけヒーターを巻き付けたような場合に不用意にピントがずれることを防ぐことができます。
- レンズリセット(A1)。OFFに設定。ONのままだと電源OFF時にピントが初期状態にリセットされてしまいます。(アストロモデルでは初期設定)
- 液晶モニタ・EVFの自動切替(I)はOFFに。老眼者がモニターをガン見するとEVFに切り替わってしまうので。
- 撮影確認(セットアップメニュー)を2秒に設定(初期状態はOFF)。
- MFアシスト(A4 )。この設定はピントリングを回すと拡大表示に切り替わるものです。当初ONにしましたが、拡大をボタンに割り当てておけば、OFFのままが使いやすいと感じました。

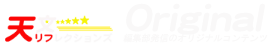
コメントを残す