オールドレンズによる天の川モザイク
編集部ピックアップ、今日の一枚。

撮影:平岡保彦様
さそり座からいて座にかけての、3枚モザイクによる広角星野です。
青い馬星雲やさそり座δ星周辺の淡い光芒から、複雑に入り組んだ暗黒星雲を経て天の川の中心部までが、モザイクならではの細密なクオリティで描き出されています。
実はこの作品、完成度の高さだけではなく、いくつもの驚くべきポイントがあります。少しかなり長くなりますが、以下ご紹介してゆきます。
非天体改造カメラを使用している
使用されたカメラはフジのX-E1。APS-Cサイズの1600万画素のセンサーをもつ、重量わずか300gのコンパクトなミラーレスカメラです。2012年発売、現在の市場価格は約5万円。
フジのカメラは、IR改造しなくても波長656nmで輝く赤い散光星雲がよく写ることが知られていますが、フルサイズのIR改造カメラと比較してまったく遜色のない写りです。
30年前のオールドレンズを使用している
使用されたレンズは今は無きミノルタのMCロッコールPG50mmF1.4。1970年代後半のレンズで、非球面レンズも特殊低分散ガラスも使っていない、5群7枚のいわゆる当時の「標準レンズ」。
重量はわずか300g。現在は中古カメラ店で数千円、ひょっとすればジャンク品扱いです。
6枚絞り羽根
アンタレスの光条が6本になっているのは、絞り羽根が6枚のため。現代のレンズでは「円形絞り」が主流なのでこの形にはなりません。例えば、9枚の絞り羽根の場合は光条は18本、いわゆる「ウニ」になります。
点光源のボケが六角形や八角形になることが嫌われてほぼ絶滅した6枚・8枚の偶数絞り羽根の「非円形絞り」レンズですが、星野写真にはこの6本光条はなんともいえない味わいです。
古いレンズコーティング
最近のレンズは10層以上のマルチコーティングがざらですが、このレンズは一部の面を除き単層コーティングです。20枚近くのエレメントから構成される最近のレンズではマルチコーティング技術は必須なのですが、構成群が5群と少ないこのレンズではそのデメリットはあらわには出ず、むしろ天体用には「明るい星がわずかに滲む」という効果となって、これまたなんともいえない味わいを示しています。
絞りF4でイメージサークルの中心部のみを使用
非球面も特殊ガラスも使用しないオールドレンズは、周辺部の収差が多く残り、開放近くでは昨今の天体写真の要求レベルを満たす画質にはなりにくいのですが、この作品の場合APS-Cセンサーのため必然的に使用するのは中心部のみ。
しかも開放F1.4のレンズをF4まで絞りこむことにより、現代の高性能レンズに劣らない素晴らしい良像となっています。
一部ではこの手法は「大吟醸モザイク」と呼ばれているようです。
JPEG1枚撮り画像
この作品、3枚モザイクではありますが、コンポジットはされておらず、しかもカメラ出力のJPEG画像によるものです。
「天体写真はRAWで!」というのは、基本中の基本として語られている事実なのですが、「なんでもかんでもRAWでなければダメ!」ではないことを、この作品が雄弁に語っています。
RAW撮影が有効なのは、極端に露出不足・露出過剰になる場合や、輝度レンジの狭い範囲を持ち上げあぶり出す場合、高輝度部と低輝度部の差が激しい場合などですが、天の川中心部のような明るい被写体の場合、「適正露出」をコントロールすればJPEG出力でも十分な階調が得られるのです。
この作品の場合、F4/ISO1600/6分とじゅうぶんな露出を与えたことがJPEGでも良好な画質が得られた理由の一つでしょう。
逆に、さそり座付近の淡い部分もしっかり描出されているのは、作者の画像処理技術の賜物です。
まとめ
今日はなんとも熱く長く語ってしまいました^^;;;
天体写真のさまざまな楽しみ方を垣間見ていただければと思います。
参考リンク)
出品者のひとりごと・・
MINOLTA (ミノルタ) MC ROKKOR – PG 50mm / f1.4
https://reflexions.jp/tenref/gallery/2017/07/07/1385/https://reflexions.jp/tenref/gallery/wp-content/uploads/sites/3/2017/07/0707hiraoka-1024x525.jpghttps://reflexions.jp/tenref/gallery/wp-content/uploads/sites/3/2017/07/0707hiraoka-150x150.jpg深宇宙星野編集部ピックアップ、今日の一枚。 撮影:平岡保彦様 さそり座からいて座にかけての、3枚モザイクによる広角星野です。 青い馬星雲やさそり座δ星周辺の淡い光芒から、複雑に入り組んだ暗黒星雲を経て天の川の中心部までが、モザイクならではの細密なクオリティで描き出されています。 実はこの作品、完成度の高さだけではなく、いくつもの驚くべきポイントがあります。少しかなり長くなりますが、以下ご紹介してゆきます。 非天体改造カメラを使用している 使用されたカメラはフジのX-E1。APS-Cサイズの1600万画素のセンサーをもつ、重量わずか300gのコンパクトなミラーレスカメラです。2012年発売、現在の市場価格は約5万円。 フジのカメラは、IR改造しなくても波長656nmで輝く赤い散光星雲がよく写ることが知られていますが、フルサイズのIR改造カメラと比較してまったく遜色のない写りです。 30年前のオールドレンズを使用している 使用されたレンズは今は無きミノルタのMCロッコールPG50mmF1.4。1970年代後半のレンズで、非球面レンズも特殊低分散ガラスも使っていない、5群7枚のいわゆる当時の「標準レンズ」。 重量はわずか300g。現在は中古カメラ店で数千円、ひょっとすればジャンク品扱いです。 6枚絞り羽根 アンタレスの光条が6本になっているのは、絞り羽根が6枚のため。現代のレンズでは「円形絞り」が主流なのでこの形にはなりません。例えば、9枚の絞り羽根の場合は光条は18本、いわゆる「ウニ」になります。 点光源のボケが六角形や八角形になることが嫌われてほぼ絶滅した6枚・8枚の偶数絞り羽根の「非円形絞り」レンズですが、星野写真にはこの6本光条はなんともいえない味わいです。 古いレンズコーティング 最近のレンズは10層以上のマルチコーティングがざらですが、このレンズは一部の面を除き単層コーティングです。20枚近くのエレメントから構成される最近のレンズではマルチコーティング技術は必須なのですが、構成群が5群と少ないこのレンズではそのデメリットはあらわには出ず、むしろ天体用には「明るい星がわずかに滲む」という効果となって、これまたなんともいえない味わいを示しています。 絞りF4でイメージサークルの中心部のみを使用 非球面も特殊ガラスも使用しないオールドレンズは、周辺部の収差が多く残り、開放近くでは昨今の天体写真の要求レベルを満たす画質にはなりにくいのですが、この作品の場合APS-Cセンサーのため必然的に使用するのは中心部のみ。 しかも開放F1.4のレンズをF4まで絞りこむことにより、現代の高性能レンズに劣らない素晴らしい良像となっています。 一部ではこの手法は「大吟醸モザイク」と呼ばれているようです。 JPEG1枚撮り画像 この作品、3枚モザイクではありますが、コンポジットはされておらず、しかもカメラ出力のJPEG画像によるものです。 「天体写真はRAWで!」というのは、基本中の基本として語られている事実なのですが、「なんでもかんでもRAWでなければダメ!」ではないことを、この作品が雄弁に語っています。 RAW撮影が有効なのは、極端に露出不足・露出過剰になる場合や、輝度レンジの狭い範囲を持ち上げあぶり出す場合、高輝度部と低輝度部の差が激しい場合などですが、天の川中心部のような明るい被写体の場合、「適正露出」をコントロールすればJPEG出力でも十分な階調が得られるのです。 この作品の場合、F4/ISO1600/6分とじゅうぶんな露出を与えたことがJPEGでも良好な画質が得られた理由の一つでしょう。 逆に、さそり座付近の淡い部分もしっかり描出されているのは、作者の画像処理技術の賜物です。 まとめ 今日はなんとも熱く長く語ってしまいました^^;;; 天体写真のさまざまな楽しみ方を垣間見ていただければと思います。 参考リンク) 出品者のひとりごと・・ MINOLTA (ミノルタ) MC ROKKOR – PG 50mm / f1.4 編集部山口 千宗kojiro7inukai@gmail.comAdministrator天文リフレクションズ編集長です。天リフギャラリー

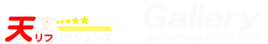






平岡保彦さんの写真は素晴しい出来栄えですね!
Hαの赤色星雲を写すための改造カメラは天文ファンのステータスですが、普通に考えたら常軌を逸した無茶な改造ですよね? 星野が良く写るカメラにHαの波長をカットしてあるのが多いので仕方ないですが…。
フジは昔からHαがけっこう写ります。フジは天体写真の大御所のSさんが勤めていらしたことと関係があるかも? 最近ではペンタックスやオリンパスも良く写ります。ペンタのK1はニコンの天体用810Aと同じくらい写るかな? 白熱電球が少なくなると赤の波長を伸ばしたカメラが増えるのかもしれない。
無茶な改造をしないで済むカメラをどしどし紹介していってください。
周囲にはK1使いの方がけっこういらっしゃって、もちろん無改造ですがしっかり赤が出るそうです。手持ちの5D3は悲しくなるほど赤が出ません・・結局、N、C以外はちゃんと赤が出るということなのでしょうか。
入門者にとっての「改造」のハードルの高さは経験があるのでとてもよくわかります。「無理に改造しないでいいから、とにかく撮ってみよう!」というメッセージをこれからも出していきたいと思っています。